テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
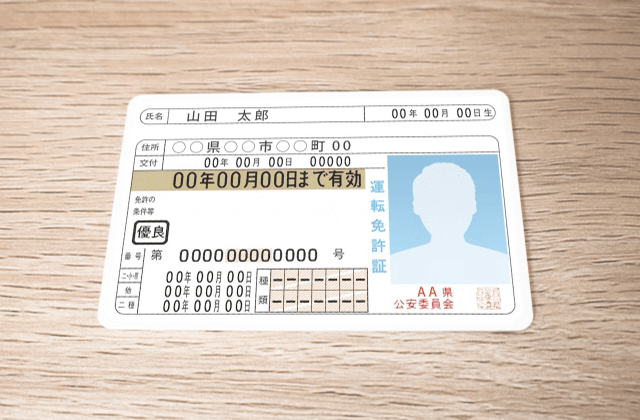
車とバイク、免許取得の年齢制限が異なるわけ
「普通自動車運転免許」を取得できるのは満18歳以上となっています。一方、「原付免許」や「普通二輪免許」(400ccまでのバイク)などの二輪車を運転できる免許は満16歳以上で取得可能です(400cc超のバイクは「大型二輪免許」となり18歳以上で取得可能)。ではなぜ年齢制限に違いがあるのでしょうか。少し経緯を掘り下げてみましょう。
全国統一の免許制度としては、1919年(大正8年)に交通法規「自動車取締令」が作られます。これによって免許取得可能年齢は一律18歳以上と定められたようです。こののち1933年(昭和8年)には「自動車取締令」が改正され、「普通免許18歳以上」「小型免許16歳以上」という区分が生まれています。ここでの小型免許とは「750ccまでの四輪車(小型自動四輪車)や小型自動三輪車、自動二輪車といったものを運転できる免許」です。
また昭和前期ごろの高校進学率が極めて低かったことも関係しています。当時、中学を卒業して働きに出ることは一般的なことでした。そういった人たちが学校を卒業後、オート三輪や自動二輪などの免許を取得して働けるように16歳で免許を取得できる制度が整えられたということのようです。
この後、1960年(昭和35年)にはそれまでの「自動車取締令」に代わって「道路交通法」が施行されます。このとき、「小型免許」は廃止されて「普通免許」に統合されますが、二輪車だけは別枠として残ります。こうしてバイクに関しては現在まで16歳以上のままということのようです。
また、韓国では原付であれば16歳以上、それ以上の排気量のものは18歳以上となっています。中国では原付等の区分なく18歳以上から取得可能となっているようです。一般的には18歳以上で取得できるところが多いようです。
過去の免許制度には「小型免許」があった
日本ではじめての自動車が走ったのは1898年(明治31年)のこととされています。その後、自動車の台数は一気に増えていき、地域の免許制度が制定されはじめます。1912年(明治45年・大正元年)の全国自動車保有台数は500台程度とかなり貴重なものでしたが、12年後の1924年(大正13年)には2万台以上に増えたようです。全国統一の免許制度としては、1919年(大正8年)に交通法規「自動車取締令」が作られます。これによって免許取得可能年齢は一律18歳以上と定められたようです。こののち1933年(昭和8年)には「自動車取締令」が改正され、「普通免許18歳以上」「小型免許16歳以上」という区分が生まれています。ここでの小型免許とは「750ccまでの四輪車(小型自動四輪車)や小型自動三輪車、自動二輪車といったものを運転できる免許」です。
「道路交通法」で残された自動二輪車
オート三輪といえば、昭和の高度経済成長の時代を描く映画や記録映像などでは必ずといっていいほど登場する、あの懐かしの乗り物です。ダイハツミゼットといった車種は聞いたことがある人もおおいのではないでしょうか。当時はこういったオート三輪が配達に使われたり、さまざまな生活物資の運搬に使われたりしています。オート三輪はいわゆる庶民の足でした。また昭和前期ごろの高校進学率が極めて低かったことも関係しています。当時、中学を卒業して働きに出ることは一般的なことでした。そういった人たちが学校を卒業後、オート三輪や自動二輪などの免許を取得して働けるように16歳で免許を取得できる制度が整えられたということのようです。
この後、1960年(昭和35年)にはそれまでの「自動車取締令」に代わって「道路交通法」が施行されます。このとき、「小型免許」は廃止されて「普通免許」に統合されますが、二輪車だけは別枠として残ります。こうしてバイクに関しては現在まで16歳以上のままということのようです。
海外では18歳以上が一般的
では海外の事情はどうなっているのでしょうか。アメリカの状況は州によって異なりますが、一般的には車・バイク共に16歳以上で取得できるところが多いようです。ただしエリアが限定されているなど条件がある州も多いようです。アメリカは土地が広いことから、車やバイクなどの移動手段がないと生活に不便であることが関連しているようです。また、韓国では原付であれば16歳以上、それ以上の排気量のものは18歳以上となっています。中国では原付等の区分なく18歳以上から取得可能となっているようです。一般的には18歳以上で取得できるところが多いようです。
<参考サイト>
なぜクルマの「運転免許」は18歳から? バイクは16歳からなのに… 年齢制限が異なる理由とは|くるまのニュース
https://kuruma-news.jp/post/539383
明治?大正?「運転免許」はいつからできた?|GAZOO
https://gazoo.com/column/daily/20/03/12/
自動車免許はいつから必要になった?免許の歴史を徹底解説|武蔵境自動車教習所
https://musasisakai-ds.co.jp/blog/31171/
バイクの免許「16歳から取得可能」は早すぎるのか? 世界の国々と比べてみると……|モーサイ
https://mc-web.jp/life/column/99794/
なぜクルマの「運転免許」は18歳から? バイクは16歳からなのに… 年齢制限が異なる理由とは|くるまのニュース
https://kuruma-news.jp/post/539383
明治?大正?「運転免許」はいつからできた?|GAZOO
https://gazoo.com/column/daily/20/03/12/
自動車免許はいつから必要になった?免許の歴史を徹底解説|武蔵境自動車教習所
https://musasisakai-ds.co.jp/blog/31171/
バイクの免許「16歳から取得可能」は早すぎるのか? 世界の国々と比べてみると……|モーサイ
https://mc-web.jp/life/column/99794/
人気の講義ランキングTOP20










