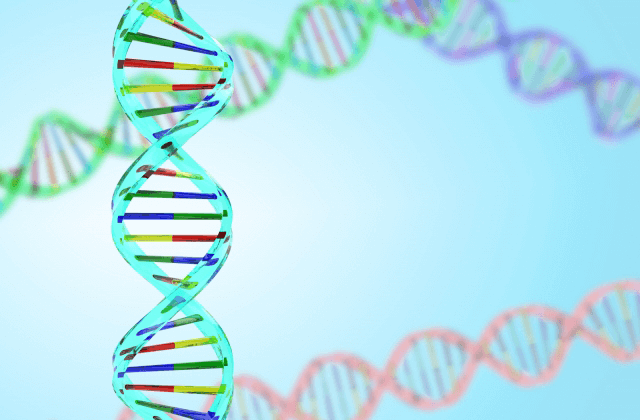
『環境DNA入門』が教えてくれる「ただよう遺伝子」の世界
生き物の設計図とも呼ばれるDNA。わたしたちの体の形を決める大切な遺伝情報を担っており、科学に詳しくない人でも、二重螺旋構造の図は見たことがあるはずです。このDNAについて探求する学問はこの世に数多存在しますが、その中でも「環境DNA」という言葉を、皆さんは聞いたことはありますでしょうか。
じつは、地球上の生物はDNAを体から排出しながら生きています。尿や便などの排泄物、髪の毛や体毛、代謝によって剥がれ落ちた皮膚など、これらにはすべてDNAが含まれています。そして、それは人間だけでなく、あらゆる地球上の生命にもいえることです。この環境中に排出されたDNAのことを「環境DNA」と呼ぶのです。
今回ご紹介するのは、神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授である源利文先生の著書『環境DNA入門 ただよう遺伝子は何を語るか』(岩波科学ライブラリー)です。サブタイトルに見る〝ただよう〟とは、決して比喩ではありません。そんなDNAが〝ただよう〟世界を覗いていきましょう。
〈水槽の中には、カルキ抜きをした水道水と一匹のコイのみ。このDNAは一体「誰の」DNAだろうか〉
そう思った源先生は、DNAを詳しく分析していきます。すると、DNAはコイに由来するものでした。これまで排出されたDNAは消失するものと考えられていたけれども、もしかしたら、川や湖などの水を汲んで、その中に含まれるDNAを調べたら、そこに生息している生物がわかるかもしれない。ということで、この研究がはじまったのは2009年のことでした。そこから、先生は数多くの実験を行っていきます。
しかし、研究を進め発表にまでたどりついたものの、学会の反応は芳しいものではなかったそうです。そのときの様子を、源先生はこう語ります。
「演台から見れば話を聞いているかどうかはひと目でわかる。(中略)何を言っているんだコイツはという顔をしている。どうやら、水をくんで魚のDNAを検出するなんていうアホらしいことができるはずがないと思われてしまったようだ」
それほど、ある環境からDNAを検出するということはあり得ないことだと思われていたのかもしれません。しかし、この分野は各国の研究チームが注目していることもあり、じつは競争の激しい分野となっていたのです。源先生は2011年に一番乗りで論文を発表。そのわずか1カ月後にヨーロッパのチームが論文を提出しているため、接戦をくぐり抜けたわけです。
例えば、3章の「いるかいないか」という部分では、希少種であるゼニタナゴの検出が実例として語られています。99カ所から水のサンプルを用意し、そのうち2箇所が陽性。つまり「いる」という反応が出ました。実際その箇所を調べてみると、なんと11年ぶりにゼニタナゴの成魚が発見されたのです。
「環境DNA分析を端緒に繁殖地の特定まで至ったケースは、おそらく世界初である。このように本来の生息地・繁殖地を守ることは、希少種の保全にとっても重要なことであり、環境DNA分析が実用的にも役に立つ可能性を示すことができた」と、源先生は語っています。
4章に関していえば、川や湖などで水を汲み調べることで、そこに生息している魚を全て検出することを「環境DNAメタバーコーディング」といいます。メタとは「まとめて」という意味で、バーコーディングとは、「スーパーのレジのようにバーコードを読み込み、情報を登録していく」ということです。この環境DNAメタバーコーディングの方法も、各国との競争の中で源先生はつくりあげていきました。
この方法を利用すると、古い地層を調査することで、過去にどんな生物が生息していたのか復元することができます。まさに「時空を超えて」、大きな環境の変化があった時期や、当時の環境を理解することができるのです。
源先生が最初に学会で発表を行ったとき、「できるはずがない」と捉えられていたことが、わずか10余年で目覚ましい発展を遂げているのです。
目に見えないミクロな世界ですが、何気なく街を流れている川や、小さな池、そして地球を覆う大気の中に、生き物たちの設計図が散らばっていると考えると、この世界の見え方ががらりと変わってしまうような気がします。本書を通して、そんなDNAが〝ただよう〟世界を体感してみてはいかがでしょうか。
じつは、地球上の生物はDNAを体から排出しながら生きています。尿や便などの排泄物、髪の毛や体毛、代謝によって剥がれ落ちた皮膚など、これらにはすべてDNAが含まれています。そして、それは人間だけでなく、あらゆる地球上の生命にもいえることです。この環境中に排出されたDNAのことを「環境DNA」と呼ぶのです。
今回ご紹介するのは、神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授である源利文先生の著書『環境DNA入門 ただよう遺伝子は何を語るか』(岩波科学ライブラリー)です。サブタイトルに見る〝ただよう〟とは、決して比喩ではありません。そんなDNAが〝ただよう〟世界を覗いていきましょう。
すぐに消失してしまうはずのDNAが……予備実験中の発見へ
一昔前まで、生物の体から排出されたDNAは、すぐに消失してしまうものだと考えられていました。ほかの生物のエサになってしまったり、紫外線によって分解されたりするからです。しかし、源先生は、コイヘルペスの研究中に水槽の中に高濃度のDNAがあることに気づきます。先生はもともと、人間活動による環境の改変と感染症の関係について調べていました。そうした中で、たまたま行った予備実験中にこの事象に気づいたのです。〈水槽の中には、カルキ抜きをした水道水と一匹のコイのみ。このDNAは一体「誰の」DNAだろうか〉
そう思った源先生は、DNAを詳しく分析していきます。すると、DNAはコイに由来するものでした。これまで排出されたDNAは消失するものと考えられていたけれども、もしかしたら、川や湖などの水を汲んで、その中に含まれるDNAを調べたら、そこに生息している生物がわかるかもしれない。ということで、この研究がはじまったのは2009年のことでした。そこから、先生は数多くの実験を行っていきます。
紆余曲折のすえ、一番乗りで論文を発表
本書の中では、こうした源先生の「環境DNA分析」の研究過程が記されています。はじめは1種類の生物を見つけることを考えましたが、他国の研究チームがすでに成功させていたため、多種を調べるという方針に転換していきます。試行錯誤を重ねる当時の状況やそのときの心境など、一つひとつのプロセスを読み進めていくと、地道な工程を繰り返す源先生の研究の様子が垣間見えるようでした。しかし、研究を進め発表にまでたどりついたものの、学会の反応は芳しいものではなかったそうです。そのときの様子を、源先生はこう語ります。
「演台から見れば話を聞いているかどうかはひと目でわかる。(中略)何を言っているんだコイツはという顔をしている。どうやら、水をくんで魚のDNAを検出するなんていうアホらしいことができるはずがないと思われてしまったようだ」
それほど、ある環境からDNAを検出するということはあり得ないことだと思われていたのかもしれません。しかし、この分野は各国の研究チームが注目していることもあり、じつは競争の激しい分野となっていたのです。源先生は2011年に一番乗りで論文を発表。そのわずか1カ月後にヨーロッパのチームが論文を提出しているため、接戦をくぐり抜けたわけです。
環境DNA分析の実用性を示す
環境DNA分析という分野を切り開く中で、さらにさまざまな研究が行われました。具体的な内容に踏み込んでいる章は本書の章見出しにもなっており、3章は「いるかいないか、どれだけいるか」、続く4章は「川ごと、国ごと、時空も超えて」。例えば、3章の「いるかいないか」という部分では、希少種であるゼニタナゴの検出が実例として語られています。99カ所から水のサンプルを用意し、そのうち2箇所が陽性。つまり「いる」という反応が出ました。実際その箇所を調べてみると、なんと11年ぶりにゼニタナゴの成魚が発見されたのです。
「環境DNA分析を端緒に繁殖地の特定まで至ったケースは、おそらく世界初である。このように本来の生息地・繁殖地を守ることは、希少種の保全にとっても重要なことであり、環境DNA分析が実用的にも役に立つ可能性を示すことができた」と、源先生は語っています。
4章に関していえば、川や湖などで水を汲み調べることで、そこに生息している魚を全て検出することを「環境DNAメタバーコーディング」といいます。メタとは「まとめて」という意味で、バーコーディングとは、「スーパーのレジのようにバーコードを読み込み、情報を登録していく」ということです。この環境DNAメタバーコーディングの方法も、各国との競争の中で源先生はつくりあげていきました。
この方法を利用すると、古い地層を調査することで、過去にどんな生物が生息していたのか復元することができます。まさに「時空を超えて」、大きな環境の変化があった時期や、当時の環境を理解することができるのです。
「できるはずがない」実験が10年余りで目覚ましい発展
生き物の体から排出されるDNA。アメリカでは空気中の環境DNAを調べることで、その付近にどんな植物が生えているのかがわかるという技術も開発されたそうです。また、直近でいえば、世界を騒がせ続けている新型コロナウィルスのRNAを下水中から採取し、感染者数との相関性が見られることもわかっています。源先生が最初に学会で発表を行ったとき、「できるはずがない」と捉えられていたことが、わずか10余年で目覚ましい発展を遂げているのです。
目に見えないミクロな世界ですが、何気なく街を流れている川や、小さな池、そして地球を覆う大気の中に、生き物たちの設計図が散らばっていると考えると、この世界の見え方ががらりと変わってしまうような気がします。本書を通して、そんなDNAが〝ただよう〟世界を体感してみてはいかがでしょうか。
<参考文献>
『環境DNA 入門 ただよう遺伝子は何を語るか』(源利文著、岩波科学ライブラリー315)
https://www.iwanami.co.jp/book/b615138.html
<参考サイト>
神戸大学大学院人間発達環境学研究科/国際人間科学部 源研究室
http://www2.kobe-u.ac.jp/~minamoto/index.html
『環境DNA 入門 ただよう遺伝子は何を語るか』(源利文著、岩波科学ライブラリー315)
https://www.iwanami.co.jp/book/b615138.html
<参考サイト>
神戸大学大学院人間発達環境学研究科/国際人間科学部 源研究室
http://www2.kobe-u.ac.jp/~minamoto/index.html
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







