テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
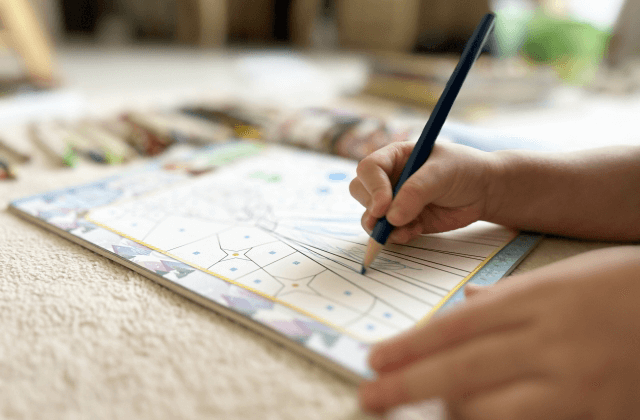
人の利き手はいつ決まるのか
利き手とは、「反射的に動かすときに用いる優位性の高い手」であり、一般的には、箸や筆記具を持つ手や、ボールを投げる手を指します。
以上のような利き手の特徴のうち、ポイントとなる点は「反射的」と「優位性」といえます。
まず反射的とは、「ある刺激に瞬間的に反応し、無意識に何かをするさま」を指します。つまり、利き手の決定は意識的に決定されるものではなく、反射的かつ無意識のうちに利き手の優位性が高まることによって、やがて利き手が決まっていくことがうかがえます。
アメリカの児童心理学者アーノルド・ゲゼル(1880-1961)の古典的な研究結果では、以下のように「利き手定着のプロセス」をまとめています。
「利き手定着のプロセス」
0~1歳 偏った使用傾向は見られない
2~3歳 左右どちらかを偏って使うかが混在している
4~6歳 もっぱら一方の手を使うようになる
7~14歳 安定して一方の手を使うようになる
一方、昭和女子大学教授で身体教育学が専門の山中健太郎氏は、個人差はあるが3~4歳頃に「両手を同時に使うようになればわかる」として、次のように述べています。
「たとえば2歳ぐらいまでの子どもの場合、左手をよく使うように見えても左利きとは限りません。片方の手しか使わない時期には、なかなか判別できないのです。その後、3歳~4歳くらいになって、両手を同時に使うようになればわかること。例えば食事の時に左手でフォークを扱い、右手でお皿を押さえるようになれば左利きです。つまりどちらがメインでどちらが補助か。逆にいうと両手で物事をしない時期に、右手を使おうが左手を使おうが、それはあまり意味を持たないと思っていただいて結構です」
そして、4~6歳頃になると、どちらかの手を優位に使うことが増して他方の手が受身的になるといわれています。この優位に使う手が、その人にとっての利き手となります。つまり、最近の研究からも、人の利き手が決まる時期はおおよそ4~6歳頃、定着は7~8歳以降が一般的とされているようです。
他方、利き手はもっと早い時期から発現しているという説もあります。なんと、胎児の頃によく指しゃぶりをしていた方の手が利き手になるという説です。
その説は、超音波検査機器で胎児の指吸い運動を15分間観察したところ、左手の使用が約8%と、成人の左利きの割合とあまり変わりないという結果が出ました。そのため、利き手と胎児がしゃぶる手指とは関係があるのではないかという仮説に由来しています。
なお、宗教や文化的な価値観によって左利きを右利きに矯正する傾向の強い国などもありますが、世界的に見ると、以前と比べると利き手を矯正する傾向は弱まっているようです。
また、利き手決定の要因やメカニズムは、遺伝や環境の観点から長年研究されていますが、2023年11月現在では解明されていません。
ただし、右利き仕様の社会設定は、当然ながら少数派の左利きにはデメリットといえます。
しかし、少数派の左利きが有利となる分野もあり、代表例として、競技スポーツが挙げられます。
なぜなら、左利きは少数派であるため、左利きを相手にする対戦者は不慣れなことが多く、経験則がものを言う競技ではそれだけで有利となります。ボクシングや格闘技などの対戦競技、野球やバレーボールなどの集団競技では、「サウスポー」や「レフティ」の活躍が目立ちます。
ところで、近年では利き手でない手を使うと脳が活性化するなど、「利き手でない方の手を使うこと自体のメリット」もあると考えられています。
まずは利き手でない方の手で、(1)歯磨きをするからはじめ、慣れてきたら、(2)PCのマウスを使う、(3)箸を使う、(4)文字を書くなど、利き手の優位性を担保しながらも、意識的に手をつかうことの有利性も高めてみてはいかがでしょうか。
以上のような利き手の特徴のうち、ポイントとなる点は「反射的」と「優位性」といえます。
まず反射的とは、「ある刺激に瞬間的に反応し、無意識に何かをするさま」を指します。つまり、利き手の決定は意識的に決定されるものではなく、反射的かつ無意識のうちに利き手の優位性が高まることによって、やがて利き手が決まっていくことがうかがえます。
利き手が決まる時期とは?
では優位性の高い手、つまり利き手はいつ頃決まるのでしょうか。アメリカの児童心理学者アーノルド・ゲゼル(1880-1961)の古典的な研究結果では、以下のように「利き手定着のプロセス」をまとめています。
「利き手定着のプロセス」
0~1歳 偏った使用傾向は見られない
2~3歳 左右どちらかを偏って使うかが混在している
4~6歳 もっぱら一方の手を使うようになる
7~14歳 安定して一方の手を使うようになる
一方、昭和女子大学教授で身体教育学が専門の山中健太郎氏は、個人差はあるが3~4歳頃に「両手を同時に使うようになればわかる」として、次のように述べています。
「たとえば2歳ぐらいまでの子どもの場合、左手をよく使うように見えても左利きとは限りません。片方の手しか使わない時期には、なかなか判別できないのです。その後、3歳~4歳くらいになって、両手を同時に使うようになればわかること。例えば食事の時に左手でフォークを扱い、右手でお皿を押さえるようになれば左利きです。つまりどちらがメインでどちらが補助か。逆にいうと両手で物事をしない時期に、右手を使おうが左手を使おうが、それはあまり意味を持たないと思っていただいて結構です」
そして、4~6歳頃になると、どちらかの手を優位に使うことが増して他方の手が受身的になるといわれています。この優位に使う手が、その人にとっての利き手となります。つまり、最近の研究からも、人の利き手が決まる時期はおおよそ4~6歳頃、定着は7~8歳以降が一般的とされているようです。
他方、利き手はもっと早い時期から発現しているという説もあります。なんと、胎児の頃によく指しゃぶりをしていた方の手が利き手になるという説です。
その説は、超音波検査機器で胎児の指吸い運動を15分間観察したところ、左手の使用が約8%と、成人の左利きの割合とあまり変わりないという結果が出ました。そのため、利き手と胎児がしゃぶる手指とは関係があるのではないかという仮説に由来しています。
利き手の割合と要因
利き手の左右比の割合は、人種・男女・年齢を問わず、世界の人口の約90%は右利き、約10%が左利きといわれています。ただし、両利きを含めた非右利きに広げると約30%になるともいわれています。なお、宗教や文化的な価値観によって左利きを右利きに矯正する傾向の強い国などもありますが、世界的に見ると、以前と比べると利き手を矯正する傾向は弱まっているようです。
また、利き手決定の要因やメカニズムは、遺伝や環境の観点から長年研究されていますが、2023年11月現在では解明されていません。
利き手のメリットとデメリット・有利と不利
利き手によるメリットとデメリットといえば、まず右利きは多数派のため、ハサミや包丁などの刃物、注ぎ口のある調理器具や片側に引き出しのついたデスクなど左右非対称の道具、さらには自動販売機といった什器類の多くが主に右利き仕様のため、日常生活に不便を感じることがないというメリットがあります。ただし、右利き仕様の社会設定は、当然ながら少数派の左利きにはデメリットといえます。
しかし、少数派の左利きが有利となる分野もあり、代表例として、競技スポーツが挙げられます。
なぜなら、左利きは少数派であるため、左利きを相手にする対戦者は不慣れなことが多く、経験則がものを言う競技ではそれだけで有利となります。ボクシングや格闘技などの対戦競技、野球やバレーボールなどの集団競技では、「サウスポー」や「レフティ」の活躍が目立ちます。
ところで、近年では利き手でない手を使うと脳が活性化するなど、「利き手でない方の手を使うこと自体のメリット」もあると考えられています。
まずは利き手でない方の手で、(1)歯磨きをするからはじめ、慣れてきたら、(2)PCのマウスを使う、(3)箸を使う、(4)文字を書くなど、利き手の優位性を担保しながらも、意識的に手をつかうことの有利性も高めてみてはいかがでしょうか。
<参考文献・参考サイト>
・『図解眠れなくなるほど面白い左利きの話』(八田武志監修、日本文芸社)
・気になる我が子の利き手「左利きは損をする説」を専門家に聞いた│MiKiHOUSE
https://baby.mikihouse.co.jp/information/post-10539.html
・【医師監修】赤ちゃんの「利き手」の話?遺伝は関係するの? 見分け方は?│マイナビ子育て
https://woman.mynavi.jp/kosodate/articles/11802
・利き手が決まるのはいつ頃?│浜松市子育て情報サイト ぴっぴ
https://www.hamamatsu-pippi.net/sodan/hamasukuqa/hamasukuqa-list/8215.html
・『図解眠れなくなるほど面白い左利きの話』(八田武志監修、日本文芸社)
・気になる我が子の利き手「左利きは損をする説」を専門家に聞いた│MiKiHOUSE
https://baby.mikihouse.co.jp/information/post-10539.html
・【医師監修】赤ちゃんの「利き手」の話?遺伝は関係するの? 見分け方は?│マイナビ子育て
https://woman.mynavi.jp/kosodate/articles/11802
・利き手が決まるのはいつ頃?│浜松市子育て情報サイト ぴっぴ
https://www.hamamatsu-pippi.net/sodan/hamasukuqa/hamasukuqa-list/8215.html
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子










