テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
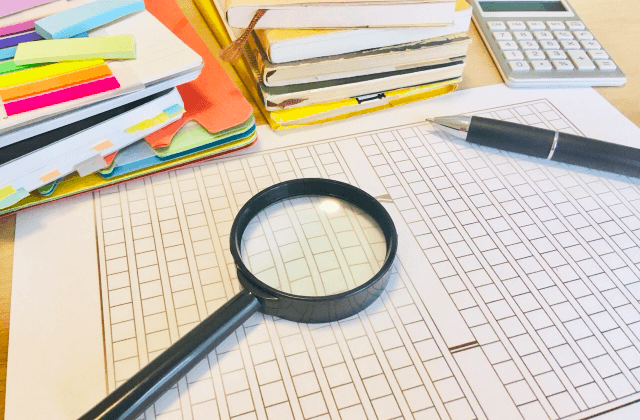
『くらべて、けみして 校閲部の九重さん』が明かす本作り秘話
一冊の本ができあがるまでの工程を知っている方は、どれほどいるでしょうか。本作りに関わる主要な人物として「作家(著者)」のほかに「編集者」がいることはよく知られていますが、他にも数多くの“縁の下の力持ち”が存在します。
本書『くらべて、けみして 校閲部の九重さん』(こいしゆうか著・協力/新潮社校閲部、新潮社)は、その1つである「校閲部」に焦点を当てて描かれたコミックエッセイです。著者のこいしゆうかさんは、著書に『そうだ、キャンプにいこう!』『カメラはじめます!』などがある通り、一般的に難しいことやとっつきにくそうなものを漫画でわかりやすく描くエッセイ漫画家。彼女が新潮社の全面協力のもと、知られざる校閲者の実態を描き出します。
ご承知のとおり、まず本作りは作家が原稿を書くことからスタートします。作家は、ときに編集者と話し合いながら原稿を完成させるわけですが、原稿が完成したからといって、いきなり印刷されて本になるわけではありません。完成した原稿が編集者の手に渡ったあと、いよいよ校閲者の仕事が始まります。
では校閲者はどのような作業がおこなうのか。「校閲」を辞書で引くと、「文書や原稿などの誤りや不備を調べて、なおしたり補ったりすること」とあります。その通りではあるのですが、実際におこなうのはさほど容易なことではありません。その様子が本書では非常にわかりやすく描かれています。
ここで本書のストーリーを少しご紹介しておきましょう。
主人公は、新頂社(しんちょうしゃ)校閲部文芸部の九重心(くじゅうこころ)さん。ある日、校閲部に新入社員である瑞垣(みずがき)さんが配属され、九重さんは彼女の教育係となります。校閲作業が初めての瑞垣さんは、作家の書いた原稿を読んでいる途中で作品に感情移入して泣いてしまいます。その姿を見た九重さんは、彼女にこう言います。「作品を読むのではなく、言葉そのものに向き合うのだ」と――。
九重さんは瑞垣さんに、校閲のイロハを教えていきます。校閲は、ただ誤字脱字を見つけるだけの校正作業ではありません。作品を通して事実関係や人物描写に矛盾がないかを徹底的に確認すること、作家の表現を確認するためにありとあらゆる辞書を調べあげること等々、いかに事細かな作業がおこなわれているのかを垣間見ることができるでしょう。
現在はパソコンで文章を書く人が大多数でしょうが、昔は皆、原稿用紙に手書きで書いていました。それを出版社側がデータ(ゲラ)にするのですが、その際の苦労話として採り上げられているのが、作家の「悪筆(読み取るのが困難なほどクセの強い字)」です。その代表例として石原慎太郎さんの原稿が拝見できるのも、また一興(いや、むしろ一驚!)です。
また、本書では校閲部OBの“レジェンド”が登場します。著者のこいしゆうかさんもコラムで取材した経緯を明かしているので、現実の人物なのでしょう。彼が発する言葉や、昭和を代表する文芸評論家・江藤淳さんとのエピソード秘話を読むと、校閲者とは作家と対等に渡り合える度胸と知識がなければいけないのだと実感させられます。まさに長年作家とともに本を作り上げてきた、いわば百戦錬磨の猛者なのです。
新人校閲者・瑞垣さんが、発売されている自社本の誤植を発見して九重さんに報告するシーンがあります。瑞垣さんは「誤植が見つかってよかったですね」と嬉々として報告したのですが、九重さんは自分が担当した本に誤植があったことでショックを受けてしまいます。自身のプライドが傷ついた瞬間だったのです。
このように校閲者は、つねに担当作品に覚悟と責任をもち、作品を世に送り出しています。素晴らしい本に出合ったとき、その本をこの世に生み出してくれた作家を讃えるとともに、その作品作りに貢献した校閲者のことも、しっかりと心にとどめておきたい。本書はそう実感させてくれる、貴重な一冊です。
本書『くらべて、けみして 校閲部の九重さん』(こいしゆうか著・協力/新潮社校閲部、新潮社)は、その1つである「校閲部」に焦点を当てて描かれたコミックエッセイです。著者のこいしゆうかさんは、著書に『そうだ、キャンプにいこう!』『カメラはじめます!』などがある通り、一般的に難しいことやとっつきにくそうなものを漫画でわかりやすく描くエッセイ漫画家。彼女が新潮社の全面協力のもと、知られざる校閲者の実態を描き出します。
本作りにおける影の立役者
校閲者は表舞台には決して出てこない存在ですが、間違いなく本作りにおける“影の立役者”です。ご承知のとおり、まず本作りは作家が原稿を書くことからスタートします。作家は、ときに編集者と話し合いながら原稿を完成させるわけですが、原稿が完成したからといって、いきなり印刷されて本になるわけではありません。完成した原稿が編集者の手に渡ったあと、いよいよ校閲者の仕事が始まります。
では校閲者はどのような作業がおこなうのか。「校閲」を辞書で引くと、「文書や原稿などの誤りや不備を調べて、なおしたり補ったりすること」とあります。その通りではあるのですが、実際におこなうのはさほど容易なことではありません。その様子が本書では非常にわかりやすく描かれています。
ここで本書のストーリーを少しご紹介しておきましょう。
主人公は、新頂社(しんちょうしゃ)校閲部文芸部の九重心(くじゅうこころ)さん。ある日、校閲部に新入社員である瑞垣(みずがき)さんが配属され、九重さんは彼女の教育係となります。校閲作業が初めての瑞垣さんは、作家の書いた原稿を読んでいる途中で作品に感情移入して泣いてしまいます。その姿を見た九重さんは、彼女にこう言います。「作品を読むのではなく、言葉そのものに向き合うのだ」と――。
九重さんは瑞垣さんに、校閲のイロハを教えていきます。校閲は、ただ誤字脱字を見つけるだけの校正作業ではありません。作品を通して事実関係や人物描写に矛盾がないかを徹底的に確認すること、作家の表現を確認するためにありとあらゆる辞書を調べあげること等々、いかに事細かな作業がおこなわれているのかを垣間見ることができるでしょう。
現実のエピソードが満載
本書の面白い点の一つは、フィクションでありながらも限りなくリアルに近い現場が描かれていることです。多彩な表現を用いられる作家として町田康さんの例が挙げられるなど、現在活躍する作家のエピソードも数多く盛り込まれています。また、各章の終わりにはコラムがあり、実際の新潮社校閲部社員の声が掲載されています。現在はパソコンで文章を書く人が大多数でしょうが、昔は皆、原稿用紙に手書きで書いていました。それを出版社側がデータ(ゲラ)にするのですが、その際の苦労話として採り上げられているのが、作家の「悪筆(読み取るのが困難なほどクセの強い字)」です。その代表例として石原慎太郎さんの原稿が拝見できるのも、また一興(いや、むしろ一驚!)です。
また、本書では校閲部OBの“レジェンド”が登場します。著者のこいしゆうかさんもコラムで取材した経緯を明かしているので、現実の人物なのでしょう。彼が発する言葉や、昭和を代表する文芸評論家・江藤淳さんとのエピソード秘話を読むと、校閲者とは作家と対等に渡り合える度胸と知識がなければいけないのだと実感させられます。まさに長年作家とともに本を作り上げてきた、いわば百戦錬磨の猛者なのです。
責任と覚悟をもって、原稿を送り出す
最後に、本書のなかで描かれている印象的なエピソードをもう一つ、紹介します。新人校閲者・瑞垣さんが、発売されている自社本の誤植を発見して九重さんに報告するシーンがあります。瑞垣さんは「誤植が見つかってよかったですね」と嬉々として報告したのですが、九重さんは自分が担当した本に誤植があったことでショックを受けてしまいます。自身のプライドが傷ついた瞬間だったのです。
このように校閲者は、つねに担当作品に覚悟と責任をもち、作品を世に送り出しています。素晴らしい本に出合ったとき、その本をこの世に生み出してくれた作家を讃えるとともに、その作品作りに貢献した校閲者のことも、しっかりと心にとどめておきたい。本書はそう実感させてくれる、貴重な一冊です。
<参考文献>
『くらべて、けみして 校閲部の九重さん』(こいしゆうか著・協力/新潮社校閲部、新潮社)
https://www.shinchosha.co.jp/book/355391/
<参考サイト>
こいしゆうかさんのツイッター(現X)
https://twitter.com/koipanda
こいしゆうかさんのオフィシャルサイト(こいしゆうか YUKA KOISHI|KOISHIYUKA.COM)
http://koishiyuka.com/
『くらべて、けみして 校閲部の九重さん』(こいしゆうか著・協力/新潮社校閲部、新潮社)
https://www.shinchosha.co.jp/book/355391/
<参考サイト>
こいしゆうかさんのツイッター(現X)
https://twitter.com/koipanda
こいしゆうかさんのオフィシャルサイト(こいしゆうか YUKA KOISHI|KOISHIYUKA.COM)
http://koishiyuka.com/
人気の講義ランキングTOP20










