テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
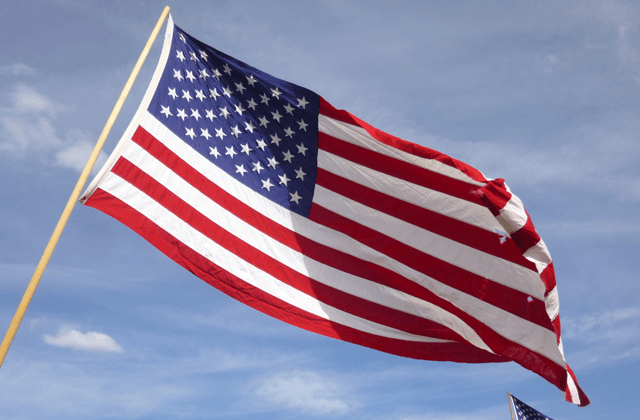
アメリカ独自の孤立主義とトランプの孤立主義
アメリカ独自の孤立主義・モンロー主義
「モンロー主義」という言葉を聞いたことはありますか? 世界を、とりわけ世の男性を虜にしたあのマリリン・モンローとは関係なく、アメリカの第5代大統領ジェームズ・モンローが1823年にヨーロッパ諸国に対して提唱した外交方針のことを指します。そこでは、アメリカとヨーロッパ相互の不干渉が宣言されています。こちらから口出しはしないけれど、相手からの口出し、手出しもさせないことによって国際間の秩序形成をするという、独自の孤立主義を打ち出しました。このモンロー主義という「不干渉」の外交方針を基本に、アメリカはかつて対ヨーロッパにおける国際秩序と貿易による南北アメリカ大陸の権益を確保しようとしたのです。
トランプ流孤立主義を2つの観点で考える
ということで、アメリカはもともとモンロー主義、あるいは孤立主義といわれるのですが、ここで気になるのが、新大統領となったドナルド・トランプ氏の極端な孤立主義がアメリカを再びモンロー主義に引き戻すのではないかということです。しかし、政治学者で慶應義塾大学大学院教授の曽根泰教氏は、国際的な秩序形成という観点から考えると、かつてのモンロー主義とトランプ氏の孤立主義は意味合いが違う、という見方をしています。トランプ氏の孤立主義の特異性は2つの角度から考えるとよく分かります。まず一つは比較優位の原則。もう一つは国際公共財の概念です。
比較優位の原則を理解すればTPPの利点も見えてくる
この二つの概念について、TPPと安保条約を例に考えてみましょう。比較優位とは、経済を専門としていない人にはなかなか分かりにくいのですが、曽根氏によると、「自由貿易をすれば、例えばアメリカあるいは生産力のある国、いずれの国も得をする」ということです。農産物、工業製品、繊維製品など、それぞれの国が高い生産力を持つものを自由貿易で取引することによって、相互が潤っていくという考え方ですね。
この考え方には経済学的に産業構造の転換などの課題を説明し切れていないという問題もあるのですが、実際には多くの経済学者がこの比較優位の原則を前提に自由貿易を議論しています。トランプ氏の「TPPに加盟して国際貿易をすると、国内でダメージをこうむる人が出てくる。だから、TPPは止めてしまおう」などという発言は、比較優位の原則を理解していないことを表しているのではないでしょうか。
そもそもmulti(複数)の発想で関係国と協定を結んでいくTPPは、全てを当該相手国とのディール(交渉)、つまりmultiではなくbi(双方)の発想で捉えてきたトランプ氏の基本姿勢とは、接点があまりにも少ないのです。
トランプ氏にとって「安保条約」はクラブ財?
もう一点、秩序形成を背景に成り立っているモンロー主義とトランプ氏の孤立主義との違いについて、国際公共財の概念から考えてみます。「公共財」とはその名の通り、あるモノやサービスを購入あるいは利用する人だけでなく、誰もがそれらの便益を享受できるというものです。例えば、誰もが出入りして散歩をしたり、休息したりすることのできる公園を思い浮かべると、この「公共財」の概念は分かりやすいでしょう。
「安全保障条約」というシステムも国際的な公共財と考えられます。日米安保条約は、日米間でかわされた条約ではありますが、これは単に二国間の同盟という枠を越えて、東アジア全域の安全保障、安全秩序に関わっているものだからです。
しかし、トランプ氏は安保条約をあたかも「クラブ財」、つまり、会費を払った会員のみがそのサービスを享受できるもの、と捉えている節があり、また、払った費用の分だけ、直接的な秩序が得られるとも考えているようです。だからこそ、トランプ氏は同盟国に米軍駐留経費の全額負担を求めているのでしょうが、これらのことからしても、彼は国際公共財という概念を理解していないのではないか、と曽根氏は見ています。
もっとも、公共財には「フリーライダー」、つまり、直接費用負担をせずにサービスを享受するただ乗り現象の発生がつきものです。よって、トランプ氏は今後、まずこの「フリーライダー徹底追及」を始めるかもしれません。
対ヨーロッパのモンロー主義とトランプ流孤立主義
こうしてみると、モンロー主義とトランプ流孤立主義の違いは歴然。モンロー主義は、ある意味、アメリカ独自の孤立主義ではありますが、それはグローバルな意味での秩序、均衡を保つために、対ヨーロッパレベルで多国間との関係を考慮したものでありました。いわば、multi(複数)の発想です。一方、トランプ氏は実業家出身ですから、multiではなく、bi-(双方)で直接やりあう「ディール(交渉)」を国際政治、外交の場でも辞さないと考えられます。モンロー主義とは一線を画すトランプ流孤立主義で、TPPも安全保障条約も押し切ろうとしているのでしょうか。人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










