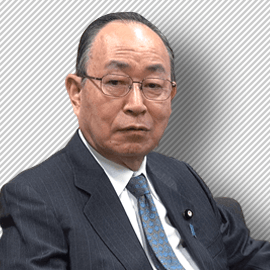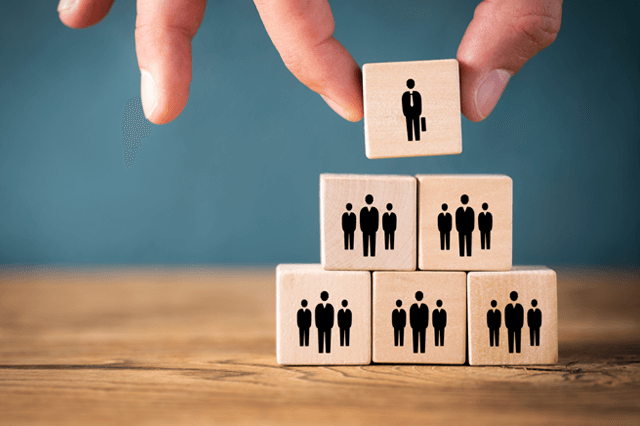●松下電器が成功した9つの理由は4つに集約できる
松下幸之助さんがどういう経営をしてきたかということについて、最後に申し上げたいことがあります。それは、松下電器が成功した理由を9つ挙げましたが、これを集約したダイジェスト版としての4項目です。1つ目は、社員に誇りを与えたということです。そして2つ目は、社員に励ましを与えたということで、3つ目は社員に感謝をしたということ。4つ目は、社員に感動を与えたということです。
松下幸之助さんが理想を掲げたことは、社員に誇りを与え、そして励ましを与えました。何よりも人材に恵まれたという考え方は、言ってみれば社員に感謝をしているわけです。そして全員経営は、結局は社員に感動を与えたことになります。
●社員を褒めるだけでなく、必要なときには叱ることも必要
この感動というものは、口先だけの感動では駄目です。近頃では、社員を褒めろということが大合唱されています。しかし、褒めてばかりいて社員を堕落させてしまっている責任は大きいと、私は思っています。褒めるべきときには褒めないといけないですが、叱るべきときには叱らなければならない。病気でもそうです。薬で病気を治す努力はしなければなりません。しかし、薬で治せないときには外科手術も必要になるわけです。
ですから、褒めることが薬を与えることだとすると、叱ることは外科手術に当たります。いよいよだというときには、外科手術をする度胸がないといけない。ところが、もう外科手術をしないといけないときに、「褒めろ、褒めろ」「薬だ、薬だ」となってしまうと、結局はその人材を殺してしまうことになります。
●松下幸之助は社員を叱るときにでも感動を与えられた
ところが松下幸之助という人は、社員を叱ったとしても、その社員に感動を与えることができたのです。それはなぜかと言えば、最初に戻りますが、人間とは何かという考え方が松下幸之助さんにはあるからです。偉大な存在である人間というのは、一人一人がダイヤモンドを持っている。ダイヤモンドを持っている一人一人の社員に対して、心から礼を尽くして叱らなければいけない、接しなければいけない。そう松下幸之助さんは考えているわけです。
これは、シリーズ内でもお話ししましたが、私が「何人で会社をやっているのか」と聞かれた時のことです。私が「250人です」と答えたら、「100...