●経済現象を理解するには歴史的な観点が欠かせない
未来社会を考える手掛かりとして、今日は小野塚知二先生が最近お出しになった『経済史』(有斐閣)という本を見ながら考えてみたいと思います。皆さんは経済史というものにご興味はおありでしょうか。私はこの本の書評を、東京大学の『UP』という雑誌に書きました。この『UP』の良いところは、普通の書評が数10文字からせいぜい数100文字で内容をまとめなければならないのに対し、5,000字程度文字数に余裕があるため、相当思い切ったことを書ける点です。
私はその冒頭に、「経済史への熱」というパラグラフを置きました。私は学生の時、経済史に大変興味を持っていました。不思議な学問領域だとずっと思っていました。ちょうど私が学生だった頃は、経済学観がマル経から近経、つまりマルクス経済学から近代経済学に移行していく時期でした。私は経済史とはどちらかというマルクス経済学に属しているというイメージで捉えていたのですが、この小野塚先生の『経済史』を拝読すると、もはやそのような二項対立は無意味であることが分かります。
今の経済現象を分析するためには歴史的なパースペクティブを置くことが極めて大事です。さきほど社会的想像力という言葉を使いましたが、実はこの経済史はわれわれの社会的想像力の一翼を担っているのです。ですからそれを変更することによって、資本主義への見方も変わってくるのではないかと、私は思っています。
●経済史をみることで、資本主義との付き合い方を考える
小野塚先生は『経済史』の中で次のような重要なことをお書きになっています。「個人の際限のない欲望を即時に管理し、また、欲望を適切に維持・創出し、個人の行為・感情までを<望ましい>方向に即時に誘導・介入する社会構造を実現できるなら、人類の文明を文字通り調和のとれた形で末永く維持し、かつ成長と資本主義を可能ならしめることができるのかもしれません。労務管理と生活管理の究極の姿をそれは示しています。そこには、基底的価値としての人格・自由・自律はありませんが、疑似的な自覚・自由・自律が確保できるなら、それは、介入的自由主義の現代を、新たな人間操作技術と統治技術・思想によって再建することになるでしょう」。
これはなかな...











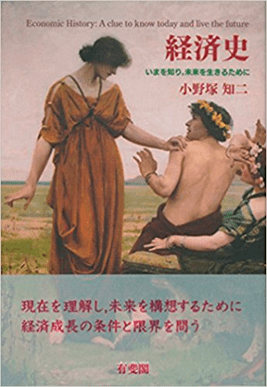

(小野塚知二著、有斐閣)