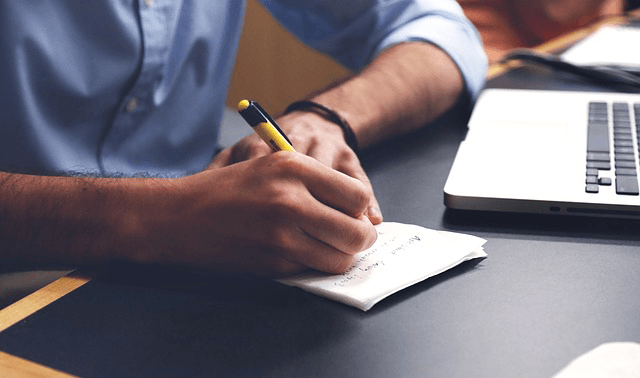●外部人材を入れる手法は副作用もある
神藏 新浪さんのようなプロ経営者の人は、日本では藤森義明さんや魚谷雅彦さんなど、極めて少ないですよね。
新浪 でも、あの方々は外資におられたので、テンプレートをお持ちでした。クリアカットに、1つの物事の考え方を分かりやすく持っていたのです。しかし、私は外資にいたことがないから、そういうことが分からないのです。
神藏 藤森さんはGEにいました。
新浪 彼はGEのやり方をLIXILに持ってきて、人もGEからどんどん入れました。資生堂の魚谷さんもコカ・コーラのやり方を取り入れていきましたよね。でも、サントリーには、そういうことが適用できないのです。サントリーでは、もう状況に合わせて対応するしかありませんでした。私は、そういう外資で仕事をした経験がないので分からないのです。ですから、私の場合は、「日本流の最たるサントリーという経営の中で、グローバルといかにアウフヘーベンするか」ということが、常に課題なのです。
神藏 そうですね。GEのチーム藤森が、そのままごそっとLIXILに移っていきましたよね。
新浪 魚谷さんの資生堂も、今度のCFOはフランス人ですよね。この辺りも、外からの人材が中心にいます。あれは欧米流としては正しいのです。新しい社長が来たら、新しいキャビネットになります。でも、サントリーにそれは向かないのです。新しい人が来ても、サントリーの中における功がなければ、誰も尊敬しませんし、付いてこないのです。私にとっては、佐治信忠会長と二人三脚で一緒にやっているということがすごく重要です。もう5年も役にいますから、この人は何者かということも分かってくれていると思いますし、そんなに悪い人ではないとは思ってくれているとは思うのですが。ただ、やはりグローバライゼーションをもっと加速するのであれば、外からもっと連れてこなければいけません。でも、それをやるとアレルギーになるのです。他社さんは、そういうものを是としたと思うのです。それは急いでやるなら、正しいと思います。でも急いでやると劇薬ですから、副作用も出るのです。
武田薬品工業も、中国というすごくいい市場を持っていますが、これからはおそらくプロパーをどう生かしていくかということにも、力を入れられると思います。私たちも、つらい目にも遭わせながら、プロパーをいかに困難の中で成長させるかという...