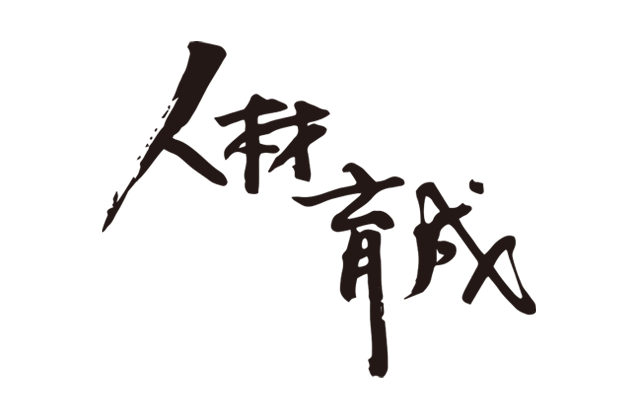●『海防八策』を書いた佐久間象山の危機感
―― 佐久間象山はものすごい弟子を育てたし、感化力もあったのですね。
田口 そうなんです。彼は本質を非常によく心得ていたので、短期間で一番重要なこと、つまり核となるべきものを教えることができたのでしょう。
そして、彼はなんでも自分でやりました。そこから、「これはこうやって教えた方が良い」といった教え方を学びました。自分が習得することで、習得の方法が分かったのです。自分でやっているからです。
―― そこは苦労して見つけたからでしょう。
田口 だから非常に生きた教育をやっていたのです。そういうところがすごいのです。その根本には、このままでは日本が西洋列強に利用されてしまい、悲惨な状況になってしまうという危機感があったということです。そのため、1840~1842年のアヘン戦争の時に、彼は『海防八策』という意見書を建白しました。ペリーが来る10年ほど前のことです。彼はそのことを予測して、「このように(黒船が)来る。だから、こうしたことをしなければダメなんだ」と言って建策をしたのです。
さらに彼は、その後も相変わらず続く危機感について、川路聖謨などに「ここはこうやらなきゃいけない」などと言って、『急務十条』などをどんどん建策していきました。これらは、明治近代国家が範として求めたものでした。
1904年に日露戦争があり、1905年にはポーツマス条約が結ばれましたが、日露戦争はなぜ勝ったのかといえば、海軍です。海軍がどうあるべきなのかということについては、日露戦争よりもかなり前、佐久間が「こうあるべきだ」というものを建策していたのです。
●「先憂後楽」の資質を持っている人間がもっと出てこないと駄目だ
田口 私が考えている佐久間から学ばなければいけない一番のキーワードは、「先憂後楽」です。
「先憂」とは、「民に先んじて憂う」ということです。政治に携わる人間や、国家を運営する人間にとっての一番大切な資質は、「先憂」にある、と。要するに、誰もがまだ心配しないことを心配し、ちゃんと手を打っておくことが重要だというのです。さらに「後楽」ですが、後楽園の「後楽」です。これは、民が「良かった、良かった、もう安心だ」といっても安心せず、その後もしばらく注意深く見て、「もう、これで大丈夫だな」と思ってから、1人楽しむべきだという考え方です。...