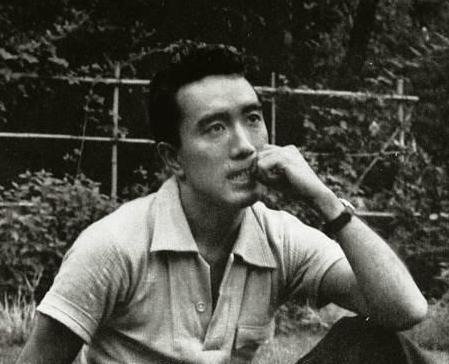●歴史学は凡人の領域だという誤解を嘆いたイブン・ハルドゥーン
私はその専門家ですから特に思うのですが、歴史という学問は、実は素晴らしい学問です。ところが、歴史学や歴史が、あたかも凡人の領域、あるいは、誰でもできると思われるのは、いささか口惜しいところがあります。
ただ、誤解しないでほしいのですが、これが口惜しいと言ったのは、私が最初ではなく、チュニジア生まれの歴史家、イブン・ハルドゥーンでした。
繰り返しになりますが、今の日本においては、特に、歴史という学問には、“誰でも参入できる”と思わせるところがあることは事実です。
●『エセー』におけるモンテーニュの辛辣な歴史揶揄
16世紀に活躍したフランスのエッセイスト、思想家であるモンテーニュという人物がいます。モンテーニュは『エセー』(随想録)の著者ですが、彼はその『エセー』の中で、歴史について、私たちにとって、ある意味では実に小面憎い、しかし、“なかなかいいところを突いているな”と思わせる名言をいくつか語っています。私は、大好きなのでモンテーニュをよく読みますが、いつも、“お主、なかなか言うな”というところと、“何を言っていやがる”というところが交錯するところがあります。
モンテーニュは、「語り口が上手であれば歴史家という仕事は誰でもつとまる面がある」と言っています。なかなか辛辣です。「つとまる」とは言わず、「つとまる面もある」と言っているのですね。
モンテーニュによれば、彼ら歴史家は、「たいていは、ふつうの人々のなかから選ばれてくる」人たちであり、「まるで歴史書で文法を習うみたいなもの」だと揶揄しているのです。
これは、誰でもでき、文法に沿って歴史を解釈していくような、それ自体平凡な学問であり、歴史家は平凡な人たちだと、モンテーニュは言いたいのでしょう。
それにしても、モンテーニュから、歴史家とは「美辞麗句をふんだんに使って、街角で集めてきたうわさを、みごとな織物に仕立てるといった具合」なのだと言われますと、モンテーニュが好きな私でさえ、少しモンテーニュをからかってみたい、あるいは、少し文句を言ってみたくなります。
●過去の正確な認識は不可能だと主張した現代主義の歴史家たち
しかし、これは後でまた触れますが、こういう見方はモンテーニュに限ったことではなく、「万人はそれぞれが...