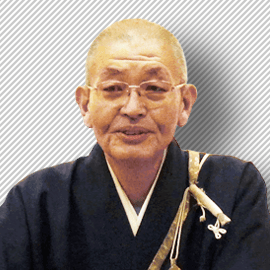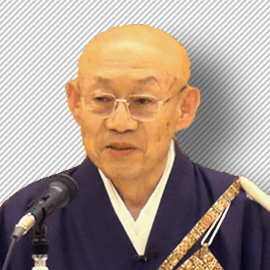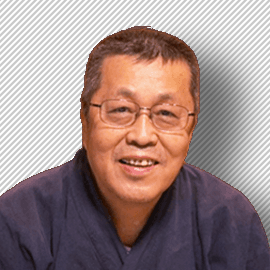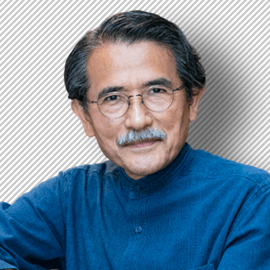千手千眼観音のサポートとは?菩薩たちのビッグバンとは?
おもしろき『法華経』の世界(3)止観と菩薩による救済
最澄の瞑想図は非常に美しいが、彼は何を瞑想していたのだろうか。答えは無、心の動きを止めるのが「止観」だからだ。また、『法華経』全巻の構成を見ると、弥勒、観音、普賢の三菩薩が衆生を導き救済する中心的存在であること...
収録日:2025/01/27
追加日:2025/05/18
SF的予言…おまえは将来、ブッダになり世界を救済していく
おもしろき『法華経』の世界(4)スペース・ファンタジーと『法華経』
「法華経はSFだ」が鎌田氏の持論だが、今回はSF映画の名作2本『2001年宇宙の旅』と『スター・ウォーズ』と『法華経』とを比較して考えていく。特に、鎌田氏が若き日に観た『2001年宇宙の旅』終盤に登場するスターチャイルドは、...
収録日:2025/01/27
追加日:2025/05/25
仏の寿命は無量で久遠に実在する…「如来寿量品」の神秘
おもしろき『法華経』の世界(9)「如来寿量品」と三身論
『法華経』の特質は、その予言力、呪力、神通力にある。それゆえ「密教の走り」とも考えられると鎌田氏は説く。とりわけ「久遠実成の本仏」を説く「如来寿量品」は、『法華経』のなかでも重視されてきた。釈迦が生まれて仏教を...
収録日:2025/01/27
追加日:2025/07/27
おみくじは「吉凶」だけでなく「和歌や漢詩」を読むのが本当
おみくじと和歌の歴史(1)おみくじは詩歌を読む
日本人にとって身近な「おみくじ」。しかし、その歴史を知る機会はあまり多くない。つい吉凶にばかり目が行きがちなおみくじだが、本当に受け取るべきメッセージはそこではないという。どういうことなのか。まず、おみくじの成...
収録日:2023/11/10
追加日:2023/12/20
沈没船の探索は戦争と技術の関係を後世に伝える重要な仕事
戦時徴用船の悲劇と大洋丸捜索(1)戦時徴用船と戦争
東京大学名誉教授の浦環氏が新たなプロジェクトとして着手した「大洋丸」の探索に関する講義シリーズ。沈没船の発見は多くの人に戦争と技術の関係に関して強い印象を与える。今回の講義では、「大洋丸」プロジェクトの内容に入...
収録日:2020/02/28
追加日:2021/03/27
『法華経』と「神道」はアバター!?通底する世界観とは
おもしろき『法華経』の世界(2)『法華経』と「神道」の共通性
聖徳太子、最澄、空海、日蓮、宮沢賢治など多くの人に多大な影響を与えてきた『法華経』は長い年月にわたり日本宗教史を貫いてきた存在である。『法華経』は、苦悩を前提としつつ、むしろそうであるがゆえに明るい未来や救済の...
収録日:2025/01/27
追加日:2025/05/11
遍歴とアバター…多様な仏、多様な菩薩が変容する面白さ
おもしろき『法華経』の世界(5)遍歴するアバター
『銀河鉄道の夜』の著者・宮沢賢治にとってもそうだが、『法華経』の重要なテーマは「遍歴」であると考えられる。遍歴や修行の旅は、仏教的には方便を用いて悟りに向かうことだが、『大日経』住心品には悟りと大悲こそが究境と...
収録日:2025/01/27
追加日:2025/06/29
陀羅尼品…あらゆるものが暗号であり、メタファーである
おもしろき『法華経』の世界(6)「陀羅尼品」とエニグマ
『法華経』下巻の「陀羅尼品」を読めば、それが真言宗の真言(=マントラ)と同様の構造を持っていることが分かる。天台教学における「諸法実相」や「本覚思想」という形而上学も、華厳経の「重々帝網」という次元世界も、全て...
収録日:2025/01/27
追加日:2025/07/06
仏国土は水平的世界だが「浄土に登る」―日本的仏教観
法隆寺は聖徳太子と共にあり(4)仏国土はどこにあるか
私たち日本人は、外からの諸物をそのまま受け入れるのではなく、自分たちの基準に従って取捨選択し、自分たちに都合よく組み上げてしまうことを得意とする。そしてそれは、典型的な経典解釈すら、日本風にアレンジしてしまうこ...
収録日:2016/03/09
追加日:2016/10/22
焼失した法隆寺を再建したのは誰か? 歴史の謎に迫る!
法隆寺は聖徳太子と共にあり(5)法隆寺最大のミステリー
法隆寺には未だに多くの謎が残されている。その中で最大のミステリーは、「誰が消失した法隆寺を再建したのか」というものだ。法隆寺管長・大野玄妙氏によれば、聖徳太子の行ったある行為が、法隆寺再建のカギとなった。そして...
収録日:2016/03/09
追加日:2016/10/29
法隆寺のお釈迦様は聖徳太子がモデル!生存中に造形が開始
法隆寺は聖徳太子と共にあり(6)「和」を広げる法隆寺
法隆寺にある仏像は、実は聖徳太子をモデルにしている。しかもそれは、彼がまだ生きている間につくられ始めた。法隆寺管長・大野玄妙氏は、こうした仏像作成法が中国に由来するものであると述べる。仏教には、教えが表面的に伝...
収録日:2016/03/09
追加日:2016/11/05
東大寺大仏建立の理由ー聖武天皇のいう「菩薩の精神」とは
東大寺建立に込められた思い(3)あまねく発展を願う
大仏造立の際に聖武天皇が出した詔では、何が語られているのか。東大寺長老・北河原公敬氏が解説する。聖武天皇は、自らを菩薩になぞらえ、この世の全てを慈しもうとした。菩薩とは、自分以外のものにも手を差し伸べ、一緒に救...
収録日:2016/03/08
追加日:2016/12/10
技術は一度途絶えてしまうと再現はできなくなる
刀匠・松田次泰に聞く―日本刀のつくり方(1)和鉄の活用
「下鍛え」の準備工程を延々と続ける刀匠・松田次泰氏。その動きを見ていると、材料の中から火床に乗せるもの・乗せないものの選別が行われている。いったい何を見て、刀匠は鉄をより分けているのだろうか。そんな素朴な疑問に...
収録日:2017/03/22
追加日:2018/01/03
長州ファイブ、イギリスへ…長州藩士と薩摩藩士の密航留学
明治維新とは~幕末を見る新たな史観(12)薩長の攘夷戦争
幕府が命じた専守防衛原則にもかかわらず、長州は攘夷攻撃を展開し、薩摩は生麦事件に端を発する薩英戦争に突入した。しかし、島田晴雄氏が注目するのは、一方で両雄藩が密航留学を行い、西欧文明をしっかりと受け止めていたと...
収録日:2018/07/18
追加日:2018/12/07
油絵を完成させたヤン・ファン・エイクの驚くべき技法
ルネサンス美術の見方(3)ヤン・ファン・エイクの油彩技法
北方を拠点としたヤン・ファン・エイクは、油彩技法を完成させたルネサンス期の人物として名高い。外交官としての顔をも持ちつつ、作品の細部にさまざまな卓越した技巧をこらし、美術史上で最重要とも評される作品『ヘントの祭...
収録日:2019/09/06
追加日:2019/11/07
ローマの剣闘士と江戸の花見は庶民の生活を楽しませるため
ローマ史と江戸史で読み解く国家の盛衰(3)剣闘士と花見
庶民のための街づくりは、「人はパンのみにて生きるにあらず」を体現し、江戸では花見、ローマでは剣闘士などが公に準備される。為政者にとってはガス抜きの意味を持つイベントや行楽の重視は、世界史上「パンとサーカス」の名...
収録日:2019/08/06
追加日:2020/01/02
「千古不易の恋」を描いた光源氏と女性たちの『源氏物語』
『源氏物語』を味わう(2)光源氏をめぐる女性たちの物語
『源氏物語』の本質は、光源氏をめぐる女性たちの物語である。登場して間もなく物の怪に殺される夕顔、ボロボロの屋敷に住んでいる末摘花、最後まで一番好きだった紫上、あわよくばものにしようとしたライバルの娘・玉鬘など、...
収録日:2022/02/22
追加日:2022/06/27
「和歌みくじ」で運をつかむ…現代に息づくおみくじの知恵
おみくじと和歌の歴史(5)現代の和歌みくじ
明治時代に入り、おみくじは大きな転換期を迎える。神仏分離令を契機に、江戸の歌占とは違う新しい和歌みくじが作られるようになるのである。その流れで現代に至るわけだが、注目したいのが明治神宮の和歌みくじだ。神道学研究...
収録日:2023/11/10
追加日:2024/01/17
平安時代から続く伝統…『源氏物語』の最大の特色は口承性
日本語と英語で味わう『源氏物語』(2)『源氏物語』が描いたリアリティ
時代を越えて読み継がれる『源氏物語』の魅力は、人間のリアリティがとことん描かれていることにある。愛読者だったという藤原道長はもちろん、白河上皇や本居宣長といった、その後の歴史的人物にも愛され、いろいろと論じられ...
収録日:2024/02/18
追加日:2024/10/21
対談 | 林望/ロバート キャンベル
十住心とは何か――迷いの世界から大日如来の心の世界へ
空海の真髄(3)十住心と大日如来の心の世界
十住心とは、十の意識のグラデーションないし心の十段階のことで、『秘蔵宝鑰』はそれを教相判釈的に解説している。中でも第十は大日如来の心の世界、すなわち秘密荘厳心が最上にして最大の包的な心の頂点と考える。今回は十住...
収録日:2024/08/26
追加日:2024/11/16