テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
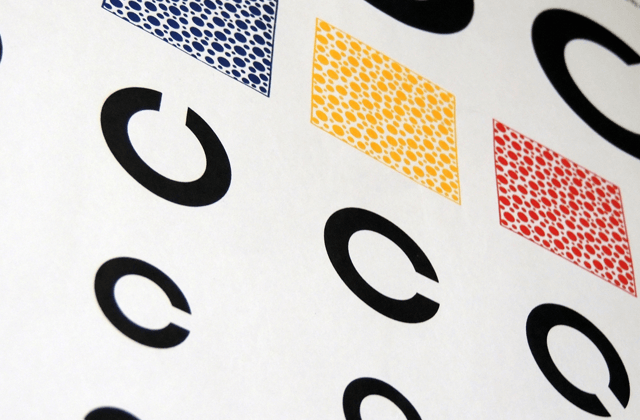
遠くが見える=「目が良い」のは勘違い?
よく「目が良い」と言うけれど……
昔から、裸眼で遠くまで見える人は、周囲にうらやましがられました。また、その当人も、「目が良い」ことをよく自慢していたものです。しかし、筑波大学眼科教授・大鹿哲郎氏は、そんな風潮を疑問視しています。そもそも「目が良い」「目が悪い」といった言い方は、日本語独特のものです。英語で似たようなことを表現する場合、端的に「視力が良い/悪い」というのであって、目そのものが良い/悪いとは言わないからです。では「目が良い」あるいは「目が悪い」とは、いったいどういうことなのでしょうか。
冒頭で述べたように、日本では「目が良い」=遠くまで見える(近視ではない)と考えるのが一般的です。しかし、日常の生活を振り返ったとき、そんなに遠くまで見ることはあるでしょうか。今、このコラムをスマホやパソコンで読んでいるみなさんは、手元しか見ていないのではありませんか。そう実は、現代社会で遠くまで見える必要はあまりないのです。
大鹿氏によれば、生活時間の3分の2は、身の回りしか見ていないそうです。いくら「目が良い」といっても、その良さを生かせる機会はそんなにないのですね。むしろ、「目が悪い」=「遠くは見えないが近くは見える」くらいが、現代社会には適しているとすら言えそうです。
現代社会で「視力2.0」は必ずしも必要ない
そのため、目が悪い人が視力矯正をする場合でも、必要以上に強い眼鏡やコンタクトレンズを着けるのは、目にあまり良くありません。たしかに強めの度数にすると、今までとは見違えるほど周りがよく見えて、「目が良い」ことを実感できるのですが、結果として目が疲れやすくなります。実際には、0.8~0.9くらいでも十分なのだそうです。レーシック手術によって近視を治す場合もありますが、同じ理由で強すぎる矯正は問題とのこと。必要以上に「目が良い」状態をめざす過矯正は、眼精疲労や肩凝り、頭痛、吐き気といった症状を引き起こすこともあるからです。必要以上に「目が良い」よりも、少しくらい「目が悪い」ほうが、ちょうど良いということです。
年齢のよって変化する、目の良さ
また大鹿氏は、どんな状態が「目が良い」状態で、どうなると「目が悪い」状態なのかは、年齢によって変化すると指摘します。子どもの頃は、たしかに「目が良い」方がうらやましがられます。しかし、年を取って老眼になると、眼鏡がなくても近くが見えることのほうが自慢になります。「目が悪い」人は近視ということになりますが、言い換えればその人は、近くはよく見えているわけです。反対に「目が良い」人には、遠視の傾向があります。しかも、遠視の人のほうが老眼の症状は出やすいそうで、そうなると、実は「目が悪い」と考えられてきた人のほうが、高齢社会では「目が良い」人ということになるのです。
時間がたてば目も変わる
時間がたてば、目の良さも変わってきます。それだけでなく、目の状態そのものも、年を取れば変わることがあるそうです。人の体は日々変化します。同様に、近視や遠視に影響する目の屈折も、実は変わっているのです。「目が良い」「目が悪い」とはどういうことかは、一義的に決まるものではありません。「目が良い」と言うためには、その人の生活環境まで含めて考えなければなりません。大切なのは、自分の目の状態を認識し、それに合った矯正や対策を行うことです。自分は「目が悪い」と落ち込んでいたみなさん、少しは心が軽やかになりましたか。
人気の講義ランキングTOP20










