テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
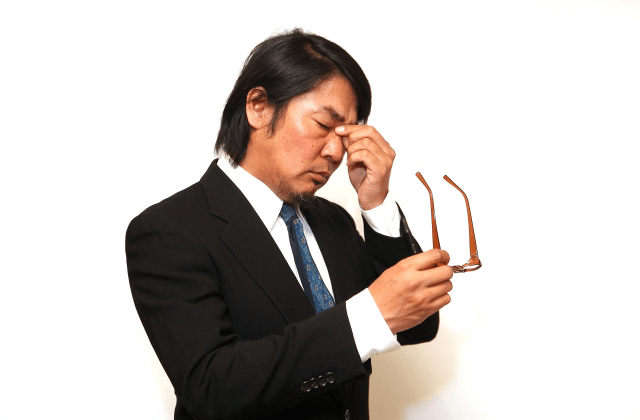
医師が語る「疲れ目」の原因と対策
昼間、パソコンとにらめっこして、目がショボショボ。通勤中にスマホの小さい画面でメールチェックして、目がチラチラ。寝る前につい携帯ゲーム機で遊んでしまって、目の奥がズーンと重い……。日常生活で目を酷使する現代人にとって、疲れ目は一生付き合っていかなければならない厄介モノです。
疲れ目対策をしようと目薬を買ってみたり、ブルーライトカットの眼鏡を使ってみたりしますが、根本的な改善にはなかなかつながりません。そもそも、疲れ目とは医学的にどのような症状のことをいうのでしょうか。また、疲れ目に有効な対策は本当にあるのでしょうか。そんな誰もが気になる疲れ目の原因と対策について、筑波大学眼科教授の大鹿哲郎氏が解説してくれました。
たとえば、画面の点滅です。いくら高精細になったとはいえ、パソコンやスマホの画面は紙に比べれば解像度が低く、かつチラチラと点滅しています。そのため、目は無意識にピント調節をしており、だんだんと疲れがたまっていきます。
パソコンなどを使用する環境も、疲れ目の原因となります。パソコンの画面に照明光が反射してしまう映り込みや画面の汚れは、画面の見にくさにつながって疲れ目の原因となります。また、画面をじっと見続けると、まばたきが減って目が乾きます。すると、目の表面がデコボコになって見にくくなり、疲れ目の原因となるのです。
また、照明の位置を変えれば、画面に光が映り込むことも防げます。画面が汚ければ、静電気防止のクロスなどで汚れを拭くといいでしょう。疲れ目の原因となる光の反射を抑制でき、見やすさが向上します。
画面そのものの明るさも、疲れ目の対策として気にするべきポイントです。暗いほうが疲れ目の対策にはなりそうですが、実は周囲の光量と差がありすぎると、ピントを調節しようとして無意識に目が動き、かえって疲れ目の原因となります。疲れ目の対策としては、部屋の明かりを少し落とした上で、画面は普通の明るさにするのがちょうど良いと、大鹿氏は言います。
ほかにも、エアコンの風向きを変えて目の乾燥を防いだり、書類を置くスタンドを設置してなるべく視線の移動を少なくしたりなど、疲れ目を緩和するための対策は実に多様です。
現在では老眼鏡の種類も増え、「中距離」用のものもあるそうです。これならば、パソコンの画面に対しても使えます。用途に合わせて複数の老眼鏡を用意した方が、より効果的な疲れ目対策になるということです。
疲れ目の原因は単純でないからこそ、複数の手段を使い分けて実施する。これが、疲れ目に対する最善の対策であるようです。大鹿氏の話をヒントに、ぜひ健康的な目を維持しましょう。
疲れ目対策をしようと目薬を買ってみたり、ブルーライトカットの眼鏡を使ってみたりしますが、根本的な改善にはなかなかつながりません。そもそも、疲れ目とは医学的にどのような症状のことをいうのでしょうか。また、疲れ目に有効な対策は本当にあるのでしょうか。そんな誰もが気になる疲れ目の原因と対策について、筑波大学眼科教授の大鹿哲郎氏が解説してくれました。
現代人の悩み、疲れ目のメカニズム
パソコンなどを長時間見て引き起こされる、疲れ目などの健康障害は、医学的にはVDT症候群と呼ばれます。疲れ目の直接的な原因は、目の中にある毛様体が固まってしまうことですが、その原因は複数あります。たとえば、画面の点滅です。いくら高精細になったとはいえ、パソコンやスマホの画面は紙に比べれば解像度が低く、かつチラチラと点滅しています。そのため、目は無意識にピント調節をしており、だんだんと疲れがたまっていきます。
パソコンなどを使用する環境も、疲れ目の原因となります。パソコンの画面に照明光が反射してしまう映り込みや画面の汚れは、画面の見にくさにつながって疲れ目の原因となります。また、画面をじっと見続けると、まばたきが減って目が乾きます。すると、目の表面がデコボコになって見にくくなり、疲れ目の原因となるのです。
疲れ目の対策あれこれ
ではどんな対策が有効でしょうか。大鹿氏によれば、まず画面の位置と照明の当たり方を気にすると良いそうです。画面が目に対して高すぎると、目を大きく見開くことになって乾燥しやすくなります。画面と水平か、あるいは少し低めの位置に置く方が、疲れ目の対策としてはちょうど良いとのことです。また、照明の位置を変えれば、画面に光が映り込むことも防げます。画面が汚ければ、静電気防止のクロスなどで汚れを拭くといいでしょう。疲れ目の原因となる光の反射を抑制でき、見やすさが向上します。
画面そのものの明るさも、疲れ目の対策として気にするべきポイントです。暗いほうが疲れ目の対策にはなりそうですが、実は周囲の光量と差がありすぎると、ピントを調節しようとして無意識に目が動き、かえって疲れ目の原因となります。疲れ目の対策としては、部屋の明かりを少し落とした上で、画面は普通の明るさにするのがちょうど良いと、大鹿氏は言います。
ほかにも、エアコンの風向きを変えて目の乾燥を防いだり、書類を置くスタンドを設置してなるべく視線の移動を少なくしたりなど、疲れ目を緩和するための対策は実に多様です。
老眼鏡の使い分けも有効
さらに大鹿氏は、老眼鏡も複数用意するのが良いと教えてくれました。というのも、一般的な老眼鏡の焦点距離よりも、パソコン画面と目の距離の方が多少長いからです。これでは、ピントが合う位置に画面がないことになるので、疲れ目の対策にはなりません。現在では老眼鏡の種類も増え、「中距離」用のものもあるそうです。これならば、パソコンの画面に対しても使えます。用途に合わせて複数の老眼鏡を用意した方が、より効果的な疲れ目対策になるということです。
疲れ目の原因は単純でないからこそ、複数の手段を使い分けて実施する。これが、疲れ目に対する最善の対策であるようです。大鹿氏の話をヒントに、ぜひ健康的な目を維持しましょう。
人気の講義ランキングTOP20










