テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
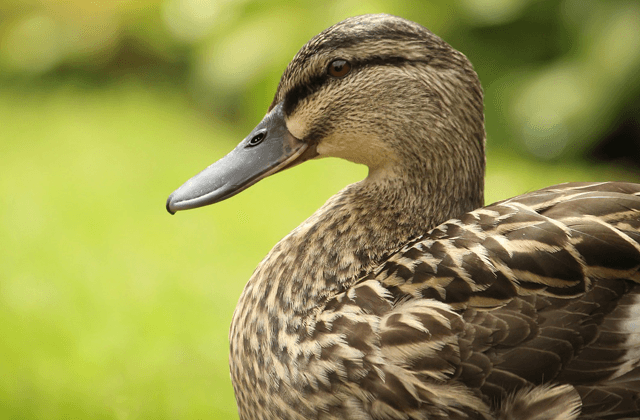
「野鴨の哲学」とはどういうものか?
2011年にWeb上にアップされた「IBM創立100周年記念サイト」には、「Wild Ducks(野鴨たち)」という映像が紹介されています。「野鴨の精神」はIBMの底流に流れるものであり、1959年当時IBM会長だったトーマス・ワトソンJr.は、「ビジネスには野鴨が必要なのです。そしてIBMでは、その野鴨を飼いならそうとは決してしません」と言ったというのです。1960年代から1980年代にかけてコンピュータの世界に君臨したトップ企業を支えた「野鴨の精神」とは、どういうものなのでしょうか。
湖には毎年、野鴨が飛来します。1万キロを超える旅をねぎらうため、近くに住む古老が餌をたっぷり用意して待つようになりました。もちろん渡り鳥である鴨は、容易には餌付けされません。しかし、毎年繰り返される饗応に、やがて野鴨たちは「何も苦労して次の湖へ飛び立つ必要はない」と思ったのでしょうか。とうとうそこに住み着いてしまいました。
そのうちに、老人が亡くなる日がやってくると、餌をもらえなくなった鴨たちは、自力で餌を探し、次の湖へ旅する必要にかられました。ところが、あてがいぶちのご馳走に慣れ、野生をなくしてしまった鴨たちは、まるでアヒルのように肥え、羽ばたいても飛べなくなっていました。
そこへ近くの山から雪を溶かした激流がなだれ込んできました。ほかの鳥たちは丘のほうへ素早く移動しましたが、かつてたくましい野生を誇った鴨たちは、なすすべもなく激流に飲み込まれていった、というお話です。
なぜ、「野鴨の話」が実存哲学とつながるのでしょうか。それは彼の死後、ドイツの哲学者ハイデッガーが、この話を「被投的投企の哲学」と呼んだからです。
人間は誰しも生まれる場所も時間も選べない。ハイデッガーの言う「投げ込まれた(被投)」状態ですが、その限られた状態の中で、これからどういう在り方をすべきかは、自分の責任で瞬間ごとに決めていけます(被投的投企)。哲学用語にすると難しくなりますが、「野鴨」に託されているのは、そのことだというのです。
それに比べると、冒頭のIBM会長の解釈である「飼い慣らされてはいけない。飼い慣らしてはいけない」は、いかにも明快に聞こえます。実は「投企」は英語ではプロジェクト(project)ですから、まだ誰も行ったことのないビジネス上の冒険を進めていくことは、「被投的投企」の連続状態とも呼べるわけです。
その内容は過激で、「この生は一回きりのものだから、ただ漠然と時を過ごすことは罪悪である。月曜から土曜までなんとなく安穏に生きた市民たちが、日曜の教会で賛美歌を歌えば許されるという考えも、それを勧める牧師の説教もちゃんちゃらおかしい」と言うのですから、嫌われても仕方ないでしょう。
42歳の秋に、キェルケゴールはコペンハーゲンの路上で卒倒し、雪かきが必要なほど大雪が降る日まで誰にも助け出してもらえず、そのままなくなりました。攻撃を受ければ受けるほど、「私は紛れもなく生きている」と感じた「野鴨の哲学」は、現代の日本にこそ必要である、と日本BE研究所所長の行徳哲男氏は語っています。
渡りをやめた野鴨の話
デンマークの首都コペンハーゲンは、シェラン島(ジーランド)という島の東部にあります。島の北部には、「ハムレット」の舞台となったクロンボー城、歴代デンマーク王の居城フレデリクスボー城があり、大きな森と有数の湖沼地帯を抱えることでも有名です。湖には毎年、野鴨が飛来します。1万キロを超える旅をねぎらうため、近くに住む古老が餌をたっぷり用意して待つようになりました。もちろん渡り鳥である鴨は、容易には餌付けされません。しかし、毎年繰り返される饗応に、やがて野鴨たちは「何も苦労して次の湖へ飛び立つ必要はない」と思ったのでしょうか。とうとうそこに住み着いてしまいました。
そのうちに、老人が亡くなる日がやってくると、餌をもらえなくなった鴨たちは、自力で餌を探し、次の湖へ旅する必要にかられました。ところが、あてがいぶちのご馳走に慣れ、野生をなくしてしまった鴨たちは、まるでアヒルのように肥え、羽ばたいても飛べなくなっていました。
そこへ近くの山から雪を溶かした激流がなだれ込んできました。ほかの鳥たちは丘のほうへ素早く移動しましたが、かつてたくましい野生を誇った鴨たちは、なすすべもなく激流に飲み込まれていった、というお話です。
「野鴨の話」と実存哲学
この話は、コペンハーゲン生まれの哲学者、セーレン・キェルケゴール(1813-1855)が残したものです。7人兄弟の末子として、家政婦から後妻になった母と、裕福な商人の父の間で育った彼は、若い頃から憂鬱な傾向がある一方、物事を深く見据え、容易には承知しない実存哲学者の先駆けとして、『死に至る病』などの著書を残しました。なぜ、「野鴨の話」が実存哲学とつながるのでしょうか。それは彼の死後、ドイツの哲学者ハイデッガーが、この話を「被投的投企の哲学」と呼んだからです。
人間は誰しも生まれる場所も時間も選べない。ハイデッガーの言う「投げ込まれた(被投)」状態ですが、その限られた状態の中で、これからどういう在り方をすべきかは、自分の責任で瞬間ごとに決めていけます(被投的投企)。哲学用語にすると難しくなりますが、「野鴨」に託されているのは、そのことだというのです。
それに比べると、冒頭のIBM会長の解釈である「飼い慣らされてはいけない。飼い慣らしてはいけない」は、いかにも明快に聞こえます。実は「投企」は英語ではプロジェクト(project)ですから、まだ誰も行ったことのないビジネス上の冒険を進めていくことは、「被投的投企」の連続状態とも呼べるわけです。
現代日本に「野鴨の哲学」を
いずれにせよキェルケゴール自身は、「飼い慣らされない」ことを他者、主に当時の教会の在り方への懐疑と批判としてぶつけたため、同時代人からたいそう嫌われたと言います。その内容は過激で、「この生は一回きりのものだから、ただ漠然と時を過ごすことは罪悪である。月曜から土曜までなんとなく安穏に生きた市民たちが、日曜の教会で賛美歌を歌えば許されるという考えも、それを勧める牧師の説教もちゃんちゃらおかしい」と言うのですから、嫌われても仕方ないでしょう。
42歳の秋に、キェルケゴールはコペンハーゲンの路上で卒倒し、雪かきが必要なほど大雪が降る日まで誰にも助け出してもらえず、そのままなくなりました。攻撃を受ければ受けるほど、「私は紛れもなく生きている」と感じた「野鴨の哲学」は、現代の日本にこそ必要である、と日本BE研究所所長の行徳哲男氏は語っています。
人気の講義ランキングTOP20










