テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
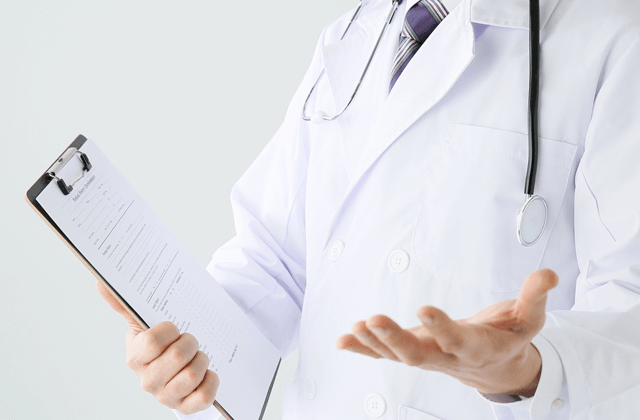
男性更年期に対処する!男性ホルモンをアップさせる方法
男性のバイタリティとプロダクティビティの根源、男性ホルモン。年齢とともに男性ホルモン(テストステロン)が減少することは昔からよく知られていましたが、中年期以降の男性のクオリティ・オブ・ライフを著しく下げていることが分かってきました。いわゆる「男性更年期」です。日本で初めて男性外来であるメンズヘルス外来を開設した経験をお持ちの順天堂大学医学部大学院医学研究科教授・堀江重郎医師のレクチャーから、男性更年期障害の特徴をかいつまんでみました。
「おーい、お茶」と呼んで、素直にお茶が出てきたら、夫の男性ホルモン量はまだまだ活発で、妻に負けていません。
「たまにはあなたも自分で入れたら」と小言と一緒にお茶が出てきたら、夫婦の男性ホルモン量はかなり接近しています。
「おーい、お茶入れたぞ」と夫が言ってしまう家庭では、妻の男性ホルモン量が逆転して、夫を上回っているというのです。
これは半分ジョークではありますが、女性が更年期を迎えると男性ホルモンが多くなるのは事実です。男性と女性の「更年期」の違いを見てみましょう。
エストロゲン周期から解放された女性は、男性ホルモンの影響を受け、より社会的な活動を行ったり、仲間と旅に出たり、何か新しいことを始めたり、活発に行動するようになります。女性にとって「更年期」は、まさに「人生をチェンジする」ための一時期なのです。
一方男性の「更年期」は、時期が特定されていません。加齢とストレスによる男性ホルモンの減少は、40代以降いつ起こっても不思議ではなく、全く感じない人も多いからです。何となく体の疲れが取れなかったり、だるさを感じるのが初期の自覚症状でしょう。何事もおっくうになりがちで、太る人もいます。筋肉をつくると同時に、脂肪組織の増加を抑える働きも担うのが男性ホルモンだからです。このため、更年期の男性ではお腹が出てくる、骨密度が減る、動脈硬化が進むなど、さまざまな影響が出てきます。
ほてり、発汗、うつ、不眠など、女性とまったく同様の症状も出現します。女性との違いは、一過性のものではなく、適切な対処をしない限り回復しない点です。不調の原因が男性ホルモンの減少にあるかもしれないと思い当たったら、そのままにしないことが重要だと堀江医師は言います。
男性ホルモンをアップさせる方法は、ホルモン補充療法だけではありません。毎日が決まりきった行動パターンに陥っている自覚のある人には、「行動を変える」ことが有効だと堀江医師は言います。例えば長距離通勤をしている人は、週に一度ぐらいは会社の近くに宿を取り、ゆっくり睡眠をとってみるのもそのひとつです。
また、定期的な運動も効果があります。ジム通いが無理でも、階段の上り下りを1日10分することから始めてはいかがでしょうか。食事で重要なのはブロッコリーやネギ類などの野菜とたんぱく質。炭水化物中心の食事は男性ホルモンを減らすということです。最後に、今日からすぐに重視したいのが睡眠。睡眠アプリなども活用して、7時間の連続睡眠をぜひ確保してください。
「おーい、お茶」テストで分かる男性ホルモン格差
ユーモラスなお人柄の堀江医師が冗談交じりに勧めるのは「おーい、お茶」テスト。自宅の茶の間で「おーい、お茶」と言ったときの反応を3段階に分けています。「おーい、お茶」と呼んで、素直にお茶が出てきたら、夫の男性ホルモン量はまだまだ活発で、妻に負けていません。
「たまにはあなたも自分で入れたら」と小言と一緒にお茶が出てきたら、夫婦の男性ホルモン量はかなり接近しています。
「おーい、お茶入れたぞ」と夫が言ってしまう家庭では、妻の男性ホルモン量が逆転して、夫を上回っているというのです。
これは半分ジョークではありますが、女性が更年期を迎えると男性ホルモンが多くなるのは事実です。男性と女性の「更年期」の違いを見てみましょう。
女性の更年期と男性の更年期の違い
女性の更年期は月経終了に伴うもので、閉経前後5年と決まっています。更年期の間の女性は、女性ホルモン(エストロゲン)が急激に下がるため、心身の変調をきたし、ほてりや発汗、うつ、不眠などに悩まされます。しかし、現代の女性は平均寿命85歳。更年期が終わっても、平均して30年ほどの人生が残されています。エストロゲン周期から解放された女性は、男性ホルモンの影響を受け、より社会的な活動を行ったり、仲間と旅に出たり、何か新しいことを始めたり、活発に行動するようになります。女性にとって「更年期」は、まさに「人生をチェンジする」ための一時期なのです。
一方男性の「更年期」は、時期が特定されていません。加齢とストレスによる男性ホルモンの減少は、40代以降いつ起こっても不思議ではなく、全く感じない人も多いからです。何となく体の疲れが取れなかったり、だるさを感じるのが初期の自覚症状でしょう。何事もおっくうになりがちで、太る人もいます。筋肉をつくると同時に、脂肪組織の増加を抑える働きも担うのが男性ホルモンだからです。このため、更年期の男性ではお腹が出てくる、骨密度が減る、動脈硬化が進むなど、さまざまな影響が出てきます。
ほてり、発汗、うつ、不眠など、女性とまったく同様の症状も出現します。女性との違いは、一過性のものではなく、適切な対処をしない限り回復しない点です。不調の原因が男性ホルモンの減少にあるかもしれないと思い当たったら、そのままにしないことが重要だと堀江医師は言います。
まずはホルモン値の測定を、そして行動変容を
現在は、多くの医療機関で男性ホルモン(テストステロン)の測定が可能になっています。まだまだ若いつもりなのに、なぜか調子が悪い、やる気が出ない人、「あなた、男性更年期じゃない?」と妻から言われたことのある人は、ぜひ測ってみてほしい、と堀江医師。「今の自分を知る」ために、また今後をより明るくするために貴重な体験です。男性ホルモンをアップさせる方法は、ホルモン補充療法だけではありません。毎日が決まりきった行動パターンに陥っている自覚のある人には、「行動を変える」ことが有効だと堀江医師は言います。例えば長距離通勤をしている人は、週に一度ぐらいは会社の近くに宿を取り、ゆっくり睡眠をとってみるのもそのひとつです。
また、定期的な運動も効果があります。ジム通いが無理でも、階段の上り下りを1日10分することから始めてはいかがでしょうか。食事で重要なのはブロッコリーやネギ類などの野菜とたんぱく質。炭水化物中心の食事は男性ホルモンを減らすということです。最後に、今日からすぐに重視したいのが睡眠。睡眠アプリなども活用して、7時間の連続睡眠をぜひ確保してください。
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










