テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
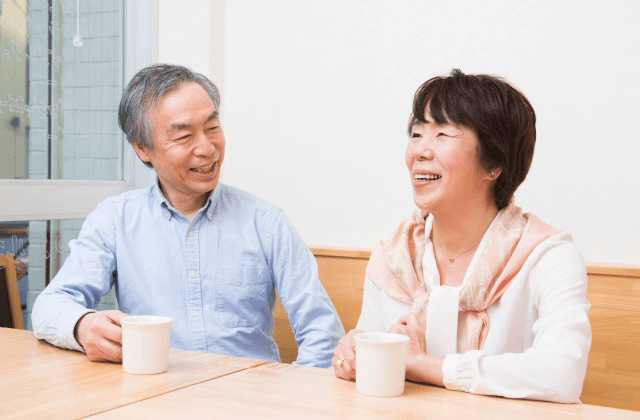
長寿社会で「住み慣れた場所で年を取る」ためには?
高齢者にとっての、ささやかだけれど最大の願い
世界に名だたる長寿国日本ですが、平均寿命と健康寿命の差は女性で12.93年、男性で9.79年と男女とも10年前後を何らかの介助、介護を必要として人生の最晩年を送っているという現実があります。また、地域差はあるものの病院での看取りが約8割。自宅で最期を迎える人は年々少なくなってきています。しかし、誰しもが、住み慣れたわが町、わが家で「いつもの散歩コースのお気に入りの喫茶店で、いつものブレンド一杯片手に本を読む」とか「長年通っている床屋でさっぱりした後、魚屋をのぞいて夕食用の刺身を買う」といったささやかな楽しみを味わいながら、安心して年を重ねたいと思うはず。このような現状、多くの人々の願望をふまえて、東京大学高齢社会総合研究機構(IOG)では、「エイジングインプレイス」のコンセプトのもと、「住み慣れたところで、安心して自分らしく年を取る」ために必要なプロジェクトをいくつも手がけています。
住宅はライフステージに合わせて住み替える
東京大学高齢社会研究機構特任教授の秋山弘子氏によれば、住み慣れた場所で安心して老後生活を送るためには、いくつかのポイントがあります。その第一は住宅です。日本は持ち家政策を進めてきたこともあり、「庭付き、2階建ての一軒家」志向が強いのですが、実は人生100年時代ともなってくると、この立派な家が子どもたちも巣立ったあとで老夫婦、あるいは独居老人には大きなストレスになっているのです。そこでIOGは、ライフステージに応じて適切なサイズの家に住み替えていく「循環型住宅政策」を提案しました。柏のある団地では、最初は大きなユニットに住み、子どもたちが独立すると小さなユニットに移ることができます。ヤドカリは体の成長に合わせて新しい貝殻に引越ししますが、いわばこれはエイジングに応じた「逆ヤドカリ」スタイル。また、同じ敷地内で、状況に応じてサービス付の高齢者住宅に移ったり、ケアシステムの整ったグループホームに移ることも可能とか。「同じ敷地内」というのがミソで、これならば、いつもの買い物や病院、クリニック通いを変える必要がありません。生活環境を変更しないで済むというのも、ストレス軽減に効果ありなのです。
医療や介護を「届ける」という発想
医療や介護ケアの問題も切実です。年を取ってくると、近所に病院やかかりつけのドクターがいる・いないにかかわらず、そこまで行くのが大きな問題です。そこで、出てきたのが医療も介護も「届ける」という発想。政府が推進する「地域包括ケア」の方針のもと、地域の医療機関や介護施設と連携したり、団地の中心に在宅医療の拠点を作ったりしています。こうすることで、元気な人は病院やリハビリセンターに出かけていく、必要に応じて、ホームドクターやホームヘルパーに定期的に来てもらう、デイサービスの送り迎えをするといった、それぞれの状況に応じたプランが組まれているのだそうです。
サービス付高齢者住宅のサービス内容も「届ける」のコンセプトのもと充実させました。24時間対応の医療機関や訪問看護、訪問介護ステーションを設置し、食事や薬局からの薬の宅配も含めたサービスが、高齢者住宅に住んでいる人のみならず地域住民全体に届けられるという、充実、安心のシステムです。
プロジェクト推進への鍵は産学官民の連携、協働体制作り
このほかにも、高齢者にとって大問題の移動手段の提供やICTの活用など、柔軟な発想で「エイジングインプレイス」プロジェクトが進められているのですが、一番の鍵は産学官民の連携、協働体制作りだとか。しかし、そのためには分野、部局横断の組織、仕組み作りが必要なのに、各組織の縦割りシステムを崩すのが容易ではないと、秋山氏は語ります。こうして聞いてみると、どうやら、エイジングインプレイスには、場所や環境そのものの豊かなエイジング、成熟も必要なのだと思わされます。人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










