テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
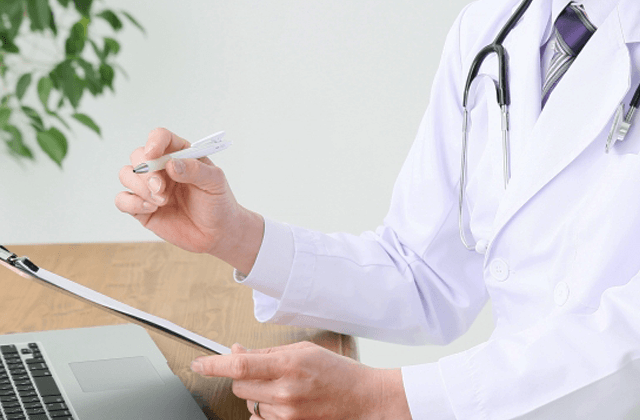
統計で見る「がん」の恐ろしさ
ここ数年のデータによると、生涯で日本人の2人に1人は何らかの「がん」に罹患しています。さらに日本人の死亡原因は、1位「悪性新生物(がん)」28.5%、2位は「心疾患」で15.1%、3位は「肺炎」で9.1%です。つまりおよそ日本人の4人に1人はがんで死亡しています(2016年のデータ)。このような数字だけを見ると、がんは怖いかもしれません。しかし、早期発見できれば問題ないがんもあります。ここではもう少し詳しくデータを見ながら、がんをとりまく状況を整理してみます。
<男性>
1位「肺」
2位「胃」
3位「大腸」
4位「肝臓」
5位「膵臓」
<女性>
1位「大腸」
2位「肺」
3位「膵臓」
4位「胃」
5位「乳房」
男女ともに「肺」「大腸」「胃」の死亡数が多く、女性に多い、「乳房」以外はおおよそ共通しているといえるでしょう。ただし、この数値は「死亡原因とされたがんの種類」です。つまり、その部位のがんにかかる人が多ければそのがんが原因とされた死亡者数も増えます。ではどのような部位のがんの死亡率が高いのでしょうか。この場合、「5年相対生存率」に注目する必要があります。
2006年から2008年にがんと診断された人全体の「5年相対生存率」は男性62.1%、女性66.0%です。部位別で見ると男性は前立腺(97.5%)、皮膚(92.2%)、甲状腺(89.5%)の順に高く、女性では甲状腺(94.9%)、皮膚(92.5%)、乳房(91.1%)の順に高くなっています。
数値をみて分かる通り、がんの部位によっては「5年相対生存率」が100%に近いものもあります。この生存率が高いがんは、比較的進行が緩やかである場合が多く、早期であるステージⅠで発見できれば対策が取りやすいようです。また、乳がんは乳房のしこりなどの症状が出るという点もあり、意識をもっていれば早期発見しやすいという点もあります。
これに対して、「5年相対生存率」が低い部位に膵臓があります。男性4.6%、女性4.8%という数値です。理由としては、初期には症状が出ないことが多く、早期に発見しにくいということのようです。つまり、がん治療には早期発見できるかどうかということがカギだということはこの数値から分かります。
インターネットで「がん」について探すと、大量の情報が溢れています。何を信じていいのか分からなくなるかもしれません。その中で、国立がん研究センターが解説している「がん情報サービス」をおすすめします。がんそのものについての情報のほかに、がんの疑いがあると言われた方がどうすればよいか、まわりの人間はどう対処すべきか、といったことなど専門家が丁寧に回答しています。
どのようながんで死亡数が多いのか
2016年のデータによると、がんで死亡した人の総数は37万2986人で、内訳は男性21万9785人、女性15万3201人となっています。死亡数が多い部位の上位はそれぞれ以下のようになっています。<男性>
1位「肺」
2位「胃」
3位「大腸」
4位「肝臓」
5位「膵臓」
<女性>
1位「大腸」
2位「肺」
3位「膵臓」
4位「胃」
5位「乳房」
男女ともに「肺」「大腸」「胃」の死亡数が多く、女性に多い、「乳房」以外はおおよそ共通しているといえるでしょう。ただし、この数値は「死亡原因とされたがんの種類」です。つまり、その部位のがんにかかる人が多ければそのがんが原因とされた死亡者数も増えます。ではどのような部位のがんの死亡率が高いのでしょうか。この場合、「5年相対生存率」に注目する必要があります。
生存率の高いがんとは
「5年相対生存率」とは、がんと診断されたのち5年後に生存している割合が、日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどの程度なのかを示しています。100%に近いほど治療で救えるがんあるということです。2006年から2008年にがんと診断された人全体の「5年相対生存率」は男性62.1%、女性66.0%です。部位別で見ると男性は前立腺(97.5%)、皮膚(92.2%)、甲状腺(89.5%)の順に高く、女性では甲状腺(94.9%)、皮膚(92.5%)、乳房(91.1%)の順に高くなっています。
数値をみて分かる通り、がんの部位によっては「5年相対生存率」が100%に近いものもあります。この生存率が高いがんは、比較的進行が緩やかである場合が多く、早期であるステージⅠで発見できれば対策が取りやすいようです。また、乳がんは乳房のしこりなどの症状が出るという点もあり、意識をもっていれば早期発見しやすいという点もあります。
これに対して、「5年相対生存率」が低い部位に膵臓があります。男性4.6%、女性4.8%という数値です。理由としては、初期には症状が出ないことが多く、早期に発見しにくいということのようです。つまり、がん治療には早期発見できるかどうかということがカギだということはこの数値から分かります。
がんとともに生きるには
がんが不治の病と呼ばれていた時代がありました。しかし、現代では有効な薬や治療法がさまざまな方向から研究されています。また、こういった医療技術の進歩に合わせて、社会通念も変化しつつあります。治療しながら、また再発を抑制しながら働く人も増えています。がんになったら終わりではありません。インターネットで「がん」について探すと、大量の情報が溢れています。何を信じていいのか分からなくなるかもしれません。その中で、国立がん研究センターが解説している「がん情報サービス」をおすすめします。がんそのものについての情報のほかに、がんの疑いがあると言われた方がどうすればよいか、まわりの人間はどう対処すべきか、といったことなど専門家が丁寧に回答しています。
<参考サイト>
・国立がん研究センター:最新がん統計
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
・国立がん研究センター:がん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/index.html
・国立がん研究センター:最新がん統計
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
・国立がん研究センター:がん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/index.html
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










