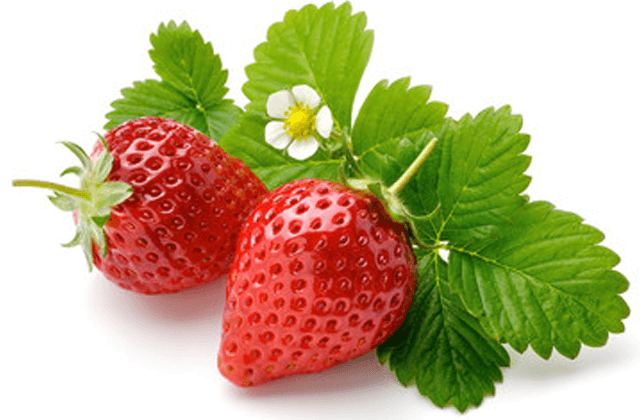
もっと知りたいイチゴの世界
「つぶろまん」「もういっこ」「ペチカ」「サマーアミーゴ」。さて、これらは何につけられた名前かお分かりでしょうか? 「とちおとめ」「紅ほっぺ」「あまおう」とくれば、もう分かりますね。そう、イチゴの名前なのです。季節になれば、近所のスーパーでも3~4種類は並ぶとても身近な果物、イチゴ。しかし、意外にも初めて知って「へぇ~」っと驚くイチゴトリビアが結構あるのです。
イチゴの果肉の外側についているツブツブ、「あれはイチゴの種なんだよ」と聞いて、あんなに小さな種から育てるなんて大変だなと思ったことはありませんか? 実はあのツブツブがイチゴの果実で植物形態学的には「痩果」といいます(確かに、“痩せた果実”ですね)。私たちが果肉と思っている部分は、果托が肥大した偽果なのです。
さらに、栄養成分も詳しく見るとちょっと驚きです。甘味の元となるブドウ糖や果糖、ビタミンCが非常に豊富であることは知っていましたが、疲労回復効果のあるアスパラギン酸や旨味成分であるグルタミンミン酸も含まれているのだとか。こうした栄養、効能を聞くと、平昌オリンピックで話題となったカーリング女子の「もぐもぐタイム」に、たびたびイチゴが登場していたのもうなずけます。
福羽逸人は促成栽培が農家にとって有望な収入源になると確信していたのですが、当初、その最先端の栽培方法は珍しさが先にたって実際に導入しようとする人はいませんでした。ようやく明治末期になってその栽培が定着し、石垣イチゴのような栽培方法も導入されるようになったのです。この促成栽培で急速に生産量が拡大したのは1950年頃から。その大きな要因は、施設栽培に不可欠のプラスチックフィルムが普及したからです。イチゴと言えばいわゆるビニールハウスを思い浮かべますが、高度経済成長による素材普及がイチゴ栽培にも影響していたのですね。
そのうえ、他の果物と違って硬い果皮に包まれているわけではないので、傷みやすく貯蔵や輸送には工夫が必要。露地ものであれば、果肉もキュッとしまっているのでさほど神経は使いませんが、大事に大事に育てられた日本の促成栽培イチゴはこの点かなりデリケートなのです。
こうしたことを踏まえて、栽培農家、研究者はまずイチゴの生理・生態をよく理解し、栽培技術に生かそうと努力しました。その結果、今では日本のイチゴの花成と休眠の制御技術は世界有数と評価されるまでになったのです。容器についてもしかり。よく外国の市場の様子を見ると、イチゴが裸のまま山積みになっていたりしますが、日本ではもってのほか。実を傷つけないように平たく浅い容器にしたり、場合によっては一粒ずつ収まる凹みをつけたりと、収穫後にもさまざまな創意工夫がされているのです。
その代わり、冒頭でもちょっと触れたように品種はまさに百花繚乱。各生産地で独自の品種を開発し、今やイチゴ界は多品種化、ブランド化、ご当地化の傾向にあり、また、花や香りを愛でる鑑賞用の開発にも熱心と聞きます。コンピューター制御による栽培施設や人工光利用の植物工場の研究、ITやAI、IoTの導入・連動など、イチゴ栽培は新世紀を迎えているといってもよいでしょう。
身近でありながら、常に変化、進化してきた果物。こうやってイチゴ栽培の歴史やさまざまな工夫を知ると、「がんばれ、日本のイチゴ!」と応援したくなります。最後に、この本で知った、今すぐに役立つイチゴ知識をご紹介しておきましょう。イチゴはへたの部分をつまんで尖端の方から口に入れるという方がほとんどだと思いますが、実はこの食べ方は損。先っぽの方ほど糖含量が高いので、こちらを後にして食べた方がより甘味を味わうことができるのです。大切に育てられ運ばれてきたイチゴですから、どうぞ一番おいしい食べ方をしてあげてください。
意外と知らないイチゴのあれこれ
イチゴトリビアを知ったきっかけは山形大学農学部野菜園芸学研究室教授・西澤隆氏の著書『まるごとわかるイチゴ』です。イチゴ栽培や研究に携わる人、農業技術の指導者など、いわば「イチゴの専門家」をメインの対象とした本ですが、自分でイチゴを育ててみたい園芸愛好家、イチゴ大好きというイチゴラバーでも興味をもって読める内容です。イチゴの果肉の外側についているツブツブ、「あれはイチゴの種なんだよ」と聞いて、あんなに小さな種から育てるなんて大変だなと思ったことはありませんか? 実はあのツブツブがイチゴの果実で植物形態学的には「痩果」といいます(確かに、“痩せた果実”ですね)。私たちが果肉と思っている部分は、果托が肥大した偽果なのです。
さらに、栄養成分も詳しく見るとちょっと驚きです。甘味の元となるブドウ糖や果糖、ビタミンCが非常に豊富であることは知っていましたが、疲労回復効果のあるアスパラギン酸や旨味成分であるグルタミンミン酸も含まれているのだとか。こうした栄養、効能を聞くと、平昌オリンピックで話題となったカーリング女子の「もぐもぐタイム」に、たびたびイチゴが登場していたのもうなずけます。
イチゴ栽培の歴史
イチゴの栽培の歴史は、実は案外と浅く世界的にみても300年に満たないのだそうです。北米原産のバージニアイチゴと南米原産のチリイチゴの交雑種がヨーロッパで育成され、日本には江戸時代末期にオランダ人によって導入されました。このオランダイチゴが明治になって広く栽培されるようになり、今私たちが食べている商業品種になっているのです。本格的な栽培品種を作ったのが近代園芸学の祖とも言われる福羽逸人(ふくばはやと)。1898年(明治31)国産イチゴ第一号となる「福羽」を作出し、この品種が現在の「あまおう」や「とよのか」のルーツとなりました。福羽逸人は促成栽培が農家にとって有望な収入源になると確信していたのですが、当初、その最先端の栽培方法は珍しさが先にたって実際に導入しようとする人はいませんでした。ようやく明治末期になってその栽培が定着し、石垣イチゴのような栽培方法も導入されるようになったのです。この促成栽培で急速に生産量が拡大したのは1950年頃から。その大きな要因は、施設栽培に不可欠のプラスチックフィルムが普及したからです。イチゴと言えばいわゆるビニールハウスを思い浮かべますが、高度経済成長による素材普及がイチゴ栽培にも影響していたのですね。
さまざまな研究、技術や工夫が実って今のイチゴに
イチゴはさんさんと降り注ぐ太陽光のもと真っ赤に成長するというイメージがありますし、確かに光合成はイチゴの成果に重要なのですが、実は高温・高湿度が大の苦手。つまり、日本のように夏が高温多湿の地域では栽培は不向きなのです。さらに、イチゴには寒さにあたると休眠し、春になると休眠打破して開花、結果するという「休眠特性」があります。一定期間低温を経過しないとイチゴは目を覚まさず、ちゃんと目覚めないと適温を与えても十分に成長しない。かつ、低温が続く環境下では自発休眠時期が終わっても眠り続ける。このようにかわいい姿形のわりには、なかなか気難しいのです。そのうえ、他の果物と違って硬い果皮に包まれているわけではないので、傷みやすく貯蔵や輸送には工夫が必要。露地ものであれば、果肉もキュッとしまっているのでさほど神経は使いませんが、大事に大事に育てられた日本の促成栽培イチゴはこの点かなりデリケートなのです。
こうしたことを踏まえて、栽培農家、研究者はまずイチゴの生理・生態をよく理解し、栽培技術に生かそうと努力しました。その結果、今では日本のイチゴの花成と休眠の制御技術は世界有数と評価されるまでになったのです。容器についてもしかり。よく外国の市場の様子を見ると、イチゴが裸のまま山積みになっていたりしますが、日本ではもってのほか。実を傷つけないように平たく浅い容器にしたり、場合によっては一粒ずつ収まる凹みをつけたりと、収穫後にもさまざまな創意工夫がされているのです。
減産傾向、多品種化という波
こうした努力で、日本の至るところで栽培されるようになったイチゴですが、実は1980年代後半をピークに生産は漸減傾向となり、今では最盛期の3/4に留まっています。品種改良などで収穫期が長くなり供給量が飽和状態になったことが、生産量の減少につながっているとされています。その代わり、冒頭でもちょっと触れたように品種はまさに百花繚乱。各生産地で独自の品種を開発し、今やイチゴ界は多品種化、ブランド化、ご当地化の傾向にあり、また、花や香りを愛でる鑑賞用の開発にも熱心と聞きます。コンピューター制御による栽培施設や人工光利用の植物工場の研究、ITやAI、IoTの導入・連動など、イチゴ栽培は新世紀を迎えているといってもよいでしょう。
身近でありながら、常に変化、進化してきた果物。こうやってイチゴ栽培の歴史やさまざまな工夫を知ると、「がんばれ、日本のイチゴ!」と応援したくなります。最後に、この本で知った、今すぐに役立つイチゴ知識をご紹介しておきましょう。イチゴはへたの部分をつまんで尖端の方から口に入れるという方がほとんどだと思いますが、実はこの食べ方は損。先っぽの方ほど糖含量が高いので、こちらを後にして食べた方がより甘味を味わうことができるのです。大切に育てられ運ばれてきたイチゴですから、どうぞ一番おいしい食べ方をしてあげてください。
<参考文献>
『まるごとわかるイチゴ』西澤 隆著(誠文堂新光社)
http://www.seibundo-shinkosha.net/products/detail.php?product_id=5573
『まるごとわかるイチゴ』西澤 隆著(誠文堂新光社)
http://www.seibundo-shinkosha.net/products/detail.php?product_id=5573
人気の講義ランキングTOP20
ダーウィン「進化論」執筆の背景…娘の死と信仰との決別
長谷川眞理子







