テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
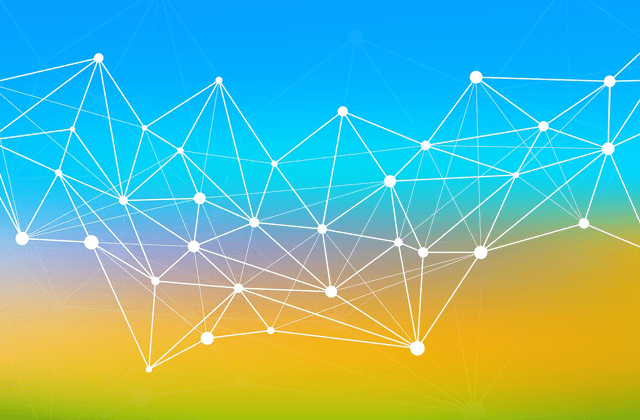
科学技術外交の最前線とSDGs(持続可能な開発目標)
「科学技術外交」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。科学技術外交には、科学者が外交官を、外交官が科学者を助け、あるいは科学領域の国際交流が外交を助けるという3つのタイプがあります。日本の科学技術外交は2015年以来、新しいフェーズに入っています。この年の9月、東京大学名誉教授で新構造材料技術研究組合(ISMA)理事長の岸輝雄氏が、日本で初めて「外務大臣科学技術顧問」という役職に就任したからです。
岸氏のもとには、「科学技術外交アドバイザリー・ネットワーク」が構築され、その一環として、生命科学、医学、生命工学、情報通信、原子力、国際関係、農学、環境、官民連携の学識経験者が集められ、「科学技術外交推進会議」委員として、科学技術外交の企画・立案に資しています。
科学技術外交の指針を握る岸氏が重要視しているのは、国連の定めた「SDGs」。"Sustainable Development Goals"の略で、「持続可能な開発目標」と訳されます。MDGsの終了後、2015年の国連で持続可能な開発のための2030アジェンダが採択されているのです。
SDGsでは、先進国と途上国がともに取り組むべき17の目標と169のターゲットが明記されています。日本はSDGs推進本部を設置し、実施指針を策定する一方、科学技術をもってどのように貢献していくかをも熟慮。「SDGsのためのSTI(Science, Technology and Innovation、科学技術イノベーション)」の第二回フォーラムでは、日本の強みである環境・防災技術などが紹介されました。
「1. 貧困をなくそう」の手がかりは衣食住の材料を提案することにあたります。「3. すべての人に健康と福祉を」に役立つのは、バイオチップや人工骨などの開発になります。「6. 安全な水とトイレを世界中に」のゴールには、ナノテクノロジーを用いた「逆浸透膜」が大きくものをいうことになりそうです。
「7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに」というゴールがありますが、そのためには原子力にどう向き合うかが問われます。福島やもんじゅの例もありますが、廃棄物処理についての答えも出ていません。高いコストとリスクをどうするべきなのか。科学技術にとって大きな課題だと岸氏は考えています。
STIがどうSDGsに寄与するかは産官学のほぼあらゆる分野から注目され、実施段階に移ろうとしています。その一方で、情報革命とマテリアル革命が刻々と進んでいるのが日本の現状です。
そのためにも、計算化学や情報工学を導入したマテリアルズインテグレーションにより、材料の組織や特性、性能を予測していくことは必須になり、やがて来るマテリアル革命につながるでしょう。
研究システムも従来のような単位ではなく、国際的な産学連携を視野に入れたパートナーシップが必要になります。そのためにもSDGsは大きな指針を与えてくれます。
バラバラになりがちなSDGsに、東京大学第28代総長の小宮山宏氏が提唱する「プラチナ社会」的な知の構造化を用いて、STI for SDGsの構造化を進めること。最重要課題に向けて、岸氏の目標は定まっているようです。
世界で4番目の「外務大臣科学技術顧問」として
「外務大臣科学技術顧問」のような役職が政府に置かれるのは米国、英国、ニュージーランドに続いて日本が4番目。科学技術を外交の重要な要素の一つととらえる見方は、21世紀になってようやく定着したかたちですが、国際的課題解決のための政策決定過程において、科学的知見の重要性は言うまでもありません。岸氏のもとには、「科学技術外交アドバイザリー・ネットワーク」が構築され、その一環として、生命科学、医学、生命工学、情報通信、原子力、国際関係、農学、環境、官民連携の学識経験者が集められ、「科学技術外交推進会議」委員として、科学技術外交の企画・立案に資しています。
科学技術外交の指針を握る岸氏が重要視しているのは、国連の定めた「SDGs」。"Sustainable Development Goals"の略で、「持続可能な開発目標」と訳されます。MDGsの終了後、2015年の国連で持続可能な開発のための2030アジェンダが採択されているのです。
SDGsでは、先進国と途上国がともに取り組むべき17の目標と169のターゲットが明記されています。日本はSDGs推進本部を設置し、実施指針を策定する一方、科学技術をもってどのように貢献していくかをも熟慮。「SDGsのためのSTI(Science, Technology and Innovation、科学技術イノベーション)」の第二回フォーラムでは、日本の強みである環境・防災技術などが紹介されました。
材料工学をSDGsに当てはめてみると?
たとえば、岸氏の専門分野である材料工学をSDGsに当てはめるとどうなるでしょうか。「1. 貧困をなくそう」の手がかりは衣食住の材料を提案することにあたります。「3. すべての人に健康と福祉を」に役立つのは、バイオチップや人工骨などの開発になります。「6. 安全な水とトイレを世界中に」のゴールには、ナノテクノロジーを用いた「逆浸透膜」が大きくものをいうことになりそうです。
「7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに」というゴールがありますが、そのためには原子力にどう向き合うかが問われます。福島やもんじゅの例もありますが、廃棄物処理についての答えも出ていません。高いコストとリスクをどうするべきなのか。科学技術にとって大きな課題だと岸氏は考えています。
STIがどうSDGsに寄与するかは産官学のほぼあらゆる分野から注目され、実施段階に移ろうとしています。その一方で、情報革命とマテリアル革命が刻々と進んでいるのが日本の現状です。
「ゼロエミッション」の実現と、知の構造化
このようななか、岸氏が今後の課題としているのは、リサイクルの徹底で廃棄物をゼロにする「ゼロエミッション」。それに伴う循環社会デザインの一部として、高機能・多機能な材料開発を考えています。そのためにも、計算化学や情報工学を導入したマテリアルズインテグレーションにより、材料の組織や特性、性能を予測していくことは必須になり、やがて来るマテリアル革命につながるでしょう。
研究システムも従来のような単位ではなく、国際的な産学連携を視野に入れたパートナーシップが必要になります。そのためにもSDGsは大きな指針を与えてくれます。
バラバラになりがちなSDGsに、東京大学第28代総長の小宮山宏氏が提唱する「プラチナ社会」的な知の構造化を用いて、STI for SDGsの構造化を進めること。最重要課題に向けて、岸氏の目標は定まっているようです。
人気の講義ランキングTOP20










