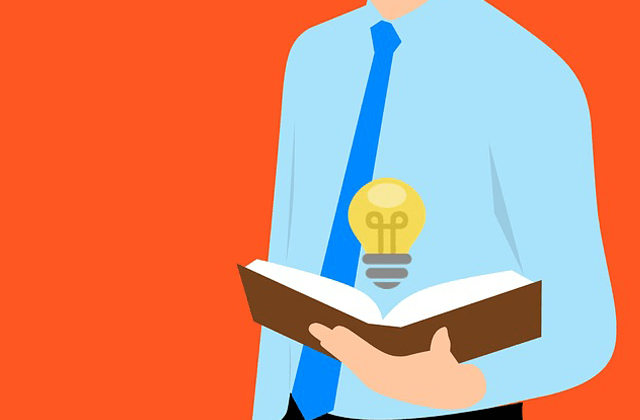
説明が「下手な人」と「うまい人」の違いは?
会議やプレゼン、報告や相談など、ビジネスの場では毎日のように「説明」する機会があります。自分は説明するのが苦手だ、下手だと感じている人もいると思いますが、「説明」は避けては通れないビジネススキルのひとつであり、必須のコミュニケーション。説明上手に越したことはありません。
そこで今回は、説明が「うまい人」と「下手な人」の特徴を社会人の男女30人にアンケート。その決定的な違いが出てしまうポイントを分析してみました。
たとえばメールマガジンが届いた時、そのタイトルやキャッチコピーに興味を感じれば開封して読むように、説明を聞く相手に「聞こう」という姿勢を取らせるツカミを用意できる人は説明上手です。説明下手な人は何の話か相手が分からないまま説明を始めてしまったり、ただ時系列で内容を並列させて話しがち。「ここテストに出ます!」と先に言われれば授業を熱心に聞いたという経験が皆さんにもあるのでは?説明は自分のためではなく、相手のためにすること。相手が「その先も聞きたい!」と興味を感じ真剣に耳を傾けたくなる言葉を初めに伝えることが必要です。
2:相手によって説明の仕方を変えているか
同じ内容を伝えるにも説明の仕方はひとつではなく、相手の性別や年齢、立場や知識レベルなどを考えて、説明方法を変えられるのが説明のうまい人。たとえば機械に強い人になら商品スペックなどを力説するのが効果的でも、詳しくない人には「以前と比べて3倍速い」「年間いくら削減できる」など、そのスペックによって得られる具体的な数字が必要です。「新規顧客にマーケティング専門用語を使って説明し、偉そう、難しそうと思わせてしまう上司の話し方はまずい」など、相手に伝わりやすい方法を選択できないと説明下手と言われてしまいます。
3:大事なポイントを強調しているかどうか
「大事なことだから2度言います」という表現をSNSなどでよく見かけますが、他人に説明するにあたって重要な箇所は、少し大げさなくらいでも強調できるのが説明上手な人です。すべて同じトーンで説明してしまうと「で、結局何が言いたいの?」と受取られることもありますし、メリハリがないため大事なポイントがぼやけてしまいます。「プレゼンの上手い先輩が、ここからが重要です!とか、しつこいようですが大事なのはこれです!と言うと相手が前のめりで聞いてくれる様子を見て、自分も見倣っている」という方も。大事なポイントは繰り返し伝えるテクニックは真似したいですね。
4:何のための説明なのか目的が伝わっているか
自己紹介や自己アピールをする時に、ただ自分の出身校や資格、趣味などを伝えて終わりでは話も膨らまず、説明下手な人だと思われてしまいます。面接なら「特技は〇〇ですではなく、特技の〇〇を活かしてこんな仕事に貢献したい、と言う」、プレゼンなら「弊社のシステムはこんなのですと説明するのではなく、こんなシステムだから御社の課題や要望に応えられますと、目的や解決法を説明する」と、何のために説明しているのかということを見失わない話し方が大切だという声が多く聞かれました。説明には、目的地や着地点のようなオチが必要です。
5:必要な情報と不要な情報が整理できているか
「余すところなく伝えたい!」そんな思いが強いと、あれもこれも話さなきゃと盛り沢山になり、話が長く、情報過多になってしまうのは説明下手な人。説明上手な人は、大事な部分を引き立たせるためにも、不要な情報を削ぎ落して話すことができます。ネットショッピングをする時も、長々と作り手の想いや製品のストーリーを読まされるよりも、その製品の特徴やベネフィットが簡潔に記されている箇条書きのような商品説明の方が分かりやすく、購買意欲を高めることにも繋がります。相手にとって有益な情報を取捨選択することは、説明上手への近道になるのでは。
・相手の関心をひきつけるアクション
・相手の気持ちや状況を説明に反映する
・伝えるポイントを絞って強調する
なんとなく流れていたテレビショッピングについ夢中になってしまったり、百貨店などの実演販売員の見事な商品説明に聞き入ってしまった経験のある方なら分かると思いますが、説明のプロ達にも、上記の3つのポイントは必ず取り入れられている要素です。時に「もっと聞いていたい」と思ってしまうほど楽しく、スっと理解できる心地よさを感じることもあると思いますが、それは聞く側にストレスや余計な疑問や迷いを与えない説明の仕方だからなのではないでしょうか。自分がうまく説明することばかりに気を取られず、聞く側のことを考えた伝え方をすることが大切なのかもしれませんね。
そこで今回は、説明が「うまい人」と「下手な人」の特徴を社会人の男女30人にアンケート。その決定的な違いが出てしまうポイントを分析してみました。
ここが違った! 説明の「上手」と「下手」の分かれ目とは
1:説明に耳を傾けさせる「ツカミ」があるかたとえばメールマガジンが届いた時、そのタイトルやキャッチコピーに興味を感じれば開封して読むように、説明を聞く相手に「聞こう」という姿勢を取らせるツカミを用意できる人は説明上手です。説明下手な人は何の話か相手が分からないまま説明を始めてしまったり、ただ時系列で内容を並列させて話しがち。「ここテストに出ます!」と先に言われれば授業を熱心に聞いたという経験が皆さんにもあるのでは?説明は自分のためではなく、相手のためにすること。相手が「その先も聞きたい!」と興味を感じ真剣に耳を傾けたくなる言葉を初めに伝えることが必要です。
2:相手によって説明の仕方を変えているか
同じ内容を伝えるにも説明の仕方はひとつではなく、相手の性別や年齢、立場や知識レベルなどを考えて、説明方法を変えられるのが説明のうまい人。たとえば機械に強い人になら商品スペックなどを力説するのが効果的でも、詳しくない人には「以前と比べて3倍速い」「年間いくら削減できる」など、そのスペックによって得られる具体的な数字が必要です。「新規顧客にマーケティング専門用語を使って説明し、偉そう、難しそうと思わせてしまう上司の話し方はまずい」など、相手に伝わりやすい方法を選択できないと説明下手と言われてしまいます。
3:大事なポイントを強調しているかどうか
「大事なことだから2度言います」という表現をSNSなどでよく見かけますが、他人に説明するにあたって重要な箇所は、少し大げさなくらいでも強調できるのが説明上手な人です。すべて同じトーンで説明してしまうと「で、結局何が言いたいの?」と受取られることもありますし、メリハリがないため大事なポイントがぼやけてしまいます。「プレゼンの上手い先輩が、ここからが重要です!とか、しつこいようですが大事なのはこれです!と言うと相手が前のめりで聞いてくれる様子を見て、自分も見倣っている」という方も。大事なポイントは繰り返し伝えるテクニックは真似したいですね。
4:何のための説明なのか目的が伝わっているか
自己紹介や自己アピールをする時に、ただ自分の出身校や資格、趣味などを伝えて終わりでは話も膨らまず、説明下手な人だと思われてしまいます。面接なら「特技は〇〇ですではなく、特技の〇〇を活かしてこんな仕事に貢献したい、と言う」、プレゼンなら「弊社のシステムはこんなのですと説明するのではなく、こんなシステムだから御社の課題や要望に応えられますと、目的や解決法を説明する」と、何のために説明しているのかということを見失わない話し方が大切だという声が多く聞かれました。説明には、目的地や着地点のようなオチが必要です。
5:必要な情報と不要な情報が整理できているか
「余すところなく伝えたい!」そんな思いが強いと、あれもこれも話さなきゃと盛り沢山になり、話が長く、情報過多になってしまうのは説明下手な人。説明上手な人は、大事な部分を引き立たせるためにも、不要な情報を削ぎ落して話すことができます。ネットショッピングをする時も、長々と作り手の想いや製品のストーリーを読まされるよりも、その製品の特徴やベネフィットが簡潔に記されている箇条書きのような商品説明の方が分かりやすく、購買意欲を高めることにも繋がります。相手にとって有益な情報を取捨選択することは、説明上手への近道になるのでは。
説明する時に大事なのは、聞き手の立場になること
いかがでしたか?今回のアンケートでは、説明上手と説明下手の「差」が出るさまざまなポイントが挙げられましたが、説明がうまい人が意識して実践していることは以下の3つにまとめられるのではないでしょうか。・相手の関心をひきつけるアクション
・相手の気持ちや状況を説明に反映する
・伝えるポイントを絞って強調する
なんとなく流れていたテレビショッピングについ夢中になってしまったり、百貨店などの実演販売員の見事な商品説明に聞き入ってしまった経験のある方なら分かると思いますが、説明のプロ達にも、上記の3つのポイントは必ず取り入れられている要素です。時に「もっと聞いていたい」と思ってしまうほど楽しく、スっと理解できる心地よさを感じることもあると思いますが、それは聞く側にストレスや余計な疑問や迷いを与えない説明の仕方だからなのではないでしょうか。自分がうまく説明することばかりに気を取られず、聞く側のことを考えた伝え方をすることが大切なのかもしれませんね。
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子
私たちにはなぜ宗教が必要だったのか…脳の働きから考える
長谷川眞理子







