テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
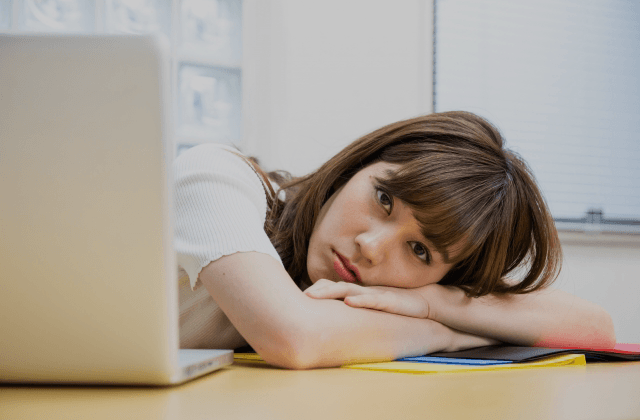
「雰囲気の悪い職場」にありがちな特徴とは?
多くのビジネスパーソンにとって、長時間を過ごすことになる職場にまず求めることは、「雰囲気の良さ」ではないでしょうか。
しかし、「雰囲気」は「その場やそこにいる人たちが自然に作り出している気分」を意味し、目に見えるものでも、具体的に取り上げられるものでもありません。その上昨今は、どちらかといえば「雰囲気の悪い職場」が増加しているように感じられます。
そこで今回は、「雰囲気の悪い職場」にありがちな特徴を取り上げながら、「雰囲気の良い職場」への改善策を考察してみたいと思います。
1)成果主義の反動で、全社員みな競争相手
多くの企業で導入された成果主義は、実績や結果でしか評価しない“プロセスを問わない職場”を作り上げてしまった。その結果、“同じ職場に勤務していても競争相手”といっても過言でない状況に陥っている。
2)わかり合えない世代間ギャップ
団塊・バブル・ロスジェネ・ゆとりなど、多くの職場では様々な世代が働いている。本来なら“世代間ギャップ”を認識・理解し合う必要があり、そのための時間や教育なども必要となる。しかしその余裕も持てないまま、相容れない関係となっている。
3)仕事のスピード化・効率化で中間管理職が消失
スピード化や効率化が過剰に求められる現代社会で、職場ではその傾向がさらに強まる。結果として過密スケジュールとなり、徹底した分業が行われることになる。しかし、どれだけ分業化されても仕事と仕事の間には“つなぎ目”があり中間管理職が担う必要があるが、その役割が果たせなくなっている。
4)ゴールの見えない競争を強いられる
1)・3)によって、一つの仕事が終わってもすぐに次の仕事が待っているという状態が延々と繰り返される、“仕事のゴールが見えなくなる”という弊害も発生。達成感を味わうことなく、疲労が解消されないまま、息苦しくても仕事をし続けることが強要されてしまう。
5)一方的に通告するメールで、コミュニケーション不足
便利である一方、双方向性に乏しいメールというツールの普及により、対面や電話などの双方向性の連絡を取る必要が減り、コミュニケーション不足の状態が慢性化するようになった。また、便利な分過剰にもなりやすいメールによる弊害も、併発・多発している。
6)管理・人材育成のコスト削減で管理職不在に
多くの職場がコスト削減に躍起となり、管理と人材育成に関わるコストも大幅に削減された。その結果、“部下の指導”“進捗状況のチェック”“相談に乗る”といった、本来の管理職の仕事をできる人材が不在となった。
7)目立つ人材ほど切られる大量リストラや人員施策
目立つ人材こそ、いわゆる「失われた10年」間の大量リストラでの対象者となりやすかった。そして、職場の仲間が簡単に切られた現実は、職場に残った人にも深い傷を残した。結果として、目立たず無難でいることが何よりの処世術となり、職場での人間関係も希薄となった。
8)協力より自らのスキルを磨く「プロ化」が加速
1)・3)・6)・7)のような状況が進むにつれ、終身雇用制度の崩壊と転職が他人事ではないムードが醸成され、職場での協力よりも、会社員であっても個々人で資格取得や技術向上を図る「プロ化」が加速。さらに分業化や細分化も極まり、専門外の仕事には関わらない・関われない状況となっている。
9)変わる風土がないのに、強引に進めた過去の改革
1)~8)のような雰囲気の悪い状況であるのに十分なアセスメントや対策案もない、つまりは変わる風土がないままに強引にトップダウンで改善や改革を進めた結果、状況が悪化。不信感をつのらせ、さらに職場の雰囲気を悪くする負のスパイラルに陥っている。
10)仕組み作りが先行し、運用できていない
1)~9)までを反省し様々な仕組みや制度を取り入れても、職場の実情にあっていない借り物の仕組みや制度だけが先行する形となって、運用できない結果となっている。
まず『他者と働く』の冒頭で宇田川氏は、ハーバード大学の名物教授ロナルド・ハイフェッツの定義を援用し、既存の知識・方法で解決できる「技術的問題」と、既存の知識・方法で解決できる「適応課題」があること。そのうち、職場で起きる問題のほとんどが、後者の「適応課題」であると紹介。
そして「適応課題」には4タイプ、1)「ギャップ型」:大切にしている「価値観」と実際の「行動」にギャップが生じるケース、2)「対立型」:互いの「コミットメント」が対立するケース、3)「抑圧型」:「言いにくいことを言わない」ケース、4)「回避型」:痛みや恐れを伴う本質的な問題を回避するために、逃げたり別の行動にすり替えたりするケースがあること。
さらに、「適応課題」が見出されたときこそ当人が関係性を改める必要が生じていると考え、まずは相手を変えようとするのではなく、こちら側から「ナラティヴ」を変える必要がある、と説きます。
なお、「ナラティヴ」とは物語ですが、いわゆる起承転結のストーリーとは少し違い、ビジネス上で狭義すると「立場・役割・専門性などによって生まれる“解釈の枠組み”」といえます。
宇田川氏は、「ポイントは、どちらかのナラティヴが正しいということではなく、それぞれの立場におけるナラティヴがあるということです。つまり、ナラティヴとは、視点の違いにとどまらず、その人たちが置かれている環境における“一般常識”のようなものなのです」と述べています。
その上で、「こちらのナラティヴとあちらのナラティヴに溝があることを見つけて、言わば“溝に橋を架けていくこと”が対話」であると提言。
そうして、「対話」とは「一言で言うと“新しい関係性を構築すること”(ただし、いきなりわかり合おうとすることではない)」で、かつ「権限や立場と関係なく誰にでも、自分の中に相手を見出すこと、相手の中に自分を見出すことで、双方向にお互いを受け入れ合っていくことを意味」するとしています。
ただし、1)負担になるレベルの親切は避ける、2)親切は自分でコントロールする、3)嫌な時は断る力も必要とし、「親切にしたい時は必ず自主的に自分から行なってください」とまとめています。
以上のように見ていくと、「雰囲気」という実体のないものであっても、実例に落とし込み具体的に分析していけば、原因や特徴が見えてくる確率が上がったり対処できる可能性が増えたりすることがわかります。
「雰囲気の悪い職場」は良い仕事ができないだけではなく、働き手である自身や仲間達のメンタルにも多大な悪影響を及ぼし、なによりも人生にもダメージを与えます。そうならないためにも、あくまでも自主性を保ちつつ、ささやかでも具体的な対話や親切を心がけ、実践することが望まれます。
しかし、「雰囲気」は「その場やそこにいる人たちが自然に作り出している気分」を意味し、目に見えるものでも、具体的に取り上げられるものでもありません。その上昨今は、どちらかといえば「雰囲気の悪い職場」が増加しているように感じられます。
そこで今回は、「雰囲気の悪い職場」にありがちな特徴を取り上げながら、「雰囲気の良い職場」への改善策を考察してみたいと思います。
ここがダメ!「雰囲気の悪い職場」の10大特徴
まずは、コンサルタントの手塚利男氏が『ギスギスした職場はなぜ変わらないのか』で取り上げた“ギスギスした職場・10の原因”に照らし合わせて、「雰囲気の悪い職場」の10大特徴を見ていきましょう。1)成果主義の反動で、全社員みな競争相手
多くの企業で導入された成果主義は、実績や結果でしか評価しない“プロセスを問わない職場”を作り上げてしまった。その結果、“同じ職場に勤務していても競争相手”といっても過言でない状況に陥っている。
2)わかり合えない世代間ギャップ
団塊・バブル・ロスジェネ・ゆとりなど、多くの職場では様々な世代が働いている。本来なら“世代間ギャップ”を認識・理解し合う必要があり、そのための時間や教育なども必要となる。しかしその余裕も持てないまま、相容れない関係となっている。
3)仕事のスピード化・効率化で中間管理職が消失
スピード化や効率化が過剰に求められる現代社会で、職場ではその傾向がさらに強まる。結果として過密スケジュールとなり、徹底した分業が行われることになる。しかし、どれだけ分業化されても仕事と仕事の間には“つなぎ目”があり中間管理職が担う必要があるが、その役割が果たせなくなっている。
4)ゴールの見えない競争を強いられる
1)・3)によって、一つの仕事が終わってもすぐに次の仕事が待っているという状態が延々と繰り返される、“仕事のゴールが見えなくなる”という弊害も発生。達成感を味わうことなく、疲労が解消されないまま、息苦しくても仕事をし続けることが強要されてしまう。
5)一方的に通告するメールで、コミュニケーション不足
便利である一方、双方向性に乏しいメールというツールの普及により、対面や電話などの双方向性の連絡を取る必要が減り、コミュニケーション不足の状態が慢性化するようになった。また、便利な分過剰にもなりやすいメールによる弊害も、併発・多発している。
6)管理・人材育成のコスト削減で管理職不在に
多くの職場がコスト削減に躍起となり、管理と人材育成に関わるコストも大幅に削減された。その結果、“部下の指導”“進捗状況のチェック”“相談に乗る”といった、本来の管理職の仕事をできる人材が不在となった。
7)目立つ人材ほど切られる大量リストラや人員施策
目立つ人材こそ、いわゆる「失われた10年」間の大量リストラでの対象者となりやすかった。そして、職場の仲間が簡単に切られた現実は、職場に残った人にも深い傷を残した。結果として、目立たず無難でいることが何よりの処世術となり、職場での人間関係も希薄となった。
8)協力より自らのスキルを磨く「プロ化」が加速
1)・3)・6)・7)のような状況が進むにつれ、終身雇用制度の崩壊と転職が他人事ではないムードが醸成され、職場での協力よりも、会社員であっても個々人で資格取得や技術向上を図る「プロ化」が加速。さらに分業化や細分化も極まり、専門外の仕事には関わらない・関われない状況となっている。
9)変わる風土がないのに、強引に進めた過去の改革
1)~8)のような雰囲気の悪い状況であるのに十分なアセスメントや対策案もない、つまりは変わる風土がないままに強引にトップダウンで改善や改革を進めた結果、状況が悪化。不信感をつのらせ、さらに職場の雰囲気を悪くする負のスパイラルに陥っている。
10)仕組み作りが先行し、運用できていない
1)~9)までを反省し様々な仕組みや制度を取り入れても、職場の実情にあっていない借り物の仕組みや制度だけが先行する形となって、運用できない結果となっている。
「対話(dialogue)」と「ナラティヴ(narrative)」
では、以上のような「雰囲気の悪い職場」となった場合、どのように改善していけばよいのでしょうか。経営学者で埼玉大学経済経営系大学院准教授の宇田川元一氏は『他者と働く』で、職場での問題を解くための手法として、「ナラティヴ(narrative)」に根ざした深い「対話(dialogue)」を推奨しています。まず『他者と働く』の冒頭で宇田川氏は、ハーバード大学の名物教授ロナルド・ハイフェッツの定義を援用し、既存の知識・方法で解決できる「技術的問題」と、既存の知識・方法で解決できる「適応課題」があること。そのうち、職場で起きる問題のほとんどが、後者の「適応課題」であると紹介。
そして「適応課題」には4タイプ、1)「ギャップ型」:大切にしている「価値観」と実際の「行動」にギャップが生じるケース、2)「対立型」:互いの「コミットメント」が対立するケース、3)「抑圧型」:「言いにくいことを言わない」ケース、4)「回避型」:痛みや恐れを伴う本質的な問題を回避するために、逃げたり別の行動にすり替えたりするケースがあること。
さらに、「適応課題」が見出されたときこそ当人が関係性を改める必要が生じていると考え、まずは相手を変えようとするのではなく、こちら側から「ナラティヴ」を変える必要がある、と説きます。
なお、「ナラティヴ」とは物語ですが、いわゆる起承転結のストーリーとは少し違い、ビジネス上で狭義すると「立場・役割・専門性などによって生まれる“解釈の枠組み”」といえます。
宇田川氏は、「ポイントは、どちらかのナラティヴが正しいということではなく、それぞれの立場におけるナラティヴがあるということです。つまり、ナラティヴとは、視点の違いにとどまらず、その人たちが置かれている環境における“一般常識”のようなものなのです」と述べています。
その上で、「こちらのナラティヴとあちらのナラティヴに溝があることを見つけて、言わば“溝に橋を架けていくこと”が対話」であると提言。
そうして、「対話」とは「一言で言うと“新しい関係性を構築すること”(ただし、いきなりわかり合おうとすることではない)」で、かつ「権限や立場と関係なく誰にでも、自分の中に相手を見出すこと、相手の中に自分を見出すことで、双方向にお互いを受け入れ合っていくことを意味」するとしています。
嫌な同僚にも親切に?自主コントロールの重要性
また、メンタリストのDaiGo氏は、「心理学的に働きやすい職場に変える方法」として、第一に「嫌な同僚にも親切にしまくろう」と断言。さらに実験結果を紹介し、「親切にした側も親切にされた側もオートノミー(自主性・自律性)というものがアップ」「親切にした人は自分自身に対して心理的なメリットがあるので、親切は人の為ではなく、さらには組織を変えてしまうもの」と述べています。ただし、1)負担になるレベルの親切は避ける、2)親切は自分でコントロールする、3)嫌な時は断る力も必要とし、「親切にしたい時は必ず自主的に自分から行なってください」とまとめています。
以上のように見ていくと、「雰囲気」という実体のないものであっても、実例に落とし込み具体的に分析していけば、原因や特徴が見えてくる確率が上がったり対処できる可能性が増えたりすることがわかります。
「雰囲気の悪い職場」は良い仕事ができないだけではなく、働き手である自身や仲間達のメンタルにも多大な悪影響を及ぼし、なによりも人生にもダメージを与えます。そうならないためにも、あくまでも自主性を保ちつつ、ささやかでも具体的な対話や親切を心がけ、実践することが望まれます。
<参考文献・参考サイト>
・「雰囲気」、『デジタル大辞泉』(小学館)
・『ギスギスした職場はなぜ変わらないのか』(手塚利男著、ナナ・コーポレート・コミュニケーション)
・『他者と働く』(宇田川元一著、ニューズピックス)
・今の職場を4週間で働きやすく変える心理テク
https://daigoblog.jp/prepare-workplace/
・「雰囲気」、『デジタル大辞泉』(小学館)
・『ギスギスした職場はなぜ変わらないのか』(手塚利男著、ナナ・コーポレート・コミュニケーション)
・『他者と働く』(宇田川元一著、ニューズピックス)
・今の職場を4週間で働きやすく変える心理テク
https://daigoblog.jp/prepare-workplace/
人気の講義ランキングTOP20










