テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
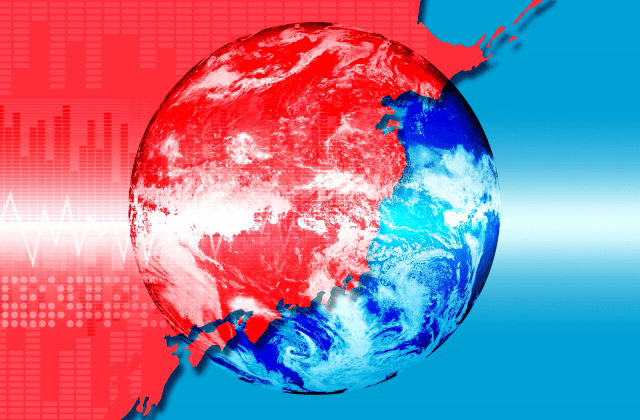
ランキングでみる 「テクノロジー後進国」日本
AI(人工知能)、ICT(情報伝達技術)、IoT(モノのインターネット)、キャッシュレス化といったデジタルテクノロジー関係のワードを目にしない日はありません。世の中はここ数年で急速にデジタル化してきました。しかし、デジタルテクノロジーに関するいくつかの国際比較資料を見ると、日本が他国に比べてかなり遅れていることが分かります。「日本は先進国」という認識は、もう過去の話なのかもしれません。ということで、ここでは日本を取り巻くデジタル化の現状を見てみましょう。
また教育分野で見ると、ICTスキルが必要な教員の割合が日本ではおよそ80%です。これはデータがある32カ国中では上から2番目の高さで、全体平均は約58%。教育現場においても日本が大きく出遅れていることが分かります。日本経済新聞によると、欧米では初等教育の段階からプログラミングを授業に取り入れるなど、デジタル人材の育成強化に向けて社会全体で取り組んでいるとのこと。日本でも2020年度から全国の小学校でもプログラミング教育が必修となりますが、どのように授業を組み立てるか、教える人材をどうするか、まだ課題は山積みのようです。
これによると「デジタルへの取り組みが進んでいない」と答えた国は、比率が高い順に、1位日本、2位デンマーク、3位フランス、4位ベルギー、5位シンガポールです。ここでも日本の立ち遅れが目立っています。また要因として上がったのは「予算およびリソース不足」が42%で最も多く、次が「組織内のスキルおよびノウハウの不足」31%となっています。次いで「一貫したデジタル戦略とビジョンの不足」(24%)と続いています。「予算、スキル、ビジョン」はプロジェクトの最初の山場かもしれません。このあたり、企業が変化のスピードに追いついていないことを意味していると言えるでしょう。
1位は人材が豊富なインドの78%で、2位は中国で77%、3位はアラブ首長国連邦(UAE)で66%と続きます。ここでの日本は29%で最下位です。また全体の回答者のうち82%が、マネージャーよりもロボットの方が物事をうまくこなすと考えています。優れていると回答されたポイントには、作業スケジュールの維持(34%)、問題解決(29%)、予算管理(26%)、偏見のない情報の提供(26%)といった項目があります。
ここから分かるのは、「管理」や「論理的解決」といったある種の「正確さ」が必要とされる判断に関しては、AIの方が信頼できる場面が多いということです。また日本はマネージャーよりもロボットを信頼するとしている割合が76%で、10カ国平均である64%を上回っています。つまり、日本ではAIに対する期待や必要性が高まっているにもかかわらず、実際の運用が進んでいない実態が見えていると言えるでしょう。
ただし、OECDの報告書では、日本はデジタル化に対応できる「大きな潜在力がある」とも指摘されているようです。これは日本の教育水準の高さが理由です。日本は、「学力の低い学生」の割合が5.6%、「デジタル技能が低い高齢層」が8.5%で加盟国の中では低い数値です。つまり、いまのうちに国がうまく舵を切れば、こういった分野への対応も可能だということを意味しているのかもしれません。この先、人口減と少子高齢化が進み、生産年齢人口は著しく減っていきます。日本はテクノロジー分野で巻き返すためにも、まずは早急に社会人・学生・生徒・児童を問わずICT教育に投資する必要があることが分かります。
日本のICT教育は不十分
日本経済新聞の記事では、経済協力開発機構(OECD)による報告書「スキル・アウトルック2019」のデータから、特に就労者の技能訓練の項目について取り上げられています。これによると、日本において、オンライン講座などで技能向上に取り組んでいる人の比率は36.6%です。これに対して、OECD加盟36カ国平均は42%。日本は平均を下回っており、日本における就労者の技能訓練は遅れていることが分かります。また教育分野で見ると、ICTスキルが必要な教員の割合が日本ではおよそ80%です。これはデータがある32カ国中では上から2番目の高さで、全体平均は約58%。教育現場においても日本が大きく出遅れていることが分かります。日本経済新聞によると、欧米では初等教育の段階からプログラミングを授業に取り入れるなど、デジタル人材の育成強化に向けて社会全体で取り組んでいるとのこと。日本でも2020年度から全国の小学校でもプログラミング教育が必修となりますが、どのように授業を組み立てるか、教える人材をどうするか、まだ課題は山積みのようです。
「予算」「リソース」「スキル」「ノウハウ」「ビジョン」が足りない
一方、デルテクノロジーズは、世界42の国と地域の企業に対して「企業のデジタルトランスフォーメーションの進捗状況に関するアンケート調査」を行っています。これによると「デジタルへの取り組みが進んでいない」と答えた国は、比率が高い順に、1位日本、2位デンマーク、3位フランス、4位ベルギー、5位シンガポールです。ここでも日本の立ち遅れが目立っています。また要因として上がったのは「予算およびリソース不足」が42%で最も多く、次が「組織内のスキルおよびノウハウの不足」31%となっています。次いで「一貫したデジタル戦略とビジョンの不足」(24%)と続いています。「予算、スキル、ビジョン」はプロジェクトの最初の山場かもしれません。このあたり、企業が変化のスピードに追いついていないことを意味していると言えるでしょう。
AIに対する期待は高まっている
2019年のオラクルの調査(対象:世界10カ国の従業員、マネージャー、人事部門リーダー合計8,370名)では、職場でのAIの利用率が国別に発表されています。1位は人材が豊富なインドの78%で、2位は中国で77%、3位はアラブ首長国連邦(UAE)で66%と続きます。ここでの日本は29%で最下位です。また全体の回答者のうち82%が、マネージャーよりもロボットの方が物事をうまくこなすと考えています。優れていると回答されたポイントには、作業スケジュールの維持(34%)、問題解決(29%)、予算管理(26%)、偏見のない情報の提供(26%)といった項目があります。
ここから分かるのは、「管理」や「論理的解決」といったある種の「正確さ」が必要とされる判断に関しては、AIの方が信頼できる場面が多いということです。また日本はマネージャーよりもロボットを信頼するとしている割合が76%で、10カ国平均である64%を上回っています。つまり、日本ではAIに対する期待や必要性が高まっているにもかかわらず、実際の運用が進んでいない実態が見えていると言えるでしょう。
日本は「テクノロジー後進国」だが潜在力がある
現状で「テクノロジー後進国」となっている日本では、合理的解決が可能な問題に対する対応が他国に比べて遅いのかもしれません。またこの状態は、教育現場での対応が遅れていることもあり、今後すぐには解決しないでしょう。こうなると企業でもスキルやノウハウが蓄積されません。わたしたちが行えるのは、企業内で早急に教育・研修体制を充実させるか、他国から改革意識のある有能な管理職級の人材を採用することです。しかし、このためには、予算とリソースが必要であることは言うまでもありません。ここにさらなる壁が立ちはだかっています。ただし、OECDの報告書では、日本はデジタル化に対応できる「大きな潜在力がある」とも指摘されているようです。これは日本の教育水準の高さが理由です。日本は、「学力の低い学生」の割合が5.6%、「デジタル技能が低い高齢層」が8.5%で加盟国の中では低い数値です。つまり、いまのうちに国がうまく舵を切れば、こういった分野への対応も可能だということを意味しているのかもしれません。この先、人口減と少子高齢化が進み、生産年齢人口は著しく減っていきます。日本はテクノロジー分野で巻き返すためにも、まずは早急に社会人・学生・生徒・児童を問わずICT教育に投資する必要があることが分かります。
<参考サイト>
・日本の就労世代、デジタル技能の訓練不足 OECD報告書|日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44581860Z00C19A5EE8000/
・「職場におけるAI」調査:回答者の64%はマネージャーよりもロボットを信頼|日本Oracle
https://www.oracle.com/jp/corporate/pressrelease/jp20191016.html
・OECD Skills Outlook 2019|OECD
http://www.oecd.org/skills/oecd-skills-outlook-2019-df80bc12-en.htm
・日本の就労世代、デジタル技能の訓練不足 OECD報告書|日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44581860Z00C19A5EE8000/
・「職場におけるAI」調査:回答者の64%はマネージャーよりもロボットを信頼|日本Oracle
https://www.oracle.com/jp/corporate/pressrelease/jp20191016.html
・OECD Skills Outlook 2019|OECD
http://www.oecd.org/skills/oecd-skills-outlook-2019-df80bc12-en.htm
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子










