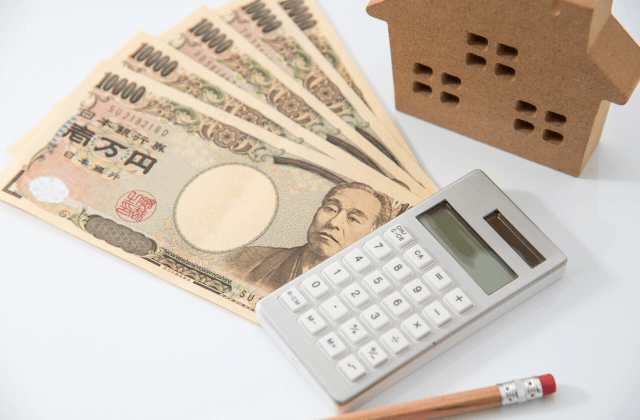
年収に見合った「家賃」はいくらなのか?
生活する上で最も大きな固定費といえば、家賃ではないでしょうか。昔はおよそ収入の3割(33%程度)が目処とされてきました。しかし、これはもはや昔の話。現在はもう少しシビアになっている様子です。ここでは、実際どれくらいが妥当なのか、年収別に見てみましょう。
現代では以前に比べてさまざまな働き方が選べるようになったと同時に、年功賃金制といった時間に任せれば給与が上がる仕組みは期待できません。雇用が維持される保証もないという状況も増えています。つまり、私たちは以前よりもリスクの高い社会に生きています。この社会ではリスクに備えて一定額を蓄えておく必要があります。
また今後、老後資金を年金だけでは賄えないことも明らかです。この点でもお金を蓄えておく必要性があります。しかし、現在では貯蓄しておくだけではお金は増えません。ゆとりを得るにはある程度を投資に回す必要もあります。国もiDeCoやNISAといった貯蓄を投資にシフトする方策を積極的に広めていますが、貯蓄を全額投資に回すのは危険です。投資にお金を回すには、ある程度の貯蓄があることを前提としなければなりません。つまり、一定額の貯蓄の上に老後資金としての投資が必要です。
さらに以前よりも消費税は上がっています。また、細かく考えればインターネットやスマホは、現在ではなくてはならない社会インフラです。これを維持するのにも毎月1万円程度は必要です。このように考えれば、2000年代以前よりも、現代では固定費が増え、自分の自由に使えるお金は減っていると考えられます。この時、一番に見直されるべき固定費は家賃です。
<年収(月割り額)20%:25%:30%>
200万円(約16.7万円/月):3.3万円:4.2万円:5.0万円
300万円(約25万円/月):5万円:6.3万円:7.5万円
400万円(約33.3万円/月):6.7万円:8.3万円:10万円
500万円(約41.7万円/月):8.3万円:10.4万円:12.5万円
600万円(約50万円/月):10万円:12.5万円:15万円
700万円(約58.3万円/月):11.7万円:14.6万円:17.5万円
800万円(約66.7万円/月):13.3万円:16.7万円:20.0万円
もちろん、一人で暮らすか、夫婦で暮らすか、また子供がいるかどうか、福利厚生の充実した会社勤めかフリーランスかといった様々な状況によって、家賃にあてることのできる金額は大きく変わります。しかし、節約できれば大きな違いが生まれることは確かです。例えば年収500万円の場合をとりだしてみましょう。30%だった場合の家賃は12.5万円、これが20%だった場合は8.3万円となります。つまり、毎月4.2万円の差が生まれるのです。これは見過ごせない金額だと言えます。
収入が少ないほどこういった固定費がシビアになることは想像に難くありません。また、夫婦2人の世帯でまだ子供がいない場合、貯蓄は手取りの20%が目安といった記事もあります。節約や貯金は習慣づけが大事です。一概に「家賃は収入の何割」と言えない部分はありますが、固定費に対する意識を持っておけば、あとで生き方に余裕が生まれることは間違いないでしょう。
収入の20%から30%程度が目安
最近は一般的に家賃の目安は20から30%とされることが多いようです。3割ということが言われていた時代は、日本の経済が上向いていくという予想がされていた時代です。つまり、未来の自分や国のお金に託せる時代の考えだったと言えるでしょう。しかし、現代の様相は異なります。現代では以前に比べてさまざまな働き方が選べるようになったと同時に、年功賃金制といった時間に任せれば給与が上がる仕組みは期待できません。雇用が維持される保証もないという状況も増えています。つまり、私たちは以前よりもリスクの高い社会に生きています。この社会ではリスクに備えて一定額を蓄えておく必要があります。
また今後、老後資金を年金だけでは賄えないことも明らかです。この点でもお金を蓄えておく必要性があります。しかし、現在では貯蓄しておくだけではお金は増えません。ゆとりを得るにはある程度を投資に回す必要もあります。国もiDeCoやNISAといった貯蓄を投資にシフトする方策を積極的に広めていますが、貯蓄を全額投資に回すのは危険です。投資にお金を回すには、ある程度の貯蓄があることを前提としなければなりません。つまり、一定額の貯蓄の上に老後資金としての投資が必要です。
さらに以前よりも消費税は上がっています。また、細かく考えればインターネットやスマホは、現在ではなくてはならない社会インフラです。これを維持するのにも毎月1万円程度は必要です。このように考えれば、2000年代以前よりも、現代では固定費が増え、自分の自由に使えるお金は減っていると考えられます。この時、一番に見直されるべき固定費は家賃です。
年収別の家賃シミュレーション
実際に年収別にシミューレーションしてみましょう。それぞれの年収で、月々20%、25%、30%でそれぞれおおよその金額を出してみます。<年収(月割り額)20%:25%:30%>
200万円(約16.7万円/月):3.3万円:4.2万円:5.0万円
300万円(約25万円/月):5万円:6.3万円:7.5万円
400万円(約33.3万円/月):6.7万円:8.3万円:10万円
500万円(約41.7万円/月):8.3万円:10.4万円:12.5万円
600万円(約50万円/月):10万円:12.5万円:15万円
700万円(約58.3万円/月):11.7万円:14.6万円:17.5万円
800万円(約66.7万円/月):13.3万円:16.7万円:20.0万円
もちろん、一人で暮らすか、夫婦で暮らすか、また子供がいるかどうか、福利厚生の充実した会社勤めかフリーランスかといった様々な状況によって、家賃にあてることのできる金額は大きく変わります。しかし、節約できれば大きな違いが生まれることは確かです。例えば年収500万円の場合をとりだしてみましょう。30%だった場合の家賃は12.5万円、これが20%だった場合は8.3万円となります。つまり、毎月4.2万円の差が生まれるのです。これは見過ごせない金額だと言えます。
収入が少ないほどこういった固定費がシビアになることは想像に難くありません。また、夫婦2人の世帯でまだ子供がいない場合、貯蓄は手取りの20%が目安といった記事もあります。節約や貯金は習慣づけが大事です。一概に「家賃は収入の何割」と言えない部分はありますが、固定費に対する意識を持っておけば、あとで生き方に余裕が生まれることは間違いないでしょう。
<参考サイト>
・これが「年収別適性家賃」|ライフルホームズ
https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00002/
・「家賃は収入の30%」は時代遅れ?手取りから逆算する"理想の家賃"をお金のプロが解説|オウチーノニュース
https://o-uccino.com/front/articles/55627
・夫婦の生活費の内訳はいくら?理想の割合や上手な分担方法も解説!|家計見直しナビ
https://www.kakeinavi.jp/559/
・これが「年収別適性家賃」|ライフルホームズ
https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00002/
・「家賃は収入の30%」は時代遅れ?手取りから逆算する"理想の家賃"をお金のプロが解説|オウチーノニュース
https://o-uccino.com/front/articles/55627
・夫婦の生活費の内訳はいくら?理想の割合や上手な分担方法も解説!|家計見直しナビ
https://www.kakeinavi.jp/559/
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







