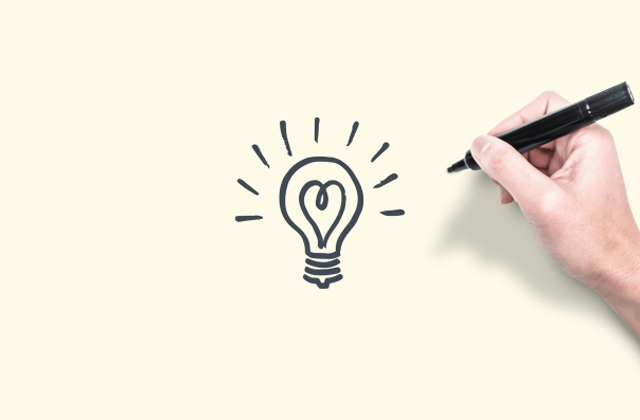
毎日が“たのしく”なる! まほうの「しかけ」とは?
日常にあふれるいろいろな問題を、“たのしく”変えてくれる「しかけ」があることをご存知でしょうか。
[問 題]書類の整理ができない
「しかけ」並べたファイルボックスの側面に斜めの線を引く
[解 決]直線になるように並べ替えたくなる
[問 題]運動不足なのについエレベーターを使ってしまう
「しかけ」階段をピアノに見立てて音がでるようにする
[解 決]階段を使ってピアノの音を鳴らしたくなる
[問 題]トイレをきれいに使ってほしい
「しかけ」トイレの中に的をつける
[解 決]的を狙いたくなる
大阪大学大学院経済学研究科教授で大阪大学シカケラボを主催する松村真宏(まつむら・なおひろ)先生の『しかけは世界を変える!! 毎日がたのしくなる!まほうのしかけ』(徳間書店)には、小学生から“たのしく”「しかけ」に取り組むための「仕掛学」の理論と実践が、網羅的かつわかりやすく書かれています。
この筒こそが、「動物以外のものも見てほしい」という動物園スタッフの「しかけ」であり、松村先生に初めて「しかけ」の可能性に気づかせてくれた「しかけ」となりました。
そこから、松村先生は“人に気づかせることが重要。そのために「しかけ」をデザインすればいい”というブレイクスルーを得ます。さらに「しかけ」の事例を集めていくうちに、松村先生の提唱する「仕掛学(しかけがく)」誕生へとつながっていきます。
[問 題]歩道沿いの自転車置き場が乱雑になる
「しかけ」白い線を引く
[解 決]線にそって自転車を停めたくなる
(1)公平性:誰も損をしていない
(2)誘因性:つい線にそって自転車を停めたくなる
(3)目的の二重性:「しかけ」を設置する人の目的(解決したい課題)は、自転車置き場の整理・「しかけ」を使う人の目的(行動理由)は、誘因性による行動の結果
考えてみると、いくら正論をいわれたとしても、人はなかなか行動に移せないのではないでしょうか。そして、行動に移せなかった結果、それが問題になったりすると、たのしくない日常を作り出してしまいます。
しかし、別のアプローチで“たのしく”誘ってくれる「しかけ」があれば、自主的に行動に移すことにつながります。それこそが「しかけ」の役割であり、「しかけ」の効用といえます。
しかしながら並行して、「しかけ」を“たのしく”活用することで自主的な行動へと変換することができ、ひいては私たち自身で問題を解決できるようになる、その可能性を、松村先生は本書を通して示してくれています。
ただ、ここでひとつ注意点ですが、「しかけ」にはよい「しかけ」だけではなく、悪い「しかけ」があることも意識しておくといいということです。とはいえ、その区別は簡単です。“しかけられる側”が“しかける側”目的を知ったときに、「素晴らしい、一本取られた!」と笑顔になるのがよい「しかけ」、逆に「だまされた!もう二度と引っかからない!!」と不快にさせるのは悪い「しかけ」です。
つまり、よい「しかけ」はネタバレしても問題なく、むしろワクワクするためネタを知っても人に伝えたくなります。反対に悪い「しかけ」は、うしろめたい気持ちがあってネタバレを避ける「しかけ」といえます。
これは、「しかけ」の定義の一つである“公平性”からも大切な観点です。「しかけ」を見つけたり作ったりする際に、必ず心がけてほしいと思います。
大切なことですので繰り返しますが、気づいた人を“たのしく”させる「しかけ」が私たちの世界にはたくさんあります。そして、その「しかけ」は、誰でも見つけることも作ることもできるのです。
日常のいろいろな問題で困っている方は、ぜひ「しかけ」の視点に立って、毎日を“たのしく”変えてみてください。そのためのヒントが、本書にあふれているのです。
[問 題]書類の整理ができない
「しかけ」並べたファイルボックスの側面に斜めの線を引く
[解 決]直線になるように並べ替えたくなる
[問 題]運動不足なのについエレベーターを使ってしまう
「しかけ」階段をピアノに見立てて音がでるようにする
[解 決]階段を使ってピアノの音を鳴らしたくなる
[問 題]トイレをきれいに使ってほしい
「しかけ」トイレの中に的をつける
[解 決]的を狙いたくなる
大阪大学大学院経済学研究科教授で大阪大学シカケラボを主催する松村真宏(まつむら・なおひろ)先生の『しかけは世界を変える!! 毎日がたのしくなる!まほうのしかけ』(徳間書店)には、小学生から“たのしく”「しかけ」に取り組むための「仕掛学」の理論と実践が、網羅的かつわかりやすく書かれています。
「しかけ」への気づき・「仕掛学」の誕生
さかのぼること2006年の夏、人工知能の研究を進めていた松村先生は、研究に行き詰まりを感じていたそうです。そこで、ぶらりと遊びに行った大阪市にある天王寺動物園の「アジアの熱帯雨林」エリアで、ふと通路脇に設置された望遠鏡のような筒に気がつきます。穴があいているだけでレンズも入っていない筒をのぞいてみると、筒の先にゾウのうんちの模型が見えました。この筒こそが、「動物以外のものも見てほしい」という動物園スタッフの「しかけ」であり、松村先生に初めて「しかけ」の可能性に気づかせてくれた「しかけ」となりました。
そこから、松村先生は“人に気づかせることが重要。そのために「しかけ」をデザインすればいい”というブレイクスルーを得ます。さらに「しかけ」の事例を集めていくうちに、松村先生の提唱する「仕掛学(しかけがく)」誕生へとつながっていきます。
「しかけ」の定義と効用
では「しかけ」とはなにか。より具体的にどのようなモノであり、またどのような効用があるのでしょか。松村先生は「しかけ」の定義として、(1)公平性(2)誘因性(3)目的の二重性――をもつモノとしています。次の「しかけ」を例に、それぞれの特徴を具体的に見てみましょう。[問 題]歩道沿いの自転車置き場が乱雑になる
「しかけ」白い線を引く
[解 決]線にそって自転車を停めたくなる
(1)公平性:誰も損をしていない
(2)誘因性:つい線にそって自転車を停めたくなる
(3)目的の二重性:「しかけ」を設置する人の目的(解決したい課題)は、自転車置き場の整理・「しかけ」を使う人の目的(行動理由)は、誘因性による行動の結果
考えてみると、いくら正論をいわれたとしても、人はなかなか行動に移せないのではないでしょうか。そして、行動に移せなかった結果、それが問題になったりすると、たのしくない日常を作り出してしまいます。
しかし、別のアプローチで“たのしく”誘ってくれる「しかけ」があれば、自主的に行動に移すことにつながります。それこそが「しかけ」の役割であり、「しかけ」の効用といえます。
よい「しかけ」と悪い「しかけ」の見分け方
以上のように見ていくと、世界は「しかけ」にあふれていることがわかってきます。そして、「しかけ」が必要な対象者は多岐にわたることも見えてきます。そのうえで、「私たちが直面する問題の多くは私たち自身の行動が作り出している」と、松村先生は説きます。しかしながら並行して、「しかけ」を“たのしく”活用することで自主的な行動へと変換することができ、ひいては私たち自身で問題を解決できるようになる、その可能性を、松村先生は本書を通して示してくれています。
ただ、ここでひとつ注意点ですが、「しかけ」にはよい「しかけ」だけではなく、悪い「しかけ」があることも意識しておくといいということです。とはいえ、その区別は簡単です。“しかけられる側”が“しかける側”目的を知ったときに、「素晴らしい、一本取られた!」と笑顔になるのがよい「しかけ」、逆に「だまされた!もう二度と引っかからない!!」と不快にさせるのは悪い「しかけ」です。
つまり、よい「しかけ」はネタバレしても問題なく、むしろワクワクするためネタを知っても人に伝えたくなります。反対に悪い「しかけ」は、うしろめたい気持ちがあってネタバレを避ける「しかけ」といえます。
これは、「しかけ」の定義の一つである“公平性”からも大切な観点です。「しかけ」を見つけたり作ったりする際に、必ず心がけてほしいと思います。
「しかけ」で私たちの毎日を“たのしく”変える一冊
いかがですか。“たのしい”「しかけ」の可能性を、感じていただけたでしょうか。大切なことですので繰り返しますが、気づいた人を“たのしく”させる「しかけ」が私たちの世界にはたくさんあります。そして、その「しかけ」は、誰でも見つけることも作ることもできるのです。
日常のいろいろな問題で困っている方は、ぜひ「しかけ」の視点に立って、毎日を“たのしく”変えてみてください。そのためのヒントが、本書にあふれているのです。
<参考文献>
『しかけは世界を変える!! 毎日がたのしくなる!まほうのしかけ』 (松村真宏著、徳間書店)
https://www.tokuma.jp/book/b493701.html
<参考サイト>
大阪大学シカケラボ
https://mtmr.jp/ja/
『しかけは世界を変える!! 毎日がたのしくなる!まほうのしかけ』 (松村真宏著、徳間書店)
https://www.tokuma.jp/book/b493701.html
<参考サイト>
大阪大学シカケラボ
https://mtmr.jp/ja/
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







