テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
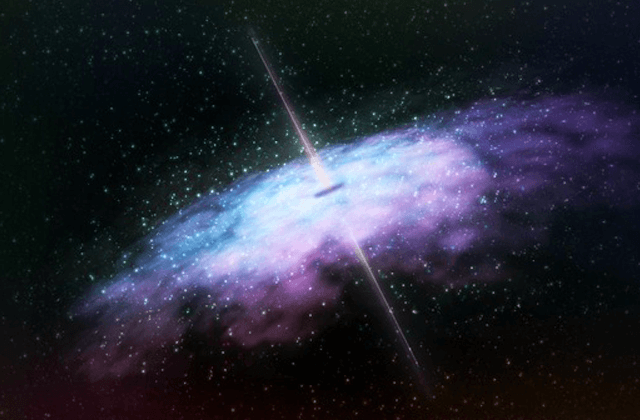
「裸の特異点」とは?未解決問題に挑む『宇宙検閲官仮説』
宇宙に詳しくない方でも「一般相対性理論」という言葉は聞いたことがあるでしょう。天才物理学者アルベルト・アインシュタインが発見した現代物理学の基礎となる考え方です。しかし、この一般相対性理論から導かれる解には、じつは大きな問題があることをご存じでしょうか。
それは、式のなかに「特異点」が含まれていること。特異点とは、この世界の物理法則を破綻させてしまう、「無限大」を導く点のことをいいます。そんな問題のある存在が宇宙には漂っているのでしょうか。そのようなものが存在するのなら、とても危険なのでは……。
今回取り上げるのは、その「特異点」にまつわる物理学の巨大な謎を解説する一冊、大阪工業大学情報科学部教授である真貝寿明先生の著書『宇宙検閲官仮説 「裸の特異点」は隠されるか』(ブルーバックス)です。
ブラックホールの姿が初めて写真に収められたのは2019年のことです。一昔前まで、ブラックホールは架空の存在として扱われてきました。一般相対性理論によってその存在が示唆されていましたが、アインシュタイン本人でさえ、その存在を否定していたほどでした。ところが、後世の学者たちによって「ブラックホールは実在する」ということがわかり、一般相対性理論の正しさが証明されるとともに、ブラックホールのなかには物理法則が破綻をきたす「特異点」があることがわかりました。
ブラックホールのなかに「特異点」が自然発生することを証明したのは、2020年にノーベル物理学賞を受賞したイギリスのロジャー・ペンローズ。彼の提唱する特異点の発生理論は「特異点定理」といわれています。しかし、ブラックホールは光さえも飲み込んでしまう超重力を持った天体です。いくら物理法則が破綻をきたす「特異点」といっても、ブラックホールが包み隠してくれているなら、地球に暮らす私たち生物に影響は出ないのかもしれません。
ところが、この「特異点定理」を突き詰めていくと、どうやら「ブラックホールの外側にも特異点が存在しているのでは」という事象が導き出されてしまうのです。
〈検閲官とは、公序良俗を乱すような「不適切な表現」が公衆の目にふれないように取り締まる役人のことですが、宇宙にもそのようなものが存在している(に違いない)という考えが「宇宙検閲官仮説」です〉
本書の冒頭で、真貝先生はこのように説明しています。本書は、あってはならないこの不適切な場所〈“裸の”特異点〉が本当に存在しているのか、そして存在しているとしたら、ペンローズが言うようにそれを検閲する存在があるのかどうか。そうした宇宙物理学の未解決問題をひも解いていくことがテーマとなっています。
じつは、この議題は今現在も未解決の謎とされています。それもそのはず、わたしたち人類が宇宙について知っていることは、わずか5%とされているからです。その5%を6%、7%、8%……と上げてくれるかもしれないのが、こうした最新の理論や定理なのです。
本書では、ペンローズの「特異点定理」に至るまでの道筋を示していきます。第1章の始まりは、17世紀の物理学者アイザック・ニュートンが発見した「ニュートン力学」。そして、コペルニクス、ケプラー、ガリレイ、アインシュタイン、シュバルツシルト、ペンローズと……壮大な物理学と数学の解説、そして天文学の歴史が語られていきます。
実際、本書のなかでは、特異点や宇宙検閲官仮説を説明するうえで、多くの数式が登場します。その数式一つひとつに宇宙の真理がちりばめられているので、特に物理学や天文学、数学が好きだという方は、その読み解きに興じるのもよいでしょう。
アインシュタインは一般相対性理論、そして特殊相対性理論を導き出し、この世界の一つの法則を数式で表すことに成功します。しかし、そこに示されたブラックホールの存在についても、また宇宙は決して普遍の存在でないということも信じられなかったと言います。いまや、そうした人類史に大きな影響を与えた人物でさえ受け入れられなかった事象が形になっているのです。
真貝先生は本書のなかで、多くの数式とともに、それに伴う学者たちのこの世界の果てを見ようとする苦闘や葛藤、そして希望や興奮を記しています。残された理論を別の研究者が読み解いていく姿は、予言書が解読されていくようなロマンを感じるということです。
近年、宇宙開発競争が進み、宇宙はさらにわたしたちの身近なものになりつつあります。しかし、それはほんの表層的な部分で、宇宙の深部にはまだまだわたしたちが知り得ることもできない事象が起こっています。
宇宙への疑問は尽きず、人類が存在している間に全てを解き明かせる保証もありません。しかし、真貝先生をはじめ、そんな果てのない世界に挑み続けている人々がいます。本書は宇宙に関する知識はもちろんのこと、ある意味で暗闇に挑むといった勇気を与えてくれるような一冊です。ぜひ、一度お手にとってご覧ください。
それは、式のなかに「特異点」が含まれていること。特異点とは、この世界の物理法則を破綻させてしまう、「無限大」を導く点のことをいいます。そんな問題のある存在が宇宙には漂っているのでしょうか。そのようなものが存在するのなら、とても危険なのでは……。
今回取り上げるのは、その「特異点」にまつわる物理学の巨大な謎を解説する一冊、大阪工業大学情報科学部教授である真貝寿明先生の著書『宇宙検閲官仮説 「裸の特異点」は隠されるか』(ブルーバックス)です。
特異点を覆い隠している謎の天体ブラックホール
本書のタイトルとなっている「宇宙検閲官」、そして「裸の特異点」とは、一体なにを指すのでしょうか。それにはまず、謎の天体「ブラックホール」について知らなくてはなりません。ブラックホールの姿が初めて写真に収められたのは2019年のことです。一昔前まで、ブラックホールは架空の存在として扱われてきました。一般相対性理論によってその存在が示唆されていましたが、アインシュタイン本人でさえ、その存在を否定していたほどでした。ところが、後世の学者たちによって「ブラックホールは実在する」ということがわかり、一般相対性理論の正しさが証明されるとともに、ブラックホールのなかには物理法則が破綻をきたす「特異点」があることがわかりました。
ブラックホールのなかに「特異点」が自然発生することを証明したのは、2020年にノーベル物理学賞を受賞したイギリスのロジャー・ペンローズ。彼の提唱する特異点の発生理論は「特異点定理」といわれています。しかし、ブラックホールは光さえも飲み込んでしまう超重力を持った天体です。いくら物理法則が破綻をきたす「特異点」といっても、ブラックホールが包み隠してくれているなら、地球に暮らす私たち生物に影響は出ないのかもしれません。
ところが、この「特異点定理」を突き詰めていくと、どうやら「ブラックホールの外側にも特異点が存在しているのでは」という事象が導き出されてしまうのです。
物理法則が破綻をきたす「特異点」は“検閲”されているのか
ペンローズはこのブラックホールに包まれていない、“裸の”特異点の発生に対して、一つの仮説を打ち立てました。それが「宇宙検閲官仮説」です。〈検閲官とは、公序良俗を乱すような「不適切な表現」が公衆の目にふれないように取り締まる役人のことですが、宇宙にもそのようなものが存在している(に違いない)という考えが「宇宙検閲官仮説」です〉
本書の冒頭で、真貝先生はこのように説明しています。本書は、あってはならないこの不適切な場所〈“裸の”特異点〉が本当に存在しているのか、そして存在しているとしたら、ペンローズが言うようにそれを検閲する存在があるのかどうか。そうした宇宙物理学の未解決問題をひも解いていくことがテーマとなっています。
じつは、この議題は今現在も未解決の謎とされています。それもそのはず、わたしたち人類が宇宙について知っていることは、わずか5%とされているからです。その5%を6%、7%、8%……と上げてくれるかもしれないのが、こうした最新の理論や定理なのです。
本書では、ペンローズの「特異点定理」に至るまでの道筋を示していきます。第1章の始まりは、17世紀の物理学者アイザック・ニュートンが発見した「ニュートン力学」。そして、コペルニクス、ケプラー、ガリレイ、アインシュタイン、シュバルツシルト、ペンローズと……壮大な物理学と数学の解説、そして天文学の歴史が語られていきます。
この世界の真理を示す理論と数式
真貝先生の専門は一般相対性理論や重力理論、天文文化学ですが、専門家だからこそ、本書を執筆するにあたり、この議題を読者の方へ平易に説明することの難しさを感じたそうです。しかし、数式なしにこの議題を解説することはできません。真貝先生は、「数式はイメージとして読み飛ばしていただいても話はつながっていますので、ご安心ください」と一言添えています。実際、本書のなかでは、特異点や宇宙検閲官仮説を説明するうえで、多くの数式が登場します。その数式一つひとつに宇宙の真理がちりばめられているので、特に物理学や天文学、数学が好きだという方は、その読み解きに興じるのもよいでしょう。
アインシュタインは一般相対性理論、そして特殊相対性理論を導き出し、この世界の一つの法則を数式で表すことに成功します。しかし、そこに示されたブラックホールの存在についても、また宇宙は決して普遍の存在でないということも信じられなかったと言います。いまや、そうした人類史に大きな影響を与えた人物でさえ受け入れられなかった事象が形になっているのです。
真貝先生は本書のなかで、多くの数式とともに、それに伴う学者たちのこの世界の果てを見ようとする苦闘や葛藤、そして希望や興奮を記しています。残された理論を別の研究者が読み解いていく姿は、予言書が解読されていくようなロマンを感じるということです。
果てのない世界に挑み続ける人々
はたしてペンローズの宇宙検閲官仮説は正しいのか。わたしたちの知る理論や定理で解決できる問題なのか。ペンローズの理論はどんな影響を与え続けているのか。解決を見ていないとはいえ、読み進めていくと、その壮大さにため息が漏れるとともに、見えてくる糸口もあります。近年、宇宙開発競争が進み、宇宙はさらにわたしたちの身近なものになりつつあります。しかし、それはほんの表層的な部分で、宇宙の深部にはまだまだわたしたちが知り得ることもできない事象が起こっています。
宇宙への疑問は尽きず、人類が存在している間に全てを解き明かせる保証もありません。しかし、真貝先生をはじめ、そんな果てのない世界に挑み続けている人々がいます。本書は宇宙に関する知識はもちろんのこと、ある意味で暗闇に挑むといった勇気を与えてくれるような一冊です。ぜひ、一度お手にとってご覧ください。
<参考文献>
『宇宙検閲官仮説 「裸の特異点」は隠されるか』 (真貝寿明著、ブルーバックス)
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000374533
<参考サイト>
大阪工業大学 情報科学部 情報システム学科 宇宙物理・数理科学研究室
https://www.oit.ac.jp/is/shinkai/
『宇宙検閲官仮説 「裸の特異点」は隠されるか』 (真貝寿明著、ブルーバックス)
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000374533
<参考サイト>
大阪工業大学 情報科学部 情報システム学科 宇宙物理・数理科学研究室
https://www.oit.ac.jp/is/shinkai/
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子










