テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
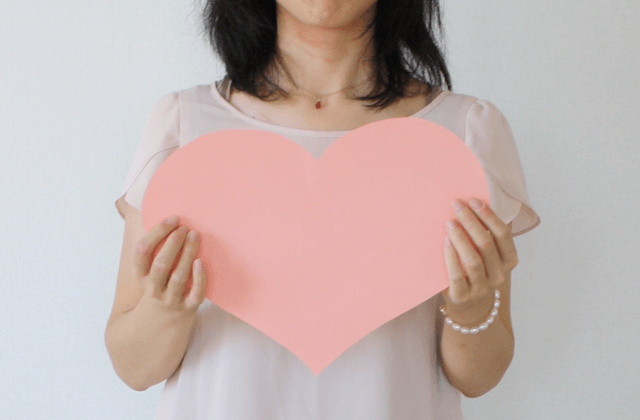
なぜ日本人は空気を読むのか?多神教の世界にみる欧米との違い
「KY」という言葉を聞かなくなって久しい。この流行語一つとってもわかるとおり、日本では空気を読むことが美徳とされてきた。一方で、以前から、空気を読みすぎることの弊害があるともいわれている。そこで、なぜ日本人は空気を読むのか、空気を読むのがよいのかどうかを改めて考えてみたい。
では、「空気」とはいったい何なのか。山本七平氏は、名著『「空気」の研究』で、空気とは古代ギリシア語のプネウマやアニマとほぼ同意だといっている。プネウマやアニマとは、風・空気を示すとともに、息・呼吸・気・精・たましい・精神などを意味する言葉だ。場の空気とは、風のように捉えがたい「気」のようなものである。
山本氏は、その原因を一神教に見ている。一神教の世界では、絶対なのは神だけで、他はすべて徹底的に相対化される。場の空気も相対化されるため、空気が絶対化されて、場を支配することが少ない。場の空気に対して反論を投げつけ、議論を進めていくのがむしろ普通の行為となっているのが、欧米の文化である。
対して、日本はアミニズム、多神教の世界であり、相対化はない。あらゆるものが神になりうるわけで、絶対化の対象が無数にある。だから、たとえば経済成長と環境問題は相対的に把握されず、一時期は「経済成長」が絶対化され、次は「環境問題」が絶対化されるという形になる。流行の移り変わりが速く、熱しやすく冷めやすいのは、日本が空気の支配に弱いからなのだ。こうした日本の特徴は、以前より少し弱まったかもしれないが、依然として続いていると見てよいだろう。
場の空気は、風のように捉えがたい
「あの場ではああ言うしかなかったけれど、あの決定はちょっとね…」。こうした言葉を、日本ではいまもよく耳にする。空気が場を支配している何よりの証拠である。不祥事が起きても、誰一人きちんと責任を取らない組織がたくさんあるのは、「悪いのは私じゃない。場の空気がそうさせたのだ」と責任転嫁できる文化があるからだ。では、「空気」とはいったい何なのか。山本七平氏は、名著『「空気」の研究』で、空気とは古代ギリシア語のプネウマやアニマとほぼ同意だといっている。プネウマやアニマとは、風・空気を示すとともに、息・呼吸・気・精・たましい・精神などを意味する言葉だ。場の空気とは、風のように捉えがたい「気」のようなものである。
欧米にも空気はあるが、支配されにくい
間違ってはならないのは、「空気」は、別に日本だけにあるものではないということだ。空気は、世界中にある。しかし、少なくとも欧米は日本のように、場が空気に支配されることは少ない。山本氏は、その原因を一神教に見ている。一神教の世界では、絶対なのは神だけで、他はすべて徹底的に相対化される。場の空気も相対化されるため、空気が絶対化されて、場を支配することが少ない。場の空気に対して反論を投げつけ、議論を進めていくのがむしろ普通の行為となっているのが、欧米の文化である。
対して、日本はアミニズム、多神教の世界であり、相対化はない。あらゆるものが神になりうるわけで、絶対化の対象が無数にある。だから、たとえば経済成長と環境問題は相対的に把握されず、一時期は「経済成長」が絶対化され、次は「環境問題」が絶対化されるという形になる。流行の移り変わりが速く、熱しやすく冷めやすいのは、日本が空気の支配に弱いからなのだ。こうした日本の特徴は、以前より少し弱まったかもしれないが、依然として続いていると見てよいだろう。
空気支配から脱却すべきではないのか
「イノベーション」が流行語になって久しいが、イノベーションは空気を読んでいては起こせない。「多様性」を重視する企業が増えているが、皆が空気を読んでいては多様性の意味はない。そろそろ日本は、空気の支配から脱却する時期に来ているのではないだろうか。そのためには、まず何よりも、物事を相対的に眺める習慣を身につける必要があるだろう。その第一歩として、一人ひとりが空気を読むのをあえて止めてみてはどうだろうか。
<参考文献>
・『「空気」の研究』(山本七平/文藝春秋)
・『「空気」の研究』(山本七平/文藝春秋)
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
葛飾北斎と応為の見事な「画狂人生」を絵と解説で辿る
テンミニッツ・アカデミー編集部
最近の話題は宇宙生命学…生命の起源に迫る可能性
川口淳一郎










