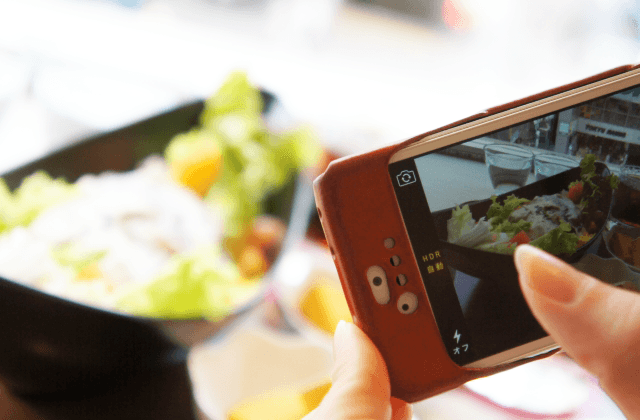
写真投稿で住所がバレる?スマホマナーと危険性
街中で、スマホを見ながら歩いていたり、電車の中でずっとスマホを見ている人が多くなりました。特にポケモンGOが日本にスタートしてからは、歩きスマホの人を非常によく見かけるようになりました。
しかし、ゲームやSNSに熱中しすぎて、周りが見えなくなっていませんか。スマホを見ているだけで人に迷惑をかけたり、大きな事故につながることもあるのです。
そのため、通信業界では歩きスマホ問題を重く受け止め、ホームページだけでなく、公共機関などと組んで注意喚起を行っているところもあります。もはや社会問題となってしまっています。
ちなみに、自転車に乗りながらのスマホに関しては、平成21年7月1日から一部改正され施行された東京都道路交通規則第8条で「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」として禁止されており、違反すると5万円以下の罰金となっています。このような罰則はまだ、歩きスマホにはありませんが、事故や被害が広がっていけば、罰則化の動きが進んでいくのもそう遠くないはずです。
また映画館や劇場、美術館などでは電源を切らなくてはいけません。誰もがわかっていることですが、うるさく言われないと守れないという人もいます。病院など精密機器の不具合を起こしかねないために使用を禁止されている場所も同じ。スマホを取り出す前に、いま使ってもいいかどうか、一度考えてみることが必要です。
さらに、撮った写真をすぐにSNSへ投稿すると、そこで問題が発生するケースも。『SNS時代の写真ルールとマナー』(日本写真家協会編、朝日新書)では、スマホの位置情報について触れ、スマホには「GPS(全地球測位システム)や電波を使って、自分がいる場所を判断する機能」があり、それは「撮影した場所を調べられる便利な機能なのですが、その写真をインターネットで公開すると、他人でも撮影場所を調べることができてしまう」とあります。例えば、「自宅で撮った写真をそのままアップロードすると、住所までインターネットに公表することになってしまう」そうです。つまり、写真を撮る行為が自分に危険を及ぼすこともあるということです。これを防ぐためにはスマホの位置情報をオフにすることが必要となるということで、スマホでの写真撮影の知識として覚えておきましょう。
しかし、ゲームやSNSに熱中しすぎて、周りが見えなくなっていませんか。スマホを見ているだけで人に迷惑をかけたり、大きな事故につながることもあるのです。
みんなやりがち歩きスマホ
歩きスマホについては、CMやポスターなどで注意喚起があるものの、ついやってしまいがちです。スマホを見ているときは、普通に前を見ているときに比べて視界が20分の1に落ちるといいます。これは怖いことです。混んでいる場所を歩くだけでも人とぶつかる可能性が高いのに、多くの人が視界を奪われたまま歩いたらどうなるか、想像できますね。スマホを見ながら歩いている間、私たちは無防備な状態になります。車や自転車が近づいてきても、とっさによけることができず、たいへんな事故につながることもあるのです。そのため、通信業界では歩きスマホ問題を重く受け止め、ホームページだけでなく、公共機関などと組んで注意喚起を行っているところもあります。もはや社会問題となってしまっています。
ちなみに、自転車に乗りながらのスマホに関しては、平成21年7月1日から一部改正され施行された東京都道路交通規則第8条で「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」として禁止されており、違反すると5万円以下の罰金となっています。このような罰則はまだ、歩きスマホにはありませんが、事故や被害が広がっていけば、罰則化の動きが進んでいくのもそう遠くないはずです。
TPOをわきまえる
時と場所と場合、これを考えるのがスマホを手にする人の最低限のマナーです。電車の中で気を付けたいのが、イヤフォンの音量。聞こえているのは自分だけ、と思いきや、意外ともれていたりします。自分には心地よい音楽でも、他人にとっては騒音でしかないときもあります。一度外してみて、大きすぎないかを確かめたほうがいいでしょう。また映画館や劇場、美術館などでは電源を切らなくてはいけません。誰もがわかっていることですが、うるさく言われないと守れないという人もいます。病院など精密機器の不具合を起こしかねないために使用を禁止されている場所も同じ。スマホを取り出す前に、いま使ってもいいかどうか、一度考えてみることが必要です。
写真を撮ることの気軽さと危うさ
今のスマホには優れた写真機能が搭載されています。まるでカメラを持ち歩くように、スマホですぐ写真が撮れる時代です。しかしその手軽さから、いつでもどこでも写真を撮るのはどうなのか、という問題があります。芸能人も一般人も、街中を歩く人たちはスマホの画面におさまるためにいるのではありません。ちょっと変わったことがあったからといってなんでもかんでもスマホで写真を撮ると、それがいつの間にか盗撮行為だと誤解されてしまうこともあるので注意が必要です。さらに、撮った写真をすぐにSNSへ投稿すると、そこで問題が発生するケースも。『SNS時代の写真ルールとマナー』(日本写真家協会編、朝日新書)では、スマホの位置情報について触れ、スマホには「GPS(全地球測位システム)や電波を使って、自分がいる場所を判断する機能」があり、それは「撮影した場所を調べられる便利な機能なのですが、その写真をインターネットで公開すると、他人でも撮影場所を調べることができてしまう」とあります。例えば、「自宅で撮った写真をそのままアップロードすると、住所までインターネットに公表することになってしまう」そうです。つまり、写真を撮る行為が自分に危険を及ぼすこともあるということです。これを防ぐためにはスマホの位置情報をオフにすることが必要となるということで、スマホでの写真撮影の知識として覚えておきましょう。
意識の低さが規制を生む
マナー、ルール、とうるさく思う人もいるかもしれません。しかし、自分が何気なくしていることが他人に迷惑をかけているとすれば、どうでしょう。自覚するだけで、おのずと行動が変わってくるはずです。
<参考文献>
『SNS時代の写真ルールとマナー』(日本写真家協会編、朝日新書)
『SNS時代の写真ルールとマナー』(日本写真家協会編、朝日新書)
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子
私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか…脳の働きで考える
長谷川眞理子







