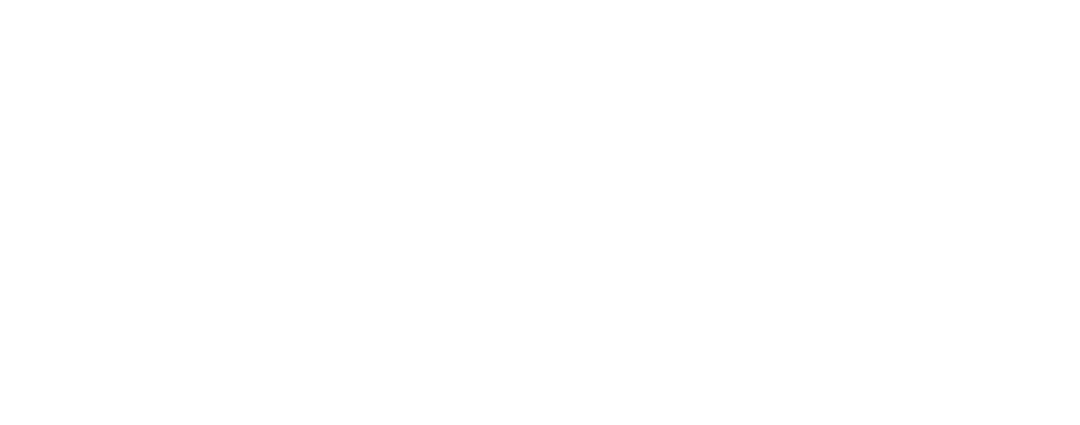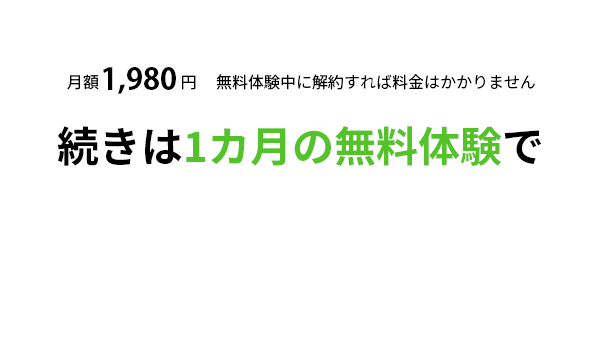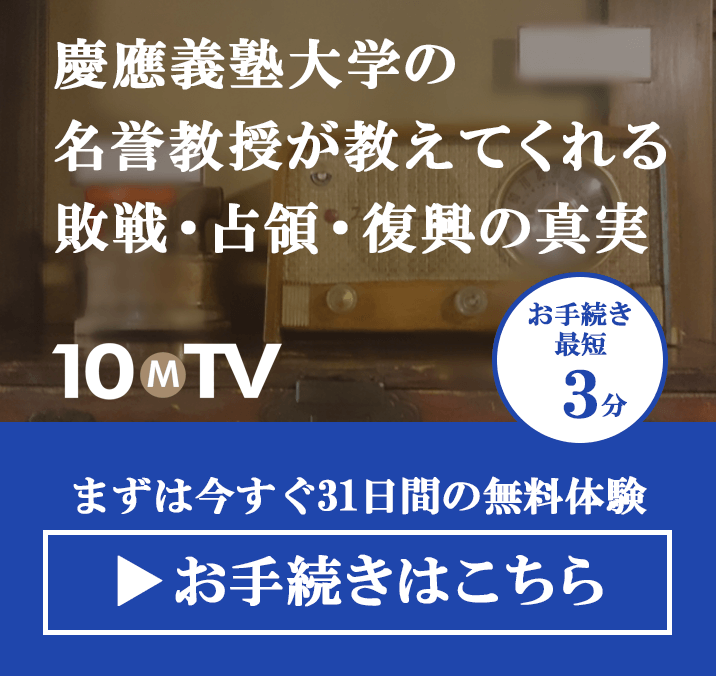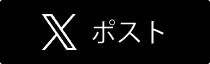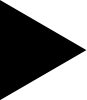●1942年に始まった戦後対策と「対日占領政策」
(ミッドウェー海戦大勝利)の勢いで、アメリカは「戦える」という感触を得ますが、それ以前から「対日占領政策」の検討を開始していたというから驚きます。
それは、第一次世界大戦からわずか20年で世界大戦を招いた原因が、戦後計画の不十分な講和にあったのではないかとの考えがあったからです。第一次大戦ではドイツに対して非常に高額な賠償金が要求され、その結果ドイツが反目したことが分かっています。それゆえ、「二度と戦争のない世界を構築したい」とアメリカは考えていたのです。
1942年2月、ハル国務長官を長として「戦後対策に関する諮問委員会(advisory committee on post-war foreign policy)」が開設されます。それまでの組織を統合し、民間から大量の専門家を糾合した組織でした。日本が戦勝気分で浮かれ返っていた頃です。
同年夏には、「極東班(far eastern group」」という専門家グループができます。そこに、日本語はできないもののアジア問題の大専門家であったジョージ・ブレイクスリーと、日本史の専門家のヒュー・ボートンの二人を専門家として招き、対日占領政策の立案を推進しようということになりました。
●「ハード・ピースか、ソフト・ピースか」の問題
当時、アメリカの世論で圧倒的だったのは「日本はけしからんから、粉々にして無条件降伏をさせろ。徹底的に破壊して、アメリカの手でつくり変えろ」という声で、実はフランクリン・ルーズベルト大統領自身が、そのように考えていたのです。
極東班が作業を開始した頃は、「ハード・ピースか、ソフト・ピースか」の二つの考え方がありました。ハード・ピースの考え方は処罰的平和で、「枢軸国をたたきつぶして、無条件に降伏させろ」というものです。ソフト・ピースの方は、その前に書かれた大西洋憲章に基づいて「もっと普遍的な人類的見地が必要だろう」とするもので、これが知日家たちの立場でした。いろいろな議論がある中、知日家の人たちは「アメリカにとって好ましい日本を再建する上では、天皇制が実は非常に貴重な財産だ」と指摘し、「戦後には、日本人自身が民主化改革できる」とも主張しました。
特に日本に詳しかったボートンは22ページのリポートを書きますが、その中には、ロンドン軍縮以来の穏健派の政治家は誰がいるか、彼らにはどんな役割が...