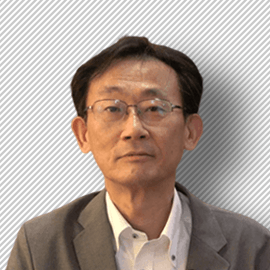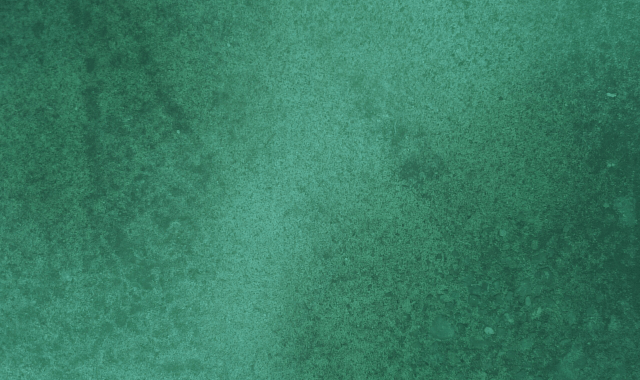●東北北部の方が中部地方・関東南部地方より水田稲作の開始は早かった
ここから第3章「金属器の登場」に入ります。これまでお話しした弥生時代は、金属器がなく石器だけの時代でした。今から50年ほど前の教科書には、弥生人は水田稲作を行い、最初から鉄器を利用していたと書かれていたかと思います。しかし、水田稲作の始まりが約500年さかのぼった結果、金属器を伴わないコメ作りの生活の存在が明らかになってきました。
金属器の話に入る前に、東北地方北部の水田稲作についてお話しします。先ほど日本で最も遅く水田稲作が始まった中部地方・関東地方のお話しをしましたが、そうすると東北北部の方が水田稲作の開始が早かったということになります。普通、より寒い東北地方の方が水田稲作の開始は遅れると考えがちですが、実は東北地方の日本海側では中部地方・関東地方南部に先んじて紀元前4世紀に水田稲作が始まったことが分かっています。
●世界最北端の砂沢遺跡から分かる東北北部の水田稲作の特徴
青森県弘前市の砂沢遺跡で、紀元前4世紀の水田跡が見つかりました。これは先史時代の遺跡としては、北緯40度を超える世界最北端の水田跡です。右側に見つかった水田の写真があります。手前が高く奥が低い、つまり手前から奥に向かって傾斜しているという構造です。ここから7区画の水田跡が見つかりました。
ただし、これらの水田は先ほどから説明しているような灌漑施設は持っておらず、傾斜を利用して手前から奥へと水を流していたとされています。この青森の水田跡の特徴は、もともと縄文人が住んでいたむらのすぐそばに造ったという点です。
先ほど福岡平野の例で説明しましたが、縄文人が利用していなかった場所に突然、水田が現れることが多いのです。西日本、たとえば近畿、あるいは関東南部ではそうした傾向が見られますが、青森だけはもともと縄文人が住んでいた領域内に水田が出現します。この事実は、誰が水田稲作を始めたのかという問題と大きく関わってきます。
他にも大きな特徴として、この砂沢遺跡は10年から12年という比較的短い期間しかコメを作っていないことが分かっています。また、西日本で水田稲作を行う遺跡でよく発見される木製農具や、朝鮮半島系の伐採用の斧などの、大陸的な道具や要素が、一切見られないのも特徴です...