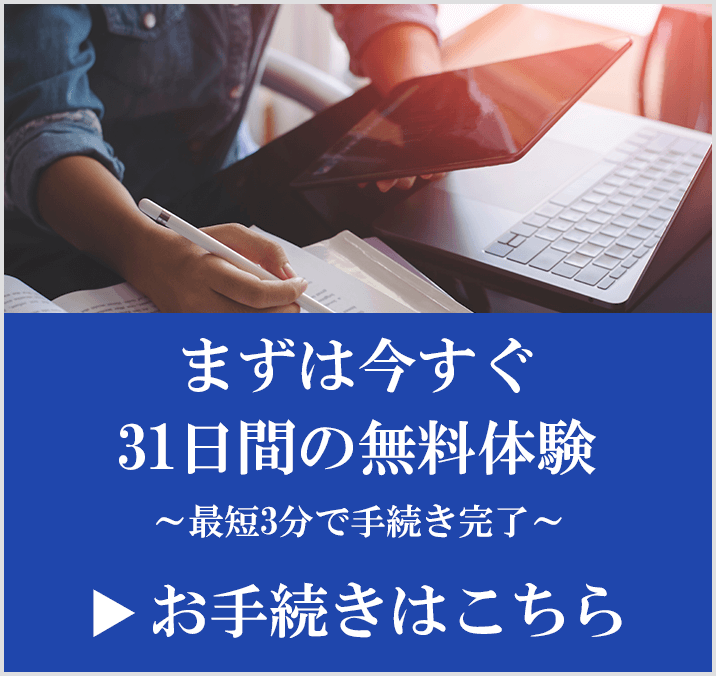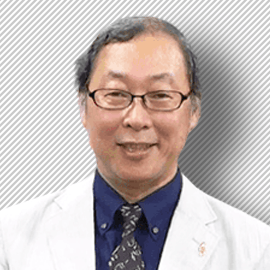●演奏会の静寂マナーは、ベートーヴェンに責任がある?
―― 前回はモーツァルトまできたので、今回はベートーヴェンですね。モーツァルトが子供のときから音楽をやっていたので、ベートーヴェンのお父さんがそれに憧れたのか、ずいぶん厳しく音楽修行をさせたという話が有名ですね。
野本 そうですね。実は、ベートーヴェンは「モーツァルト2世」みたいな感じ、「新しいモーツァルト」としてデビューしたんです。それこそ子供のときですが、「モーツァルト並みの天才が現れたぞ」というので、最初の演奏会をやったりしています。完全に意識をしていたことは確かです。
ただし、どうもベートーヴェンはモーツァルトに直接会うことはできなかったようなんですね。というのは、モーツァルトは1791年に亡くなってしまいますね。1770年生まれのベートーヴェンは22歳になる1792年にようやくウィーンに行くのですが、モーツァルトはもう死んじゃっているんです。
―― ベートーヴェンは、日本ではクラシックというと、知らない人はまずいない存在です。まず出てくるのがベートーヴェンですが、だいたい皆さんが不思議に思うのは、「ベートーヴェンは何がすごいか」ということだと思うんですけど、先生はどのようにお考えですか。
野本 ベートーヴェンは音楽史上、最大の人と言っても過言ではない存在ですね。もちろん音楽もすばらしいんですけども、いろいろな点でベートーヴェンはすばらしく画期的だった人なんです。
身近なことで言うと、演奏会に行ったら、とにかくおしゃべりもしちゃいけなくて、曲が始まったら静かに固まって聴いてなくちゃいけませんね。
―― 咳をするのも我慢するぐらいですね。
野本 それをしたのはベートーヴェンに責任があると言ってもいいんです。まさに「演奏中は、みんな黙って俺の曲を聴け」みたいな感じにしてしまったのが、つまり「娯楽」じゃなくて「芸術」だというふうにしたのがベートーヴェンなんです。
●「注文通り」ではなく「つくりたいもの」をつくりこむ
―― なるほど。それはモーツァルトまでの音楽とはけっこう違いますね。
野本 そうなんです。モーツァルトまでは「職人さん」だったわけです。給料をもらって、言われたようにつくる。言われたようにつくらなかったら、もう一遍書き直しというふうになっていたわけですから。
―― 「雰囲気が違います」...