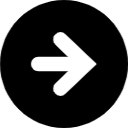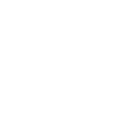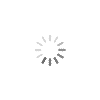イギリスも2020年に入って、それまで親中だったスタンスを大きく変えた。コロナの影響に加え、香港国家安全維持法によって、かつての宗主国だった香港のプライドが踏みにじられた。ファーウェイ製品についても、2020年1月まではアメリカの呼びかけに応じず一部採用予定だったが、7月になって全面排除を決めた。その背景にはイギリスの情報機関の存在もあり、イギリスのインテリジェンスには国策を変えさせる力がある。(全10話中第5話)
※インタビュアー:川上達史(テンミニッツTV編集長)
≪全文≫
●「一国二制度」の合意を踏みにじられたイギリス
―― 次にイギリス並びにヨーロッパの分析に行きたいのですが、まず香港について伺います。
今般の香港をめぐるが問題が、かなり大きなことになっています。以前ならアメリカ、とくにトランプ政権が比較的、反中の姿勢を示す中、ヨーロッパはそこまでではないという見方もありました。特にドイツは親中的なスタンスで、経済活動も含めて、いろいろやっているという見方もありました。これが2020年になって、ずいぶん変わってきたのでしょうか。
中西 非常に大きく変わりました。特にイギリスをはじめとするアングロサクソン諸国、あるいはアングロスフィア(アングロ圏)の国々を中心に、アメリカ以外の国でも「中国離れ」が急速に進んでいるのが、2020年の非常に大きな特徴です。やはりコロナの影響が大きいと思います。
特にイギリスはコロナの被害では、ヨーロッパでもっとも多い死者数を数えています。さらに香港については、イギリスは当事者の立場です。中国と合意した「一国二制度」が、世界の誰が見ても分かる格好で、中国によって踏みにじられた。「香港の自由、香港の民主主義は、われわれが育てた」というプライドが、イギリスにはあります。
実際は返還が決まるまで必ずしもイギリスは精力的に民主化を推進したわけではありませんが、それはともかく、返還の際の「英中共同声明」という合意も国際法の一部になり、国連にも寄託されています。中国はこれを、言わば紙くずのように捨て去ったわけです。どう見てもイギリスとしては許せない。
その旧宗主国としてのプライドは、われわれには分かりかねるものがありますが、やはりイギリスはそういうところで生きているところがあります。「われわれは大英帝国の後継者である」「世界に議会制を広げたのも我がイギリスである」「撤退したけれど、いろいろな国に民主主義を植え付けて近代化し、いろいろな恩恵も残してきた」。こういうこともイギリスのプライドの背景にあります。
●ファーウェイ製品の全面排除へ
中西 さらにはアメリカが訴えてきたファーウェイの5G問題をはじめとするセキュリティ問題に、イギリスも少し、あるいはかなりはっきり気づき始めたことも大きいと思います。これは日本のような、「アメリカに追随せよ」、あるいは「アメリカが言うからしかたがない」という立場では...