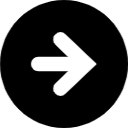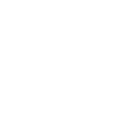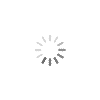この講義シリーズは第2話まで
登録不要で無料視聴できます!
本当のことがわかる昭和史《5》満洲事変と石原莞爾の蹉跌
満洲は別物―国際社会に第一に説くべきだったこと
本当のことがわかる昭和史《5》満洲事変と石原莞爾の蹉跌(7)崇高だった五族協和の理念
渡部昇一(上智大学名誉教授)
当時、国際社会に強調するべき点は、満州国はシナとは別物であるということに加えて、満洲国が掲げた「五族協和」の理念だった。日本人、漢人、朝鮮人、満洲人、蒙古人など諸民族の協調路線のことである。差別を排して、五族協和を実現するという理念は、まことに崇高なものだった。上智大学名誉教授・渡部昇一氏によるシリーズ「本当のことがわかる昭和史」第五章・第7回。
時間:4分15秒
収録日:2015年2月2日
追加日:2015年9月10日
収録日:2015年2月2日
追加日:2015年9月10日
カテゴリー:
≪全文≫
改めて考えてみると、日本には全体を考えて、実際に全体を動かしうる人がいなくなったのである。
国際連盟脱退で日本国内での人気を高めた松岡洋右は、昭和15年(1940)に第二次近衛文麿内閣の外相に就任するが、彼も幣原外交を批判し自主外交を主張したものの、英米に対抗するべく三国同盟路線を走り、さらにソ連を加えた四カ国同盟を構想するなど、また別の意味で危うい人だった。
ヨーロッパでは、ロカルノ条約を破棄したドイツがあっという間にオーストリアを併合(昭和13年〈1938〉)し、チェコスロバキア領だったズデーテン地方を割譲(同年)させるなど、再び緊張が高まっていた。
第一次世界大戦後の平和・緊張緩和の時代が終わり、国際的な軍拡競争と共産主義の脅威が広がり始めた世界の趨勢から見ると、日本が自存自衛を図るうえで最も正しい解は、やはり満洲事変であり、それが実際に成功を収めた。
だからこそ、なおさら、なぜあのとき日本は満洲国の独立をイギリスやアメリカにうまく説明できなかったのか、本当に残念で仕方がない。
繰り返し強調するが、ポイントは、満洲をシナの一部として見なしてしまっている西洋人たちに、「満洲は別物なのだ」ということをわからせられるかどうかだった。私も「リットン報告書」を注釈をつけながら精読したが(『全文 リットン報告書』〈ビジネス社〉)、リットン調査団も、満洲をシナの一部として見ていた。だから日本政府は、「満洲はシナではない」ということを、国際社会に第一に説くべきだったのである。
もう一つ強調すべきは、満洲国が「五族協和」を謳う国だったことだろう。先にも述べた通り、ここでいう五族協和とは日本人、漢人、朝鮮人、満洲人、蒙古人など諸民族の協調路線のことである。この時代に「民族自決」が叫ばれたことはすでに紹介した。植民地の独立などに大きな影響を与えた理念ではあるが、しかし、それが極端なかたちに行きすぎて排他主義を帯びると、悲劇的な民族紛争を招いてしまう。これは現代の世界も直面している課題である。さらに、「民族自決」を利用して、国際共産主義運動は自らの勢力を拡大しようとした。その結果、共産主義独裁政権が世界各地に成立し、各国で虐殺などが次々と引き起こされたのは20世紀の悲しい教訓であった。その意味でも、差別を排して、五族協和を実現するのだという理念は...
改めて考えてみると、日本には全体を考えて、実際に全体を動かしうる人がいなくなったのである。
国際連盟脱退で日本国内での人気を高めた松岡洋右は、昭和15年(1940)に第二次近衛文麿内閣の外相に就任するが、彼も幣原外交を批判し自主外交を主張したものの、英米に対抗するべく三国同盟路線を走り、さらにソ連を加えた四カ国同盟を構想するなど、また別の意味で危うい人だった。
ヨーロッパでは、ロカルノ条約を破棄したドイツがあっという間にオーストリアを併合(昭和13年〈1938〉)し、チェコスロバキア領だったズデーテン地方を割譲(同年)させるなど、再び緊張が高まっていた。
第一次世界大戦後の平和・緊張緩和の時代が終わり、国際的な軍拡競争と共産主義の脅威が広がり始めた世界の趨勢から見ると、日本が自存自衛を図るうえで最も正しい解は、やはり満洲事変であり、それが実際に成功を収めた。
だからこそ、なおさら、なぜあのとき日本は満洲国の独立をイギリスやアメリカにうまく説明できなかったのか、本当に残念で仕方がない。
繰り返し強調するが、ポイントは、満洲をシナの一部として見なしてしまっている西洋人たちに、「満洲は別物なのだ」ということをわからせられるかどうかだった。私も「リットン報告書」を注釈をつけながら精読したが(『全文 リットン報告書』〈ビジネス社〉)、リットン調査団も、満洲をシナの一部として見ていた。だから日本政府は、「満洲はシナではない」ということを、国際社会に第一に説くべきだったのである。
もう一つ強調すべきは、満洲国が「五族協和」を謳う国だったことだろう。先にも述べた通り、ここでいう五族協和とは日本人、漢人、朝鮮人、満洲人、蒙古人など諸民族の協調路線のことである。この時代に「民族自決」が叫ばれたことはすでに紹介した。植民地の独立などに大きな影響を与えた理念ではあるが、しかし、それが極端なかたちに行きすぎて排他主義を帯びると、悲劇的な民族紛争を招いてしまう。これは現代の世界も直面している課題である。さらに、「民族自決」を利用して、国際共産主義運動は自らの勢力を拡大しようとした。その結果、共産主義独裁政権が世界各地に成立し、各国で虐殺などが次々と引き起こされたのは20世紀の悲しい教訓であった。その意味でも、差別を排して、五族協和を実現するのだという理念は...
「歴史と社会」でまず見るべき講義シリーズ
人気の講義ランキングTOP10