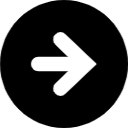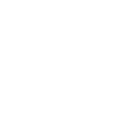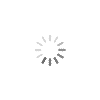本当のことがわかる昭和史《5》満洲事変と石原莞爾の蹉跌
列強に蚕食されていた中国で民族自決の気運が一気に高まる
本当のことがわかる昭和史《5》満洲事変と石原莞爾の蹉跌(2)アメリカとソ連が火をつけた「民族自決」
渡部昇一(上智大学名誉教授)
民族自決権という考え方が、対支二十一カ条で怒りを抱いたシナの若者たちに火をつけた。加えて、コミンテルンの過激な煽動によって、排日運動はどんどん激化していく。それがシナ本土だけならまだしも、満洲でも起こってくるから、なおさら日本も引けなくなった。上智大学名誉教授・渡部昇一氏によるシリーズ「本当のことがわかる昭和史」第五章・第2回。
時間:3分03秒
収録日:2015年2月2日
追加日:2015年9月7日
収録日:2015年2月2日
追加日:2015年9月7日
カテゴリー:
≪全文≫
だが、実は日本がロシアから得た満洲の権益の内実は不安定なものだった。いずれもロシアが清国と結んだ協定を、両国の了承のもとに引き継いだものだが、その協定では大連や旅順が含まれる関東州の租借期間はわずか25年であり、東清鉄道の権益は、開通後36年で清国が買い戻せることになっていた。租借は大正12年(1923)に、鉄道は昭和8年(1933)前後には、期限を迎えることになっていたのである。
その後、明治44年(1911)に辛亥革命が起こり、シナでは中華民国が生まれ、やがて袁世凱が大総統の地位に就く。日本は袁世凱に突きつけた対支二十一カ条(大正4年〈1915〉)──このうち最後の五カ条は撤去──で、99年の期間延長を認めさせ、一息ついた。
だが、ロシアにソビエト連邦が誕生して左翼思想で反日運動を煽動し、また、アメリカが引き続きシナへの参入を強く求めたことが、日本を新たな窮地に陥れていくことになる。
ソ連のスターリンが、東アジアの主敵である日本を打倒するために「中国革命」を利用した話は第一章で紹介した通りだ。ソ連は、国民党にも中国共産党にも援助をし、両者を国共合作で合同させようと画策する。そして民族主義を鼓吹し、中国人民の敵愾心を日本に向けて、各地で深刻な反日運動を展開させていった。
そして、民族主義を鼓吹したのはアメリカも同じだった。第一次大戦後にアメリカが訴えた「民族自決権」という考え方が、大きな影響を与えたのである。
「民族自決」とは本来、第一次大戦終盤にアメリカのウィルソン大統領が議会に対する教書の中で、講和の原則の一つとして示したものである。あくまで第一次世界大戦の戦場となったヨーロッパ、とくに当時のオーストリア=ハンガリー帝国などの支配下にあった各民族に対し、政治体制や帰属を自ら決定する権利を持つ、としたのが、ウィルソン大統領が唱えた民族自決権であった。
そもそも、イギリスがインドをはじめとする植民地を、民族自決権に基づき独立させるはずはないし、アメリカもフィリピン、ハワイに対して民族自決権を認めるわけがない。民族自決権といえば非常にきれいに聞こえるが、実は、それはハプスブルク家が統治していた東ヨーロッパから中央ヨーロッパにかけての複雑な民族関係に限られていたのだ。
だが、そんなアメリカの本来の思惑を超えて、「民族自決」の考え方...
だが、実は日本がロシアから得た満洲の権益の内実は不安定なものだった。いずれもロシアが清国と結んだ協定を、両国の了承のもとに引き継いだものだが、その協定では大連や旅順が含まれる関東州の租借期間はわずか25年であり、東清鉄道の権益は、開通後36年で清国が買い戻せることになっていた。租借は大正12年(1923)に、鉄道は昭和8年(1933)前後には、期限を迎えることになっていたのである。
その後、明治44年(1911)に辛亥革命が起こり、シナでは中華民国が生まれ、やがて袁世凱が大総統の地位に就く。日本は袁世凱に突きつけた対支二十一カ条(大正4年〈1915〉)──このうち最後の五カ条は撤去──で、99年の期間延長を認めさせ、一息ついた。
だが、ロシアにソビエト連邦が誕生して左翼思想で反日運動を煽動し、また、アメリカが引き続きシナへの参入を強く求めたことが、日本を新たな窮地に陥れていくことになる。
ソ連のスターリンが、東アジアの主敵である日本を打倒するために「中国革命」を利用した話は第一章で紹介した通りだ。ソ連は、国民党にも中国共産党にも援助をし、両者を国共合作で合同させようと画策する。そして民族主義を鼓吹し、中国人民の敵愾心を日本に向けて、各地で深刻な反日運動を展開させていった。
そして、民族主義を鼓吹したのはアメリカも同じだった。第一次大戦後にアメリカが訴えた「民族自決権」という考え方が、大きな影響を与えたのである。
「民族自決」とは本来、第一次大戦終盤にアメリカのウィルソン大統領が議会に対する教書の中で、講和の原則の一つとして示したものである。あくまで第一次世界大戦の戦場となったヨーロッパ、とくに当時のオーストリア=ハンガリー帝国などの支配下にあった各民族に対し、政治体制や帰属を自ら決定する権利を持つ、としたのが、ウィルソン大統領が唱えた民族自決権であった。
そもそも、イギリスがインドをはじめとする植民地を、民族自決権に基づき独立させるはずはないし、アメリカもフィリピン、ハワイに対して民族自決権を認めるわけがない。民族自決権といえば非常にきれいに聞こえるが、実は、それはハプスブルク家が統治していた東ヨーロッパから中央ヨーロッパにかけての複雑な民族関係に限られていたのだ。
だが、そんなアメリカの本来の思惑を超えて、「民族自決」の考え方...
「歴史と社会」でまず見るべき講義シリーズ
人気の講義ランキングTOP10