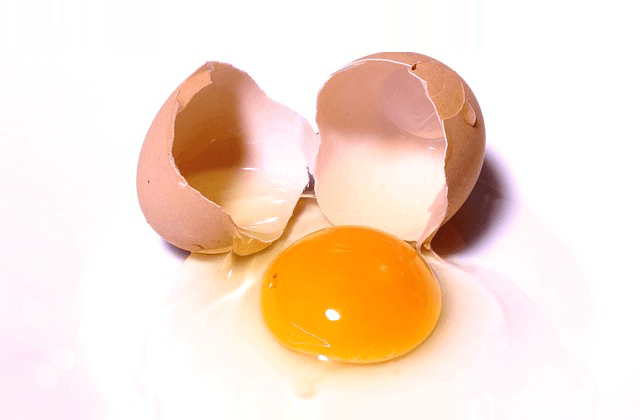
健康のヒミツは「タンパク質」にあった!
「タンパク質」と聞くと、多くの方が、お肉や魚、卵や乳製品、大豆など食べ物を思い浮かべるのではないしょうか。じっさい、これらの食べ物にはタンパク質が多く含まれており、健康を維持するために、適正量の摂取が欠かせません。
ただし、タンパク質のスゴいところは、こうした栄養に関する話にとどまりません。じつは、食べ物以外でも、タンパク質は健康と密接に関わっているのです。最近の研究では、がんやアルツハイマー、うつ病との関係も指摘され、その治療や予防がおおいに期待されています。
からだには、約2万種類のタンパク質があり、そのうち60パーセントは機能も判明しています。ほとんどが、からだのしくみにとって、とても重要な役割を果たしています。そのため、タンパク質の異常は、病気を引き起こす原因となるのだそうです。
このことは、タンパク質の異常をうまく検出できれば、病気の診断の役に立ち、異常を修復することで治療できる可能性があるということ示しています。
また、岡山理科大学と徳島大学の共同研究グループは、「うつ病」を改善させる可能性のあるタンパク質を突き止めたと発表しています。
ロイター通信は、イギリスの分子生物学研究所のチームが、「アルツハイマー病」患者の脳に蓄積するタンパク質の構造を初めて解明し、「新たな治療確立の入り口になる見通し」と伝えています。
以上の3つはすべて「2017年の6月」以降に報道されたニュースです。タンパク質の研究は、今まさに、現在進行形で急速に発展しつつあります。今後もまちがいなく、タンパク質の研究から革新的な医療技術が創出されていくことでしょう。
これらの病気の予防は、野菜や果物に含まれるビタミンAやビタミンCなどの抗酸化物質やミネラルを摂取することによって、可能になります。したがって、まじめにタンパク質を考えて食事をするのなら、肉や魚とともに、野菜もたっぷり摂取することが実は必要なのです。
タンパク質の酸化障害のメカニズムが解明されれば、老化の進行を遅らせることができるかもしれないと言われています。難病の予防や治療、アンチエイジングなど、ますます期待は膨らみますが、健康も老化防止も、大事なのはやはり生活習慣。タンパク質の正しい知識を吸収して、生活習慣に磨きをかけましょう。なお、タンパク質の名を借りた、ちょっとあやしい健康法や食事法も少なくないので、ご注意を。
スゴいのは「栄養」だけじゃない
タンパク質は、からだの主要成分です。体重のおよそ20パーセントを占めており、これは水分に次いで多い割合です。三大栄養素のひとつと言われる理由もここにあります。ただし、タンパク質のスゴいところは、こうした栄養に関する話にとどまりません。じつは、食べ物以外でも、タンパク質は健康と密接に関わっているのです。最近の研究では、がんやアルツハイマー、うつ病との関係も指摘され、その治療や予防がおおいに期待されています。
タンパク質は2万種類もある!?
実は、タンパク質、自然科学においては最先端の研究分野です。ノーベル賞を受賞した大隅良典教授(2016)や下村脩教授(2008)、田中耕一教授(2002)の研究もすべてタンパク質に関わるものでした。こうした功績もあって、タンパク質の種類や役割が次第に明らかになってきました。からだには、約2万種類のタンパク質があり、そのうち60パーセントは機能も判明しています。ほとんどが、からだのしくみにとって、とても重要な役割を果たしています。そのため、タンパク質の異常は、病気を引き起こす原因となるのだそうです。
このことは、タンパク質の異常をうまく検出できれば、病気の診断の役に立ち、異常を修復することで治療できる可能性があるということ示しています。
「がん」も「うつ」も「認知症」も
最近では、あるタンパク質を指標にすることで、「膵臓がん」を正確に早期検出できる可能性のある血液検査法が開発され話題となりました。また、岡山理科大学と徳島大学の共同研究グループは、「うつ病」を改善させる可能性のあるタンパク質を突き止めたと発表しています。
ロイター通信は、イギリスの分子生物学研究所のチームが、「アルツハイマー病」患者の脳に蓄積するタンパク質の構造を初めて解明し、「新たな治療確立の入り口になる見通し」と伝えています。
以上の3つはすべて「2017年の6月」以降に報道されたニュースです。タンパク質の研究は、今まさに、現在進行形で急速に発展しつつあります。今後もまちがいなく、タンパク質の研究から革新的な医療技術が創出されていくことでしょう。
野菜が「タンパク質」のためになる
タンパク質のはたらきは、普段のヘルスケアにも応用できます。たとえば、紫外線や放射線の照射、精神的ストレスなどで発生する活性酸素は、からだの中で増えすぎると、タンパク質の酸化障害を引き起こします。このタンパク質の酸化障害は、脳卒中やアルツハイマー病、糖尿病、がん、老化など、さまざまな疾患の原因になります。これらの病気の予防は、野菜や果物に含まれるビタミンAやビタミンCなどの抗酸化物質やミネラルを摂取することによって、可能になります。したがって、まじめにタンパク質を考えて食事をするのなら、肉や魚とともに、野菜もたっぷり摂取することが実は必要なのです。
タンパク質の酸化障害のメカニズムが解明されれば、老化の進行を遅らせることができるかもしれないと言われています。難病の予防や治療、アンチエイジングなど、ますます期待は膨らみますが、健康も老化防止も、大事なのはやはり生活習慣。タンパク質の正しい知識を吸収して、生活習慣に磨きをかけましょう。なお、タンパク質の名を借りた、ちょっとあやしい健康法や食事法も少なくないので、ご注意を。
<参考文献・参考サイト>
・『タンパク質とからだ』(平野久著、中央公論新社)
・国がんとAMED 膵がん早期発見へ 新血液バイオマーカーでの実験的検診を実施、鹿児島で
https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/57675/Default.aspx
・アルツハイマーの原因タンパク質の原子構造を解明、英チーム
http://jp.reuters.com/article/alzheimer-idJPKBN19R0KJ
・うつ病関与のタンパク質を特定 胃炎の治療剤が効果か
https://www.j-cast.com/healthcare/2017/06/01299546.html
・『タンパク質とからだ』(平野久著、中央公論新社)
・国がんとAMED 膵がん早期発見へ 新血液バイオマーカーでの実験的検診を実施、鹿児島で
https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/57675/Default.aspx
・アルツハイマーの原因タンパク質の原子構造を解明、英チーム
http://jp.reuters.com/article/alzheimer-idJPKBN19R0KJ
・うつ病関与のタンパク質を特定 胃炎の治療剤が効果か
https://www.j-cast.com/healthcare/2017/06/01299546.html
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子







