テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
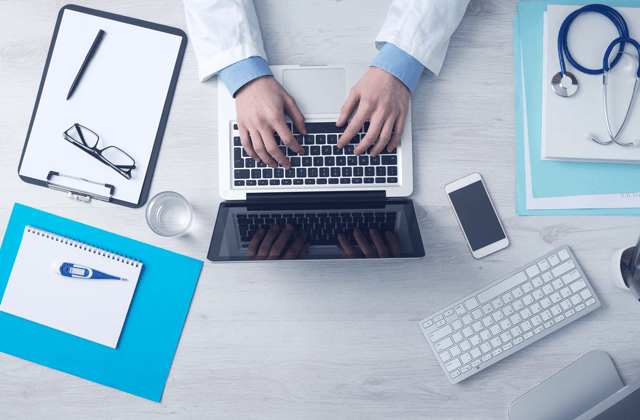
世界に誇る日本の医療制度~一枚の健康保険証の重み
みなさんの中には、内科、整形外科、眼科などいつも決まっていくクリニックや病院があるけれども、「あそこの歯医者さん上手だよ」といった評判を聞くと、「一度そっちで診てもらおうかな」と思って変えてみた、という経験のある方もいるのではないでしょうか。しかし、私たちが当たり前のように思っている、この医療機関を自分で選べるというシステムは、実は世界の中ではかなり例外的なものなのです。
ところが、これは世界ではかなり例外的な制度で、たとえばイギリスでは、「National Health Service」という国が定めた制度のもと、地域の診療所のドクター(家庭医)に登録されます。深刻な症状があるため大病院で診てもらいたいと思っても、最初は必ずこの家庭医の診療を受けて、必要があれば他の専門医、病院を紹介してもらうという流れになるそうです。
フランスもやはり、かかりつけ医の紹介なしに他の医師の診療を受けることを制限されていて、仮に紹介状無しで受診しようとすると、かなり高額の医療費を払わなければならないのだとか。
日本でもホームドクターやかかりつけ薬局を持って、地域の医療機関と密な関係を築こうと言われ始めていますが、それでも、最初から制限されているのと、選択肢が自由な中でメインの医師を決めておくのでは、大変な違いがあります。
今村氏は、このフリーアクセスによって、いつでもどこでも気軽に医師に相談・診療してもらえる体制が、病気の早期発見、早期治療に役立っていると言います。
アメリカは長らくこの「国民皆保険」を課題としてきました。オバマ政権の時にいわゆる「オバマケア」が実施されましたが、これは公的保険の制度ではなく、民間の医療保険に加入しやすくしたというもの。それでもようやく多くの人が医療保険に加入できるようになったのが一転、トランプ大統領の「オバマケア完全撤廃」の方針で、再びアメリカの医療保険制度は揺れています。
おかげで、具合が悪いなと思ったらすぐに医者に診てもらえるし、出先で急にケガをした場合、どこの病院でも保健医療を受けられます。健康保険証をお財布やカバンに入れていつも持ち歩くという行為も、国民皆保険、フリーアクセスという日本の医療制度の特徴があってこそ、生きてくるのですね。
こうした高レベルの医療制度のおかげで、日本は世界に名だたる長寿国となり、高い保健医療水準を誇っています。しかし、この制度を維持するには多くの財源を必要とすること、人生100年時代と言われるほどの高齢化社会に向かって、必要な財源はますます増していくというのが、今後の問題です。その解決に向けては、保険料の負担増や保健医療の範囲の見直しなどが議論されており、こうした状況を聞くと、一枚の健康保険証の重みを感じます。
保険料負担はもちろんですが、私たちなりに日本の健康保険の仕組みを支えるためにできることを、考えていかなければなりません。そのためには、保険証はお守りとして、食生活や運動など生活習慣に気をつけて、「まず予防」を心がけたいですね。
制限の多い海外の医療事情
公益社団法人日本医師会副会長・今村聡氏によれば、日本の医療制度には主に三つの特徴があり、その一つが先述した医療機関を自分で選べるという、「フリーアクセス」のシステムです。これは、具合が悪いと感じたときに、文字通り、自由にどの医療機関にもアクセスできる、受診先を選べるというシステムです。ところが、これは世界ではかなり例外的な制度で、たとえばイギリスでは、「National Health Service」という国が定めた制度のもと、地域の診療所のドクター(家庭医)に登録されます。深刻な症状があるため大病院で診てもらいたいと思っても、最初は必ずこの家庭医の診療を受けて、必要があれば他の専門医、病院を紹介してもらうという流れになるそうです。
フランスもやはり、かかりつけ医の紹介なしに他の医師の診療を受けることを制限されていて、仮に紹介状無しで受診しようとすると、かなり高額の医療費を払わなければならないのだとか。
日本でもホームドクターやかかりつけ薬局を持って、地域の医療機関と密な関係を築こうと言われ始めていますが、それでも、最初から制限されているのと、選択肢が自由な中でメインの医師を決めておくのでは、大変な違いがあります。
今村氏は、このフリーアクセスによって、いつでもどこでも気軽に医師に相談・診療してもらえる体制が、病気の早期発見、早期治療に役立っていると言います。
日本が世界に誇る「国民皆保険」制度
そもそも、日本国民は原則として皆、公的な医療保険に加入しています。国民健康保険、各企業の健康保険組合や協会けんぽ、公務員のための共済組合といった保険を運営する「保険者」は約3500あり、日本国民全員が何らかの形でこうした医療保険の恩恵にあずかっているわけです。アメリカは長らくこの「国民皆保険」を課題としてきました。オバマ政権の時にいわゆる「オバマケア」が実施されましたが、これは公的保険の制度ではなく、民間の医療保険に加入しやすくしたというもの。それでもようやく多くの人が医療保険に加入できるようになったのが一転、トランプ大統領の「オバマケア完全撤廃」の方針で、再びアメリカの医療保険制度は揺れています。
長いようで短い日本の公的医療制度の歴史
しかし、世界に誇れるこの「国民皆保険」の歴史は意外と短いのです。それは1927(昭和2)年に施行された「健康保険法」までさかのぼります。しかし、この時点では、保険対象者は一部大企業の従業員に限られていました。終戦後も国民の3分の1が公的医療保険未加入の状態であったため、すべての人が安心して医療を受けられることを目的に議論が続き、1958年に国民健康保険法」が制定。現在の「国民皆保険」が実現したのは1961年のことでした。まだ60年も経っていないのです。おかげで、具合が悪いなと思ったらすぐに医者に診てもらえるし、出先で急にケガをした場合、どこの病院でも保健医療を受けられます。健康保険証をお財布やカバンに入れていつも持ち歩くという行為も、国民皆保険、フリーアクセスという日本の医療制度の特徴があってこそ、生きてくるのですね。
健全な医療制度を維持するために
今村氏が挙げるもう一つの特徴が「現物支給」です。診療や注射や手術、薬など、必要な医療をお金ではなく現物で給付するというこの当たり前すぎるほど当たり前のことも、きちんと医療保険という形で保障されているのです。こうした高レベルの医療制度のおかげで、日本は世界に名だたる長寿国となり、高い保健医療水準を誇っています。しかし、この制度を維持するには多くの財源を必要とすること、人生100年時代と言われるほどの高齢化社会に向かって、必要な財源はますます増していくというのが、今後の問題です。その解決に向けては、保険料の負担増や保健医療の範囲の見直しなどが議論されており、こうした状況を聞くと、一枚の健康保険証の重みを感じます。
保険料負担はもちろんですが、私たちなりに日本の健康保険の仕組みを支えるためにできることを、考えていかなければなりません。そのためには、保険証はお守りとして、食生活や運動など生活習慣に気をつけて、「まず予防」を心がけたいですね。
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










