テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
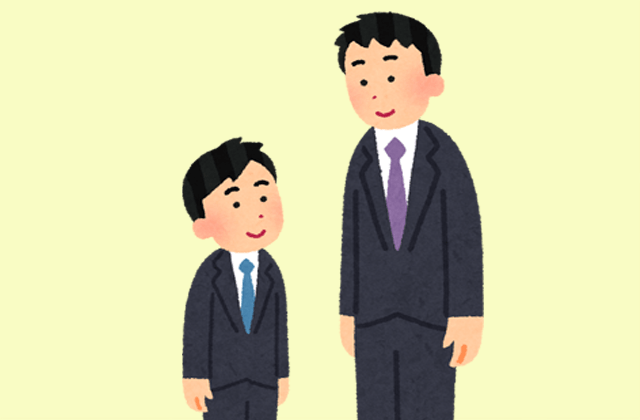
寒い地域ほど「平均身長が高い」ってホント?
アジア人は世界の中でも身長が低いというイメージはありませんか?逆にヨーロッパ系の人々は背が高く、体重や体つきも大きいというのが、固定概念として多くの人が抱く、人種の差だと思います。
2014年の調査では、日本人の平均身長は、17歳の男性の場合、170.7cm、同年齢の女性で157.9cmとなっています。戦後、栄養状況が飛躍的に改善した日本では、長らく平均身長が年々更新されていましたが、近年は変化がなくDNAの限界とも言われます。
対して、ヨーロッパ諸国の平均身長を見てみましょう。オランダが181.7cm、ノルウェーは179.9cmと、日本人より10cm以上高い国々が目につきます。ところが、スペインは173.9cm、ポルトガルが170.7cmと、あまり目を見張るような差のない地域もあるのです。
実はこの身長差の背景には、居住地域の寒さが関係していると言われています。
東南アジアに生息するマレーグマは140cm程度、北海道を中心に生息しているヒグマが200cm、ホッキョクグマが250cmと、寒い地域にいくほど、同じ種の動物でも平均サイズが大きくなっていることがわかります。
先ほどあげた日本や諸外国の平均身長もこれと同じことが言えます。アングロサクソン人やゲルマン人など、北方に住んでいた人々は身長も高く、体つきもガッシリとしています。対して、温暖な地中海などを拠点としていたラテン系の血を引く人々は、日本人とさほど身長の差がありません。
ではなぜ、寒冷地域の動物は体が大きくなるのでしょうか?それは、体内で発生させる熱と、それを逃がす体の表面積にありました。
体を大きくすると、その分、熱を逃がす表面積も広くなるように思いますが、同じ体の大きさを基準に考えた時、体重は体格に対して3乗、表面積は2乗という対比の基準があるのです。つまり、体が大きい方が、体重あたりの表面積は小さくなるのです。そのため、寒い地方に生息している動物はなるべく体を大きく成長させるように進化しました。
対して、赤道付近に住む生物は熱を放出させることに重きを置いた進化をしています。人類でも、南の島に住む人たちは身長が低いというイメージがあるかもしれませんが、耳や足、尾など、体温を逃がす部分は大きくなるということで、これは温暖な地域の生物の特徴といえるのです。
これは世界単位の話ではなく、日本国内でもあてはめることができます。2014年に行われた学校保健統計調査では、17歳の男性の平均身長で最も背が高かったのは石川県の171.7cm、次いで秋田県と富山県の171.4cmが続きます。逆に、身長が低い県は下から、沖縄県の168.8cm、福岡県の169.3cm、島根県、広島県、高知県の169.8cm。わずか3cmの違いではありますが、国内でもこうした特徴が出ているのです。
なぜ地域で身長差があるのか、漠然とした疑問でも、科学的な側面から見ていくと、意外な事実が出てくるものなのですね。
2014年の調査では、日本人の平均身長は、17歳の男性の場合、170.7cm、同年齢の女性で157.9cmとなっています。戦後、栄養状況が飛躍的に改善した日本では、長らく平均身長が年々更新されていましたが、近年は変化がなくDNAの限界とも言われます。
対して、ヨーロッパ諸国の平均身長を見てみましょう。オランダが181.7cm、ノルウェーは179.9cmと、日本人より10cm以上高い国々が目につきます。ところが、スペインは173.9cm、ポルトガルが170.7cmと、あまり目を見張るような差のない地域もあるのです。
実はこの身長差の背景には、居住地域の寒さが関係していると言われています。
ベルクマンの法則とは?
「ベルクマンの法則」は、1847年にドイツの生物学者であるベルクマンが発見した法則です。これは「寒い地域の動物の方が体が大きい」というもので、例としてあげるなら熊がわかりやすいでしょう。東南アジアに生息するマレーグマは140cm程度、北海道を中心に生息しているヒグマが200cm、ホッキョクグマが250cmと、寒い地域にいくほど、同じ種の動物でも平均サイズが大きくなっていることがわかります。
先ほどあげた日本や諸外国の平均身長もこれと同じことが言えます。アングロサクソン人やゲルマン人など、北方に住んでいた人々は身長も高く、体つきもガッシリとしています。対して、温暖な地中海などを拠点としていたラテン系の血を引く人々は、日本人とさほど身長の差がありません。
ではなぜ、寒冷地域の動物は体が大きくなるのでしょうか?それは、体内で発生させる熱と、それを逃がす体の表面積にありました。
恒温動物は体を大きくすることで熱を維持する
人は、自分の体内で熱を発生させて一定の体温を保つ「恒温動物」です。そのため、寒い地方ではいかに体温を維持できるかが生存の鍵となります。体重を増やし、体つきを大きくすることで、体内でより多くの熱を発生させることができるのです。体を大きくすると、その分、熱を逃がす表面積も広くなるように思いますが、同じ体の大きさを基準に考えた時、体重は体格に対して3乗、表面積は2乗という対比の基準があるのです。つまり、体が大きい方が、体重あたりの表面積は小さくなるのです。そのため、寒い地方に生息している動物はなるべく体を大きく成長させるように進化しました。
対して、赤道付近に住む生物は熱を放出させることに重きを置いた進化をしています。人類でも、南の島に住む人たちは身長が低いというイメージがあるかもしれませんが、耳や足、尾など、体温を逃がす部分は大きくなるということで、これは温暖な地域の生物の特徴といえるのです。
国内だけでも見られる地域と身長の関係
この「ベルクマンの法則」に似たものに、「アレンの法則」というものがあります。同じ種の個体でも、地域によって体格や成長に差があるというものです。これは世界単位の話ではなく、日本国内でもあてはめることができます。2014年に行われた学校保健統計調査では、17歳の男性の平均身長で最も背が高かったのは石川県の171.7cm、次いで秋田県と富山県の171.4cmが続きます。逆に、身長が低い県は下から、沖縄県の168.8cm、福岡県の169.3cm、島根県、広島県、高知県の169.8cm。わずか3cmの違いではありますが、国内でもこうした特徴が出ているのです。
なぜ地域で身長差があるのか、漠然とした疑問でも、科学的な側面から見ていくと、意外な事実が出てくるものなのですね。
<参考サイト>
・スクスクのっぽくん:身長データバンク
http://www.suku-noppo.jp/data/average_height_region.html
・スクスクのっぽくん:身長データバンク
http://www.suku-noppo.jp/data/average_height_region.html
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
葛飾北斎と応為の見事な「画狂人生」を絵と解説で辿る
テンミニッツ・アカデミー編集部
最近の話題は宇宙生命学…生命の起源に迫る可能性
川口淳一郎










