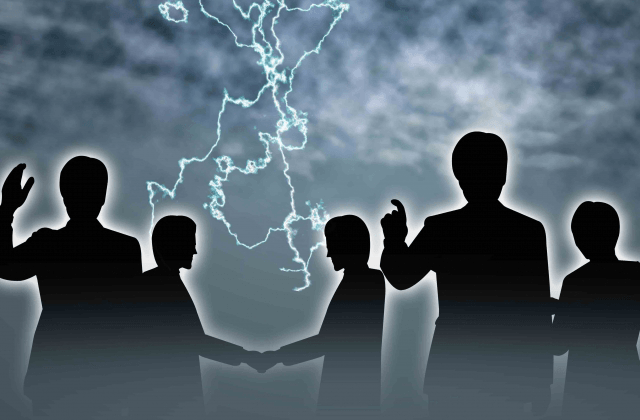
定額働かせ放題?「働き方法案」のブラックな中身
日本で働く多くの人々にとって、「過労」は大きな問題のひとつです。「過労死」という言葉は海外にも輸出され、「KAROSHI」とそのままの意味で使用されているそうです。
そんな日本では今、さまざまな形で働き方の見直しが行われています。政府も「働き方改革」と銘打って、課題の解消に取り組んでいますが、みなさんは「高度プロフェッショナル制度」をご存じでしょうか?
法案のひとつにあがっていた制度ですが、実はこの制度、「残業代ゼロ法案」とも呼ばれています。なぜ「働き方改革」で「残業代ゼロ」がうたわれているのでしょう?
高収入で高度な専門職に就いている人であれば、自分の判断で自由に働けるはず、というのが政府の考えです。休日の取り方、労働時間なども、個人の裁量に任せるというもの。その分、残業代や休日出勤の手当もなくなるわけです。
現在、「裁量労働制」という働き方の制度があります。こちらも、仕事量を個人の裁量に任せるというものですが、労働基準法の保護対象となるため、あらかじめ定められた「みなし時間」を超えた場合、残業代や休日手当が支給されるのです。「高度プロフェッショナル制度」は、この点で「裁量労働制」をより拡大させたものといえます。いくら専門職とはいえ、繁忙期には残業もありますし、上司に指示をされたら「自分は高度プロフェッショナル制度の該当者なので」と断るわけにも行きません。この制度を、「定額働かせ放題」と揶揄する声もあがっています。
仕事をしている間、その代価をもらうということは当たり前のことですが、仕事の成果から考えると、また違う側面が見えてきます。例えば、定時に退社する人と、仕事が終わらず残業をして帰る人、ともに同じ分の仕事の成果であれば、仕事が終わらず残業をした人の方に多く代金が支払われることになります。成果主義は必ずしもよいとはいえませんが、経営サイドにとっては頭の痛い課題でもあります。
ならば「働いた時間ではなく、成果に応じて賃金が決まる制度」を、と考えますよね。そうした側面へのフォローを売りにしていたのが「高度プロフェッショナル制度」だったのですが、法案の文面には「成果に応じて賃金が決まる」とは記載されていないのです。
また、「高度プロフェッショナル制度」と同時に、「残業上限規制法案」と「同一労働同一賃金」もあがっていました。「同一労働同一賃金」は正規社員と非正規社員の格差をなくすことが目的ですが、「残業上限規制法案」は問題が残っているといわれます。繁忙期の残業の上限「月100時間未満」を設定していますが、これは国が労災認定をする目安の過労死ラインと同じなのです。
多様な人の生活と人生があり、その分、働き方にもさまざまな形が存在していますが、労働や成果に対して、相応の対価をもらうことは当たり前のことです。どれだけ労働基準や法律が整備されている国でも、忙しければ残業もしますし、理想としているワーク・ライフ・バランスが崩れることもあります。
さまざまな方法や理論が提示され、社会全体を一度に変えようとすることは、難しいことなのかもしれませんが、現在の日本に合う制度を模索していく姿勢は、有権者であるわたしたちにも必要ではないでしょうか。
そんな日本では今、さまざまな形で働き方の見直しが行われています。政府も「働き方改革」と銘打って、課題の解消に取り組んでいますが、みなさんは「高度プロフェッショナル制度」をご存じでしょうか?
法案のひとつにあがっていた制度ですが、実はこの制度、「残業代ゼロ法案」とも呼ばれています。なぜ「働き方改革」で「残業代ゼロ」がうたわれているのでしょう?
専門職には残業代も労働基準法もいらない?
東洋経済ONLINEの記事でコメントしている弁護士によると、この「高度プロフェッショナル制度」は、平均年収の3倍以上、つまり年収1075万円以上の収入があり、高度な専門職に就いている労働者が対象となっているとのこと。具体的には、為替のトレーダー、研究職などが該当の職業です。この制度の該当者となると、労働基準法の保護外となり、残業代や休日出勤の代金を支払う必要がなくなります。高収入で高度な専門職に就いている人であれば、自分の判断で自由に働けるはず、というのが政府の考えです。休日の取り方、労働時間なども、個人の裁量に任せるというもの。その分、残業代や休日出勤の手当もなくなるわけです。
現在、「裁量労働制」という働き方の制度があります。こちらも、仕事量を個人の裁量に任せるというものですが、労働基準法の保護対象となるため、あらかじめ定められた「みなし時間」を超えた場合、残業代や休日手当が支給されるのです。「高度プロフェッショナル制度」は、この点で「裁量労働制」をより拡大させたものといえます。いくら専門職とはいえ、繁忙期には残業もありますし、上司に指示をされたら「自分は高度プロフェッショナル制度の該当者なので」と断るわけにも行きません。この制度を、「定額働かせ放題」と揶揄する声もあがっています。
残業代のあり方と、課題
2017年10月現在、「高度プロフェッショナル制度」は衆議院解散によって廃案となりましたが、度々残業代を押さえる法案が作られます。その理由のひとつにあげられるのは、日本の長時間労働は「残業代」にあるという見方が存在していることです。残業代は、それぞれの会社のルールによっても異なりますが、会社にいればいるほど額があがっていくものです。仕事をしている間、その代価をもらうということは当たり前のことですが、仕事の成果から考えると、また違う側面が見えてきます。例えば、定時に退社する人と、仕事が終わらず残業をして帰る人、ともに同じ分の仕事の成果であれば、仕事が終わらず残業をした人の方に多く代金が支払われることになります。成果主義は必ずしもよいとはいえませんが、経営サイドにとっては頭の痛い課題でもあります。
ならば「働いた時間ではなく、成果に応じて賃金が決まる制度」を、と考えますよね。そうした側面へのフォローを売りにしていたのが「高度プロフェッショナル制度」だったのですが、法案の文面には「成果に応じて賃金が決まる」とは記載されていないのです。
また、「高度プロフェッショナル制度」と同時に、「残業上限規制法案」と「同一労働同一賃金」もあがっていました。「同一労働同一賃金」は正規社員と非正規社員の格差をなくすことが目的ですが、「残業上限規制法案」は問題が残っているといわれます。繁忙期の残業の上限「月100時間未満」を設定していますが、これは国が労災認定をする目安の過労死ラインと同じなのです。
働き方を見直すには
「働き方」に多くの人の注目が集まり、長時間労働の是非や過労死事件のニュースが頻繁に取り上げられるなど、多くの人々の意識は確かに変わろうとしています。「高度プロフェッショナル制度」も、一昔前であればさしてニュースにもならず、法案が通るということもあったかもしれません。多様な人の生活と人生があり、その分、働き方にもさまざまな形が存在していますが、労働や成果に対して、相応の対価をもらうことは当たり前のことです。どれだけ労働基準や法律が整備されている国でも、忙しければ残業もしますし、理想としているワーク・ライフ・バランスが崩れることもあります。
さまざまな方法や理論が提示され、社会全体を一度に変えようとすることは、難しいことなのかもしれませんが、現在の日本に合う制度を模索していく姿勢は、有権者であるわたしたちにも必要ではないでしょうか。
<参考サイト>
・東洋経済ONLINE:「働き方法案」に潜むブラック要素を検証する
http://toyokeizai.net/articles/-/189579
・東洋経済ONLINE:「働き方法案」に潜むブラック要素を検証する
http://toyokeizai.net/articles/-/189579
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







