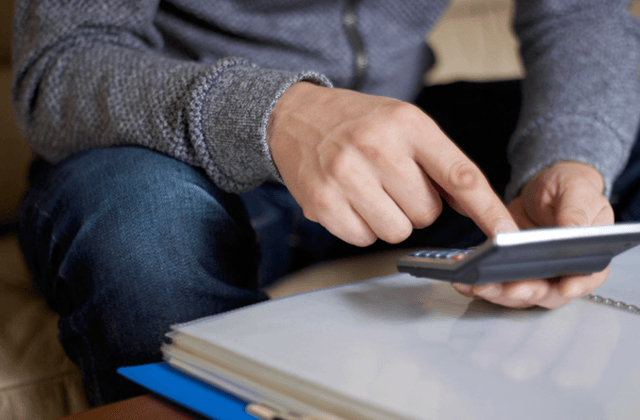
定年後に支払う必要のある「3つの税金」とは?
65歳以上人口約3627万人。日本の高齢化率(65歳以上人口/総人口)は2022年9月15日に29.1%に達し、前年と比較して0.3ポイント上昇、過去最高を記録しました。政府が提唱する「人生100年時代」は刻々と迫りつつあります。ここ数年は、老後と呼べる年齢が何歳になるのか、変化の瀬戸際にありますが、気になるのはやはり家計の状況。定年後の暮らしに関して、直近の動向を調べてみました。
次に、令和4年度版「高齢社会白書」をのぞいてみると、経済的な暮らし向きについて「心配ない」と答えている65歳以上の割合は68.5%に上ります。65歳以上の者だけ、あるいは18歳未満の未婚者が加わった高齢者世帯の平均所得は312.6万円で、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いたその他世帯(664.5 万 円)の約5割となっています。
公的年金・恩給を受給している高齢者世帯について、公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合を見ると、公的年金・恩給が家計収入の全てとなっている世帯が半数以上となっていることから、将来的には今後の制度において、不安は大きいと言えるのではないでしょうか。
令和4年度版生命保険文化センターによる「生活保障に関する調査」を参照してみましょう。
調査では、老後生活に不安を感じる人の割合は82.2%。何が不安なのかというと、「公的年金だけでは不十分」79.4%を占め、「日常生活に支障が出る」57.3%、「自助努力による準備が不足する」36.3%の順になります。
回答者が望んでいる老後の生活水準は、「つつましい生活」が63.9%。現役時代と同程度やそれ以上を望む割合は平成5年をピークに平成22年で底を打ち、老後の最低日常生活費として具体的には「20~25万円未満」を望む声が最多。老後のゆとりのための上乗せ額も「10~15万円未満」が多く、10万円未満でよいとする層を足すと5割以上を占めます。
夫婦二人で月22万円、ゆとりある老後の暮らしには月34.9万円。そのために公的年金以外に個人年金も…という流れになるようですが、厚生労働省のモデル年金は40年間会社勤めの夫と同じ年月専業主婦の夫婦を想定して、夫婦で月額238,125円となっています。仮に現状の年金制度がこの先ずっと続けば、それほど心配する必要はないのかもしれませんが、さて今後どうなるのでしょう。
まず、所得税は、所得に応じてその都度支払うものですが、サラリーマンはあらかじめ1年の総収入を月割りにして源泉徴収されています。退職後、1か月以上ブランクがあると、納め過ぎということになります。もちろん納め過ぎ分は還付されますが、手続きの方法は同年に再就職したかしなかったかで変わってきます。年内に再就職した場合は、再就職先で年末調整を、再就職しなかった場合は、翌年の確定申告を行う必要があります。
住民税は6月が期のはじまりとなるため、退職時期が1月から5月の人と6月以降の人で支払い方法が異なります。前者では退職時に一括徴収され、6月以降に退職の場合は一括か分割かを選べます。なお、住民税は「前年度の収入」に対してかかるものなので、退職した翌年も支払いの必要があります。忘れないようにしましょう。
なお、住居や土地にかかる固定資産税は、収入の有無にかかわらず、退職後も地価評価に応じて支払っていく必要があります。相続税も同様です。これらの税金が回りまわって公的年金になっていくのですから、あまり渋い顔はできませんね。
意外にも「心配がない」高齢者の暮らし向き
まず国際比較を見てみましょう。令和2年度、日本、アメリカ、ドイツ、スウェーデンで同時に行われた調査によると、「現在の老後の生活に満足している」高齢者の割合は、アメリカ94.6%、スウェーデン92.2%、ドイツ91.6%、日本81.5%となっています。次に、令和4年度版「高齢社会白書」をのぞいてみると、経済的な暮らし向きについて「心配ない」と答えている65歳以上の割合は68.5%に上ります。65歳以上の者だけ、あるいは18歳未満の未婚者が加わった高齢者世帯の平均所得は312.6万円で、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いたその他世帯(664.5 万 円)の約5割となっています。
公的年金・恩給を受給している高齢者世帯について、公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合を見ると、公的年金・恩給が家計収入の全てとなっている世帯が半数以上となっていることから、将来的には今後の制度において、不安は大きいと言えるのではないでしょうか。
夫婦で月22万円、ゆとり資金を合わせた35万円を確保できるか
2019年6月、金融庁の報告書によって老後資金が2,000万円不足すると報告され大炎上したことも記憶に新しいところ。経済産業省の試算では2,895万円の貯蓄が必要だという報告もありました。はたして老後の資金は、実際いくらあれば足りるのでしょう?令和4年度版生命保険文化センターによる「生活保障に関する調査」を参照してみましょう。
調査では、老後生活に不安を感じる人の割合は82.2%。何が不安なのかというと、「公的年金だけでは不十分」79.4%を占め、「日常生活に支障が出る」57.3%、「自助努力による準備が不足する」36.3%の順になります。
回答者が望んでいる老後の生活水準は、「つつましい生活」が63.9%。現役時代と同程度やそれ以上を望む割合は平成5年をピークに平成22年で底を打ち、老後の最低日常生活費として具体的には「20~25万円未満」を望む声が最多。老後のゆとりのための上乗せ額も「10~15万円未満」が多く、10万円未満でよいとする層を足すと5割以上を占めます。
夫婦二人で月22万円、ゆとりある老後の暮らしには月34.9万円。そのために公的年金以外に個人年金も…という流れになるようですが、厚生労働省のモデル年金は40年間会社勤めの夫と同じ年月専業主婦の夫婦を想定して、夫婦で月額238,125円となっています。仮に現状の年金制度がこの先ずっと続けば、それほど心配する必要はないのかもしれませんが、さて今後どうなるのでしょう。
退職後も同様に払う税金
退職後も続く経済的負担として、支払わなければならない税金があります。大きく分けて所得税、住民税、固定資産税の3種類を順番に見ていきましょう。まず、所得税は、所得に応じてその都度支払うものですが、サラリーマンはあらかじめ1年の総収入を月割りにして源泉徴収されています。退職後、1か月以上ブランクがあると、納め過ぎということになります。もちろん納め過ぎ分は還付されますが、手続きの方法は同年に再就職したかしなかったかで変わってきます。年内に再就職した場合は、再就職先で年末調整を、再就職しなかった場合は、翌年の確定申告を行う必要があります。
住民税は6月が期のはじまりとなるため、退職時期が1月から5月の人と6月以降の人で支払い方法が異なります。前者では退職時に一括徴収され、6月以降に退職の場合は一括か分割かを選べます。なお、住民税は「前年度の収入」に対してかかるものなので、退職した翌年も支払いの必要があります。忘れないようにしましょう。
なお、住居や土地にかかる固定資産税は、収入の有無にかかわらず、退職後も地価評価に応じて支払っていく必要があります。相続税も同様です。これらの税金が回りまわって公的年金になっていくのですから、あまり渋い顔はできませんね。
<参考サイト>
・総務省統計局:1.高齢者の人口
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1321.html
・内閣府:令和2年度度 第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果
https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/r02/zentai/pdf_index.html
・公益財団法人 生命保険文化センター:令和元年度「生活保障に関する調査」
https://www.jili.or.jp/research/chousa/8944.html
・内閣府:令和4年版高齢社会白書
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html
・総務省統計局:1.高齢者の人口
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1321.html
・内閣府:令和2年度度 第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果
https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/r02/zentai/pdf_index.html
・公益財団法人 生命保険文化センター:令和元年度「生活保障に関する調査」
https://www.jili.or.jp/research/chousa/8944.html
・内閣府:令和4年版高齢社会白書
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/04pdf_index.html
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子
毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング
長谷川眞理子







