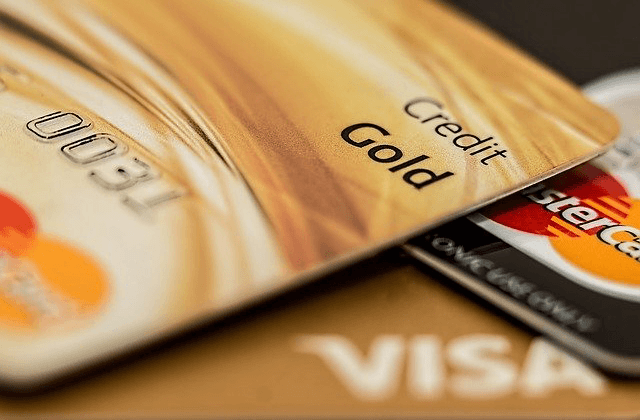
日本は後進国?キャッシュレス化が進む海外
消費増税後のポイント還元事業によって、日本でもじわじわと広がっているキャッシュレス化。お隣の中国ではその比較にならない勢いでキャッシュレス化が進んでいるとよく報道されています。中国をはじめ世界の違いに焦点を当てて、日本のキャッシュレス化の動向を探ります。
経済産業省によると、韓国が89.1パーセント、中国が60パーセント、カナダが55.4パーセントと続き、アメリカが45パーセント、インドが38.4パーセントという数字が並ぶ中で、なんと日本は18.4パーセント。これは2015年時点のデータなので、現状を正確に知ることはできませんが、日本のキャッシュレス化が非常に遅れていることがよくわかります。
ちなみにドイツは14.9パーセントで日本よりもさらに低い普及率でした。先進国の中で、日本とドイツだけ際立って現金主義が強いようです。
日本のキャッシュレス市場で最大シェアを誇るPayPayも海外のお店ではほとんど利用できません。ただし、PayPayは、中国のAlipayと提携し、日本国内でAlipayが使えるように申請しているPayPay加盟店では、AlipayのQRコード決済が可能になりました。
中国には二大QRコード決済サービスがあり、そのうちの一つがAlipayです。そしてもう一つがWechat Payです。
海外ではこのコンタクトレス決済が主流です。ただし、日本で使われているコンタクトレス決済はほとんど海外では使うことができません。なぜなら、タッチ決済の規格が異なるからです。日本では「Felica」という規格が主流なのに対して、海外は「NFC Pay」が広く普及しています。
海外でメジャーなキャッシュレス決済の方法は、VisaやMastercardなど電波アイコン(非接触対応マーク)がついているクレジットカードによるタッチ決済です。日本でもちょっとずつ、この電波アイコンのあるクレジットカードによるタッチ決済が広がってきています。
同じキャッシュレスとはいえ、QRコード決済にしてもコンタクトレス決済にしても、日本と海外では大きな違いがあることが分かりましたね。今後、この溝をどのように埋めていくかが課題になっています。キャッシュレス後進国だからこその強みを活かして、日本と世界の消費者の利便性を追求した、日本ならではのキャッシュレス決済のサービスを展開していってほしいものです。
日本とドイツの意外な共通点
2019年はキャッシュレス元年とも言われ、日本でもキャッシュレス化が拡大しつつあります。とはいえ、まだまだキャッシュレス後進国と言われている日本。その理由は、世界の普及率と比較すれば一目瞭然です。経済産業省によると、韓国が89.1パーセント、中国が60パーセント、カナダが55.4パーセントと続き、アメリカが45パーセント、インドが38.4パーセントという数字が並ぶ中で、なんと日本は18.4パーセント。これは2015年時点のデータなので、現状を正確に知ることはできませんが、日本のキャッシュレス化が非常に遅れていることがよくわかります。
ちなみにドイツは14.9パーセントで日本よりもさらに低い普及率でした。先進国の中で、日本とドイツだけ際立って現金主義が強いようです。
QRコード決済は海外では使えない?
ところで日本で普及しているQRコードを読み取るスマホ決済は海外ではそれほどメジャーではないことをご存知でしたか。そのため、残念なことに海外ではほとんど使えません。日本のキャッシュレス市場で最大シェアを誇るPayPayも海外のお店ではほとんど利用できません。ただし、PayPayは、中国のAlipayと提携し、日本国内でAlipayが使えるように申請しているPayPay加盟店では、AlipayのQRコード決済が可能になりました。
中国には二大QRコード決済サービスがあり、そのうちの一つがAlipayです。そしてもう一つがWechat Payです。
海外でメジャーなキャッシュレス決済
キャッシュレス決済にはQRコード決済の他にコンタクトレス決済があります。コンタクトレス決済は分かりやすい例がSuicaやPASMOなどの交通系ICカード。つまり、専用リーダーにかざすだけで完了する決済方法です。海外ではこのコンタクトレス決済が主流です。ただし、日本で使われているコンタクトレス決済はほとんど海外では使うことができません。なぜなら、タッチ決済の規格が異なるからです。日本では「Felica」という規格が主流なのに対して、海外は「NFC Pay」が広く普及しています。
海外でメジャーなキャッシュレス決済の方法は、VisaやMastercardなど電波アイコン(非接触対応マーク)がついているクレジットカードによるタッチ決済です。日本でもちょっとずつ、この電波アイコンのあるクレジットカードによるタッチ決済が広がってきています。
同じキャッシュレスとはいえ、QRコード決済にしてもコンタクトレス決済にしても、日本と海外では大きな違いがあることが分かりましたね。今後、この溝をどのように埋めていくかが課題になっています。キャッシュレス後進国だからこその強みを活かして、日本と世界の消費者の利便性を追求した、日本ならではのキャッシュレス決済のサービスを展開していってほしいものです。
<参考サイト>
・【図解・経済】各国のキャッシュレス決済比率(2019年8月):時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_eco_kinyushoken20190816j-05-w380
・PayPay「海外で日本のQRコード決済は使える?インバウンド対策にも役立つキャッシュレス決済!」
https://paypay.ne.jp/store-media/qr/0020_qr_overseas/
・「海外との違いを知ろう!国内でのタッチ決済の今と未来」
https://squareup.com/jp/ja/townsquare/what-is-nfc-payment/japan-trends
・【図解・経済】各国のキャッシュレス決済比率(2019年8月):時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_eco_kinyushoken20190816j-05-w380
・PayPay「海外で日本のQRコード決済は使える?インバウンド対策にも役立つキャッシュレス決済!」
https://paypay.ne.jp/store-media/qr/0020_qr_overseas/
・「海外との違いを知ろう!国内でのタッチ決済の今と未来」
https://squareup.com/jp/ja/townsquare/what-is-nfc-payment/japan-trends
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







