テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
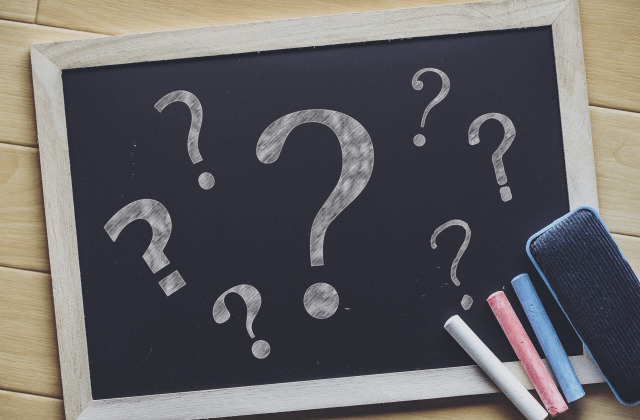
日本の迷信はどのようにして生まれたのか?
日本にはたくさんの迷信があります。いわゆる“お雇い外国人”の大学教師として来日し、近代化以前の明治日本を“外の視点”をもって体験したアメリカの教育者・宗教家にして日本学者のW.E.グリフィスは、「日本の迷信」について以下のように述べています。
「(日本の迷信には)明らかに道徳上、教育上の目的をもったもの、すなわち身なりのよさ、なさけ深さの教訓を教えこんだり、家事などの清潔や正確さの習慣をつけるためのものがある。天気の予想や、火事などの災難を防ぐために前もって知らせるようなものもある」
そのような日本の迷信は、どのようにして生まれたのでしょうか。由来をたどれる例を挙げながら、考察してみたいと思います。
『涅槃経』という経典では、仏教の開祖である仏陀(ぶっだ)がなくなるシーンは、「頭を来北に向けて」休まれたと書かれています。日本ではその箇所が勘違いされ、人が亡くなるときは頭を来北に向けて寝かす=「北枕」とされました。しかしインドでは、北が理想の方角であるため、むしろいわゆる北枕は良い寝方とされています。
2)茗荷を食べると物忘れがひどくなる
仏陀の弟子の一人の周利槃特(しゅりはんどく)は非常に物覚えが悪く、自分の名前すら忘れるほどでした。そこで仏陀の助言を受けて、名前を書いた板を背負うことになりました。そして、周利槃特の死後、彼の墓場に生えた見慣れない草が、“名”を“荷”(にな)った生前の行いにあやかり「名荷」と名付けられ、転じて迷信の由来になったといわれています。ただし、「子どもが茗荷を食べると物忘れが良くなる」といった、転じた迷信が残る地方もあります。
3)茶碗を叩くと餓鬼が寄る
餓鬼(がき)は仏教用語で、六道の一つである餓鬼道に落ちた亡者を指します。そして餓鬼道では、前世の業によって飢えと渇きに苦しむ世界とされています。そのため、餓鬼と食・空腹・欲求などの親和性が高くなり、食べ物を食に関する行為や欲深い行為への戒めや教訓、行儀作法や習慣の継承として、餓鬼のメタファーはよく使われ、それら由来の迷信や教訓も多数発生しました。
庚申(こうしん)とは、陰陽五行説に由来する干支の一つです。干支は暦や方位に用いられたことで、年回りや年中行事、さらには方位の吉凶の概念などとも深く関係していくことになります。さらに大元の概念に、道教があります。道教では、人の体内にいる三尸(さんし)という虫が庚申の日ごとに体内から抜け出して天に上り、その人の罪を天帝に告げて早死にさせようとすると考えられていました。そこで、虫を天に昇らせないように、庚申の日は夜通し起きて過ごすことが奨励されたことに由来するといわれています。
2)鬼門に玄関や水回りを造ってはいけない
鬼門(きもん)とは、陰陽道における邪悪な鬼が出入りするとして万事に忌み嫌われた艮(うしとら)の方位を指し、方角では北東に位置します。鬼門に玄関やトイレ・浴室・台所といった水回り、さらには倉なども含め建物全般を造ることによって、病人が絶えない、主人が死ぬなど、その家に不幸や災難がおよぶといわれました。
3)仏滅の日に漁具を新調しない
仏滅(ぶつめつ)とは、六曜(暦注の一種で、日の吉凶をみるのに使われる。先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の六個の星からなる)の一つです。六曜の思想は中国から伝わりましたが、日本では特に江戸時代末期から流布し、さまざまな迷信の由来となります。特に仏滅は死・殺生・不吉なものと親和性が高いとされ、ひるがえって、生や聖、吉や祝に関することから避けられるようになります。現代でも、婚礼や葬礼などの儀式の日取りを決めるときに、大きな影響を及ぼしています。
日本では、人は眠ると魂が肉体を離れて遊びに出るという考え方がありました。そのため、急に強く起こしてしまうと、目が覚める前に魂が肉体に戻れなくなってしましい、起こされた人が死んでしまうといった、日本的な死生観に由来した迷信です。
2)子どもは頭に籠を載せて運んではいけない
日本では、昔から背が高くなりたい気持が一般的に共有されています。そのため、成長を押えるような不吉なことはすべて避けるべき行為とされたことに由来する迷信です。同様の迷信に、子どもに桶や笊を冠らせると丈が伸びない、立ち臼に子どもが上ると背が伸びない、自分で背の高さを測ってはいけない、などがあります。
3)いたちが一度鳴くと火事になる
日本では、火事が大きな災厄の一つであったため、火事に関する迷信が多数発生しました。他にも、雄鶏が夜大きな声で鳴くとき、犬が建物の屋根に登るときなどは火事の予兆とされ、木瓜の花を仏に供えると家が焼ける、彼岸花を家に飾ると火事になるなど、火事を避けるための迷信も各地に残っています。ちなみに、いたちが一度鳴いた場合は、左手に柄杓を持って水を三杯かけねばならないとされています。
さて、最後に取り上げた3選は、冒頭で紹介したグリフィスが聞いて書き留めた迷信です。グリフィスはその由来を日本的な精神にあるようにみていますが、その前に紹介した仏教由来・3選と日本的精神由来・3選のように、厳密に日本由来の迷信を探すことは、古代をさかのぼっても難しいように感じます。
なぜなら、文字が伝わる以前から日本的精神から生まれた迷信はあったものの、文字とともに様々な外来文化が伝来し、それらが混ざり合って生まれた迷信が、現在に伝わっていると考えられるからです。とはいえ、いわゆる江戸期の鎖国を経て、独自の文化的な醸成がされていた明治初期の日本を、外からの新鮮な視点で捉えたグリフィスの感性から、日本の迷信の生まれてきた背景が、そこはかと感じられるようにも思えます。
なお、グリフィスは日本の迷信を、「すべて比較的無害である」と表しています。迷信とのつきあい方も自由に選ぶことができる現代、迷信に惑わされることなく、迷信を教訓や良い習慣の伝承に役立てたり、話のネタや文化的考証の貴重な資料としたりと、活用してみることもおもしろいかもしれません。
「(日本の迷信には)明らかに道徳上、教育上の目的をもったもの、すなわち身なりのよさ、なさけ深さの教訓を教えこんだり、家事などの清潔や正確さの習慣をつけるためのものがある。天気の予想や、火事などの災難を防ぐために前もって知らせるようなものもある」
そのような日本の迷信は、どのようにして生まれたのでしょうか。由来をたどれる例を挙げながら、考察してみたいと思います。
仏教由来・3選
1)北枕はせぬもの『涅槃経』という経典では、仏教の開祖である仏陀(ぶっだ)がなくなるシーンは、「頭を来北に向けて」休まれたと書かれています。日本ではその箇所が勘違いされ、人が亡くなるときは頭を来北に向けて寝かす=「北枕」とされました。しかしインドでは、北が理想の方角であるため、むしろいわゆる北枕は良い寝方とされています。
2)茗荷を食べると物忘れがひどくなる
仏陀の弟子の一人の周利槃特(しゅりはんどく)は非常に物覚えが悪く、自分の名前すら忘れるほどでした。そこで仏陀の助言を受けて、名前を書いた板を背負うことになりました。そして、周利槃特の死後、彼の墓場に生えた見慣れない草が、“名”を“荷”(にな)った生前の行いにあやかり「名荷」と名付けられ、転じて迷信の由来になったといわれています。ただし、「子どもが茗荷を食べると物忘れが良くなる」といった、転じた迷信が残る地方もあります。
3)茶碗を叩くと餓鬼が寄る
餓鬼(がき)は仏教用語で、六道の一つである餓鬼道に落ちた亡者を指します。そして餓鬼道では、前世の業によって飢えと渇きに苦しむ世界とされています。そのため、餓鬼と食・空腹・欲求などの親和性が高くなり、食べ物を食に関する行為や欲深い行為への戒めや教訓、行儀作法や習慣の継承として、餓鬼のメタファーはよく使われ、それら由来の迷信や教訓も多数発生しました。
中国思想由来・3選
1)庚申の夜に眠ってはいけない庚申(こうしん)とは、陰陽五行説に由来する干支の一つです。干支は暦や方位に用いられたことで、年回りや年中行事、さらには方位の吉凶の概念などとも深く関係していくことになります。さらに大元の概念に、道教があります。道教では、人の体内にいる三尸(さんし)という虫が庚申の日ごとに体内から抜け出して天に上り、その人の罪を天帝に告げて早死にさせようとすると考えられていました。そこで、虫を天に昇らせないように、庚申の日は夜通し起きて過ごすことが奨励されたことに由来するといわれています。
2)鬼門に玄関や水回りを造ってはいけない
鬼門(きもん)とは、陰陽道における邪悪な鬼が出入りするとして万事に忌み嫌われた艮(うしとら)の方位を指し、方角では北東に位置します。鬼門に玄関やトイレ・浴室・台所といった水回り、さらには倉なども含め建物全般を造ることによって、病人が絶えない、主人が死ぬなど、その家に不幸や災難がおよぶといわれました。
3)仏滅の日に漁具を新調しない
仏滅(ぶつめつ)とは、六曜(暦注の一種で、日の吉凶をみるのに使われる。先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の六個の星からなる)の一つです。六曜の思想は中国から伝わりましたが、日本では特に江戸時代末期から流布し、さまざまな迷信の由来となります。特に仏滅は死・殺生・不吉なものと親和性が高いとされ、ひるがえって、生や聖、吉や祝に関することから避けられるようになります。現代でも、婚礼や葬礼などの儀式の日取りを決めるときに、大きな影響を及ぼしています。
日本的精神由来・3選
1)寝ている人を急に強く起してはいけない日本では、人は眠ると魂が肉体を離れて遊びに出るという考え方がありました。そのため、急に強く起こしてしまうと、目が覚める前に魂が肉体に戻れなくなってしましい、起こされた人が死んでしまうといった、日本的な死生観に由来した迷信です。
2)子どもは頭に籠を載せて運んではいけない
日本では、昔から背が高くなりたい気持が一般的に共有されています。そのため、成長を押えるような不吉なことはすべて避けるべき行為とされたことに由来する迷信です。同様の迷信に、子どもに桶や笊を冠らせると丈が伸びない、立ち臼に子どもが上ると背が伸びない、自分で背の高さを測ってはいけない、などがあります。
3)いたちが一度鳴くと火事になる
日本では、火事が大きな災厄の一つであったため、火事に関する迷信が多数発生しました。他にも、雄鶏が夜大きな声で鳴くとき、犬が建物の屋根に登るときなどは火事の予兆とされ、木瓜の花を仏に供えると家が焼ける、彼岸花を家に飾ると火事になるなど、火事を避けるための迷信も各地に残っています。ちなみに、いたちが一度鳴いた場合は、左手に柄杓を持って水を三杯かけねばならないとされています。
さて、最後に取り上げた3選は、冒頭で紹介したグリフィスが聞いて書き留めた迷信です。グリフィスはその由来を日本的な精神にあるようにみていますが、その前に紹介した仏教由来・3選と日本的精神由来・3選のように、厳密に日本由来の迷信を探すことは、古代をさかのぼっても難しいように感じます。
なぜなら、文字が伝わる以前から日本的精神から生まれた迷信はあったものの、文字とともに様々な外来文化が伝来し、それらが混ざり合って生まれた迷信が、現在に伝わっていると考えられるからです。とはいえ、いわゆる江戸期の鎖国を経て、独自の文化的な醸成がされていた明治初期の日本を、外からの新鮮な視点で捉えたグリフィスの感性から、日本の迷信の生まれてきた背景が、そこはかと感じられるようにも思えます。
なお、グリフィスは日本の迷信を、「すべて比較的無害である」と表しています。迷信とのつきあい方も自由に選ぶことができる現代、迷信に惑わされることなく、迷信を教訓や良い習慣の伝承に役立てたり、話のネタや文化的考証の貴重な資料としたりと、活用してみることもおもしろいかもしれません。
<参考文献>
・『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)
・『明治日本体験記』(W.E.グリフィス著、山下英一訳、東洋文庫)
・『仏教、本当の教え』(植木雅俊著、中公新書)
・『イラスト日本の迷信・妖怪事典 2』(高村忠範文・絵、汐文社)
・『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)
・『明治日本体験記』(W.E.グリフィス著、山下英一訳、東洋文庫)
・『仏教、本当の教え』(植木雅俊著、中公新書)
・『イラスト日本の迷信・妖怪事典 2』(高村忠範文・絵、汐文社)
人気の講義ランキングTOP20










