テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
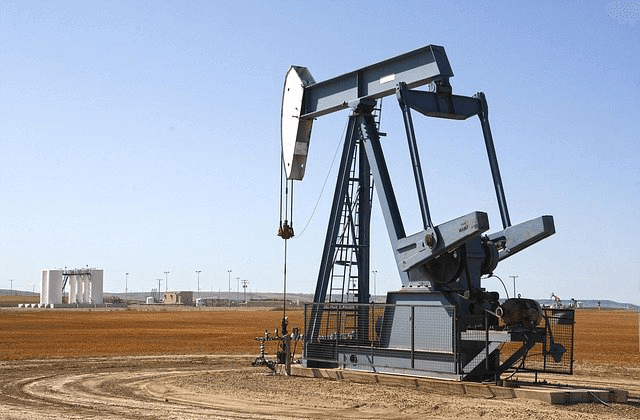
石油は本当に枯渇するのか?
1970~80年代の2度のオイル・ショックの頃から、「あと40年程で石油が枯渇する!?」と懸念され、石油は世界中で資源問題の中心に君臨してきました。
あれから約40年以上経った現在。石油の使用量は世界的に一向に減少しないどころかさらなる需要と消費が増加しているにも関わらず、有限である石油は枯渇することなく、第一級・第一線の経済資源であり続けています。
さらには、「あと40年程で石油が枯渇する!?」が、変わることなく今日的な喫緊の課題として取り沙汰されています。
1)「絶対埋蔵量」(「原始埋蔵量」とも)
まず、地球上に存在する原油の総量を、「絶対埋蔵量」といいます。ただし、現代の技術でも「絶対埋蔵量」の全存在の確認はできておらず、今後も難しいとされています。
2)「可採埋蔵量」(「確認埋蔵量」とも)
次に、「絶対埋蔵量」のうち“採掘すれば採算が取れるだろう”と判断された油田の埋蔵量を、「可採埋蔵量」といいます。なお、技術や経済的理由によって、採掘しない場合も多々あります。
3)「可採年数」
さらに、《「可採埋蔵量」÷年産量(1年間の石油産出量)=「可採年数」》といいます。この「可採年数」が、いわゆる「石油はあと○○年で枯渇する!?」の○○年に流用されることとなっています。
4)「確認可採埋蔵量」≒「埋蔵量」
なお、「可採埋蔵量」の中には、“すでに採掘してしまった分”も含まれます。そのため、《「可採埋蔵量」-“すでに採掘してしまった分”=「確認可採埋蔵量」》となります。
そして、一般的に「埋蔵量」という用語が取り沙汰される際は、この「確認可採埋蔵量」を指している場合が多いといわれています。
石油の埋蔵量について、京都大学大学院人間・環境学研究科教授の鎌田浩毅氏は、1)技術進歩や石油探査に対する投資によって増減する、2)原油価格が急騰した場合、以前よりもコストをかけて低品位であっても経済的に成り立つ――結果、3)埋蔵量は時間とともに増加する――、と述べています。
さらに、石油に限ったことではありませんが、地下資源は枯渇するほど価値が上がります。
そのため、石油の枯渇問題やオイル・ショックのような危機が起こる度に、新たな探査開発や資金投入、さらにはそれらによる技術革新が進むこととなり、結果として逆に埋蔵量が増加するというパラドックスが生じることにもあります。
また、同様にたとえ原油が地下にあったとしても、石油の需要がなくなれば、「(絶対埋蔵量としての)原油はあっても、(可採埋蔵量としての)石油は枯渇する」事態となるかもしれません。
しかしながら、今後もしばらく第一級・第一線の経済資源であり続けると予測される石油の需要が枯渇するような社会状況は、あまり現実的ではありません。そのため、今後もしばらく、石油は枯渇することなく供給されることが予想されます。
しかしながら当然のこととして、使えば使うほど絶対埋蔵量は減少します。また、そもそも論として、石油のような地下資源は、個人や企業、国や現代社会にさえとどまることなく、“持続する世界の共有財産(コモンズ)”です。
持続可能な未来のためにも、環境保全や国際政治のバランス等を考慮した意識や技術を革新し、正しく適切に無駄なく使うことが、今を生きる全人類に求められています。
あれから約40年以上経った現在。石油の使用量は世界的に一向に減少しないどころかさらなる需要と消費が増加しているにも関わらず、有限である石油は枯渇することなく、第一級・第一線の経済資源であり続けています。
さらには、「あと40年程で石油が枯渇する!?」が、変わることなく今日的な喫緊の課題として取り沙汰されています。
絶対・可採・確認可採。種々の石油埋蔵量
石油資源の枯渇問題を考えるとき、いくつもある“石油埋蔵量に関する用語”の整理をすると、わかりやすくなます。1)「絶対埋蔵量」(「原始埋蔵量」とも)
まず、地球上に存在する原油の総量を、「絶対埋蔵量」といいます。ただし、現代の技術でも「絶対埋蔵量」の全存在の確認はできておらず、今後も難しいとされています。
2)「可採埋蔵量」(「確認埋蔵量」とも)
次に、「絶対埋蔵量」のうち“採掘すれば採算が取れるだろう”と判断された油田の埋蔵量を、「可採埋蔵量」といいます。なお、技術や経済的理由によって、採掘しない場合も多々あります。
3)「可採年数」
さらに、《「可採埋蔵量」÷年産量(1年間の石油産出量)=「可採年数」》といいます。この「可採年数」が、いわゆる「石油はあと○○年で枯渇する!?」の○○年に流用されることとなっています。
4)「確認可採埋蔵量」≒「埋蔵量」
なお、「可採埋蔵量」の中には、“すでに採掘してしまった分”も含まれます。そのため、《「可採埋蔵量」-“すでに採掘してしまった分”=「確認可採埋蔵量」》となります。
そして、一般的に「埋蔵量」という用語が取り沙汰される際は、この「確認可採埋蔵量」を指している場合が多いといわれています。
消費すれば増加する?石油のパラドックス
以上から、たとえ石油を消費しても、“これから採掘可能な埋蔵量”である「確認可採埋蔵量」≒「埋蔵量」の増加分がある限り、いわゆる「石油はあと○○年で枯渇」の○○年も、一定年数が保たれることがみえてきました。石油の埋蔵量について、京都大学大学院人間・環境学研究科教授の鎌田浩毅氏は、1)技術進歩や石油探査に対する投資によって増減する、2)原油価格が急騰した場合、以前よりもコストをかけて低品位であっても経済的に成り立つ――結果、3)埋蔵量は時間とともに増加する――、と述べています。
さらに、石油に限ったことではありませんが、地下資源は枯渇するほど価値が上がります。
そのため、石油の枯渇問題やオイル・ショックのような危機が起こる度に、新たな探査開発や資金投入、さらにはそれらによる技術革新が進むこととなり、結果として逆に埋蔵量が増加するというパラドックスが生じることにもあります。
石油は“持続する世界の共有財産(コモンズ)”
他方、たとえ原油が地下にあったとしても、採掘するためのコストが膨大な額となり経済的に釣り合わない場合、「(絶対埋蔵量としての)原油はあっても、(可採埋蔵量としての)石油はない」となります。また、同様にたとえ原油が地下にあったとしても、石油の需要がなくなれば、「(絶対埋蔵量としての)原油はあっても、(可採埋蔵量としての)石油は枯渇する」事態となるかもしれません。
しかしながら、今後もしばらく第一級・第一線の経済資源であり続けると予測される石油の需要が枯渇するような社会状況は、あまり現実的ではありません。そのため、今後もしばらく、石油は枯渇することなく供給されることが予想されます。
しかしながら当然のこととして、使えば使うほど絶対埋蔵量は減少します。また、そもそも論として、石油のような地下資源は、個人や企業、国や現代社会にさえとどまることなく、“持続する世界の共有財産(コモンズ)”です。
持続可能な未来のためにも、環境保全や国際政治のバランス等を考慮した意識や技術を革新し、正しく適切に無駄なく使うことが、今を生きる全人類に求められています。
<参考文献>
・『資源がわかればエネルギー問題が見える』(鎌田浩毅著、PHP新書)
・『結局、世界は「石油」で動いている』(佐々木良昭著、青春新書)
・「ピークオイル」[エネルギーシステム]『イミダス2018』([内山洋司著)
・「鎌田浩毅の役に立つ地学<4>「枯渇しない」石油のナゾ 採掘技術の進歩で増える「埋蔵量」」『週刊エコノミスト』(2020年6月2日号、鎌田浩毅著、毎日新聞出版)
・『資源がわかればエネルギー問題が見える』(鎌田浩毅著、PHP新書)
・『結局、世界は「石油」で動いている』(佐々木良昭著、青春新書)
・「ピークオイル」[エネルギーシステム]『イミダス2018』([内山洋司著)
・「鎌田浩毅の役に立つ地学<4>「枯渇しない」石油のナゾ 採掘技術の進歩で増える「埋蔵量」」『週刊エコノミスト』(2020年6月2日号、鎌田浩毅著、毎日新聞出版)
人気の講義ランキングTOP20










