テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
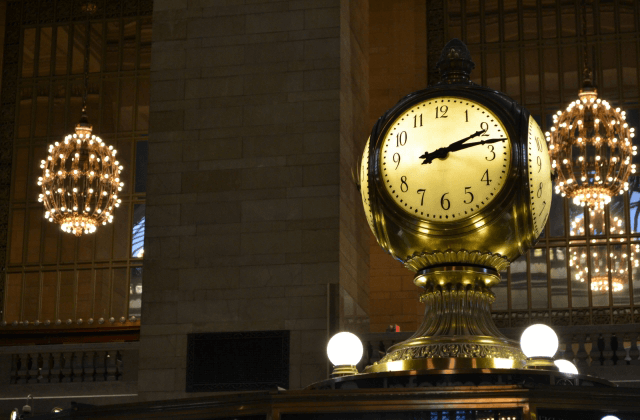
ニュースでよく聞く「未明」はいつのこと?
「関東では明日○日未明にかけて雨になるでしょう」「本日未明、容疑者が逮捕されました」……天気予報やニュースで聞くこの「未明」という言葉。時間帯を表すのだろうけど、なんとなく分かるようで分からない……という人は多いのではないでしょうか。この「未明」のほか、「深夜」「明け方」「日中」といった“時を表す用語”には、実はそれぞれきちんと時間帯が決まっているのです。
今回はそんな“時を表す用語”について解説します。
ニュースでもこの「午前0時~午前3時頃」を指して使われることが多いですが、場合によっては「午前0時~夜明けまで」か「夜遅い時間全体」を表すことも。いずれにしても「日にちを過ぎたあとの一定期間(午前0時以降)」を指すことがほとんどのようです。
そのほか、「未明」と似たような時間帯を指す言葉はいくつかあります。それぞれの時間の境界はどこでしょうか。気象庁ではこれらの言葉にも細かく時間帯を定義していますので、それを参考に並べて見ると、以下のようになります。
<夜間帯>
21時頃~24時(0時)頃……【夜遅く】
0時~3時頃……【未明】
3時頃~6時頃……【明け方】
(※気象庁「1日の時間細分図(府県天気予報の場合)」より抜粋)
以上のように、だいたい3時間ごとに区切って伝えていることがわかります。同じく朝~お昼の時間帯も、以下のように3時間ごとに言葉を使い分けているそうです。
<朝~昼間帯>
6時頃~9時頃……【朝】
9時頃~12時頃……【昼前】
12時ちょうど……【正午】
12時頃~15時頃……【昼過ぎ】
15時頃~18時頃……【夕方】
18時頃~21時頃……【夜のはじめ頃】
【きょう一杯、あす一杯】
「きょう一杯」とは予報発表時(5時または11時)からその日の24時まで。「あす一杯」とは「あすの0時~24時」のことです。
“一杯”とは有る限りを尽くす様、ありったけという意味なので、その日のすべての時間帯を指します。
【夜明け、夜明け前】
「明け方」が3時頃~6時頃を指すのに対し、「夜明け」は“日の出の前の空が薄明るくなる頃”という意味で、時間帯は決まっていません。季節によって日の出の時間は変わるので、それに合わせた汎用的な言葉ということになるでしょう。
そして「夜明け前(明け方前)」とは、“日の出の前2時間くらい”とされています。「明け方」と混同しやすいため気象庁ではこの言葉の使用を控え、「明け方」のほうを積極的に用いているようです。
【早朝、午前中、午後】
「朝」が6時頃~9時頃を表すのに対し、「早朝」の定義は“一般の人が活動を始める前”で、だいたい「夜明け(薄明るくなる頃)」から1~2時間とされています。
「午前中」は一般的には午前0時~正午までですが、天気予報では“予報発表時から正午までの期間”を指す時に使われます。それに対し「午後」は12時~24時です。
【日中】
「明日日中の最高気温は……」という使われ方をする「日中」は、午前9時頃から18時頃までとなっています。そのあとの18時頃から24時頃は「夜」です。夜の間ずっと、を表す言葉は「夜通し」となります。
【夜半】
0時の前後、それぞれ30分間くらいを合わせた1時間くらいを指します。ただし“日常的に使われない言葉”のため、気象庁の発表では使用を控えることになっています。
いかがでしたか。普段何気なく聞いている予報用語も、その言葉の時間帯が分かると予定も立てやすくなりますよね。天気予報やニュースでこれらの用語を聞いた時には、ぜひ思い出してみてください。
今回はそんな“時を表す用語”について解説します。
「未明」「明け方」「夜遅く」……朝、夜の時間帯を表す言葉
未明とは、読んで字のごとく夜が明けきらない時のことです。本来の意味、つまり辞書に載っている意味では午前3時~日の出前を指しますが、気象庁では「午前0時~午前3時頃」と定義しています。字面から「明らかになっていない(いつ頃かわからない)」という意味で認識している方も多いようですが、間違えないようにしましょう。ニュースでもこの「午前0時~午前3時頃」を指して使われることが多いですが、場合によっては「午前0時~夜明けまで」か「夜遅い時間全体」を表すことも。いずれにしても「日にちを過ぎたあとの一定期間(午前0時以降)」を指すことがほとんどのようです。
そのほか、「未明」と似たような時間帯を指す言葉はいくつかあります。それぞれの時間の境界はどこでしょうか。気象庁ではこれらの言葉にも細かく時間帯を定義していますので、それを参考に並べて見ると、以下のようになります。
<夜間帯>
21時頃~24時(0時)頃……【夜遅く】
0時~3時頃……【未明】
3時頃~6時頃……【明け方】
(※気象庁「1日の時間細分図(府県天気予報の場合)」より抜粋)
以上のように、だいたい3時間ごとに区切って伝えていることがわかります。同じく朝~お昼の時間帯も、以下のように3時間ごとに言葉を使い分けているそうです。
<朝~昼間帯>
6時頃~9時頃……【朝】
9時頃~12時頃……【昼前】
12時ちょうど……【正午】
12時頃~15時頃……【昼過ぎ】
15時頃~18時頃……【夕方】
18時頃~21時頃……【夜のはじめ頃】
「夜明け前」「早朝」「日中」……あいまいな時間を表す言葉
そのほか、一見するといつの時間か分かりにくい、ちょっとややこしい気象予報用語をご紹介しましょう。【きょう一杯、あす一杯】
「きょう一杯」とは予報発表時(5時または11時)からその日の24時まで。「あす一杯」とは「あすの0時~24時」のことです。
“一杯”とは有る限りを尽くす様、ありったけという意味なので、その日のすべての時間帯を指します。
【夜明け、夜明け前】
「明け方」が3時頃~6時頃を指すのに対し、「夜明け」は“日の出の前の空が薄明るくなる頃”という意味で、時間帯は決まっていません。季節によって日の出の時間は変わるので、それに合わせた汎用的な言葉ということになるでしょう。
そして「夜明け前(明け方前)」とは、“日の出の前2時間くらい”とされています。「明け方」と混同しやすいため気象庁ではこの言葉の使用を控え、「明け方」のほうを積極的に用いているようです。
【早朝、午前中、午後】
「朝」が6時頃~9時頃を表すのに対し、「早朝」の定義は“一般の人が活動を始める前”で、だいたい「夜明け(薄明るくなる頃)」から1~2時間とされています。
「午前中」は一般的には午前0時~正午までですが、天気予報では“予報発表時から正午までの期間”を指す時に使われます。それに対し「午後」は12時~24時です。
【日中】
「明日日中の最高気温は……」という使われ方をする「日中」は、午前9時頃から18時頃までとなっています。そのあとの18時頃から24時頃は「夜」です。夜の間ずっと、を表す言葉は「夜通し」となります。
【夜半】
0時の前後、それぞれ30分間くらいを合わせた1時間くらいを指します。ただし“日常的に使われない言葉”のため、気象庁の発表では使用を控えることになっています。
いかがでしたか。普段何気なく聞いている予報用語も、その言葉の時間帯が分かると予定も立てやすくなりますよね。天気予報やニュースでこれらの用語を聞いた時には、ぜひ思い出してみてください。
<参考サイト>
・時に関する用語(気象庁)
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/toki.html
・時に関する用語(気象庁)
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/toki.html
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
昭和陸軍の派閥抗争には三つの要因があった
中西輝政










