テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
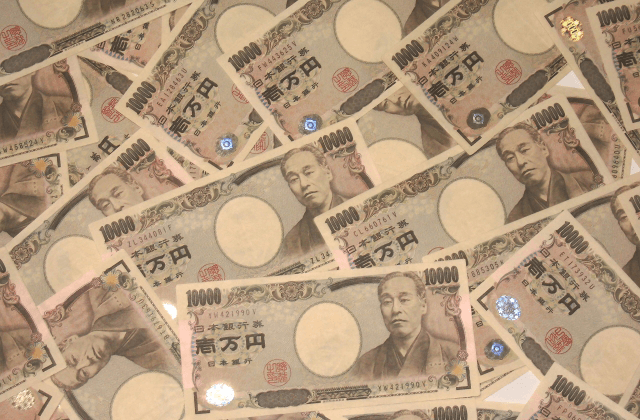
「ブル弁」「ケー弁」「イソ弁」って?弁護士の年収&稼ぎ最前線
世紀の変わり目の一大事業として行なわれた「司法制度改革」。その結果、弁護士の所得に異変が起こっているとする説がある。今回は、高所得&難関資格のシンボルとして医師の双璧をなす弁護士を取り上げてみたい。
個人事務所を開設する弁護士の22%が年間所得100万円以下という国税庁の調査結果もある、というが、これは弁護士の「働き方」の事情を考えてみればよくわかる。
弁護士は、法律事務所に属しながら、個人で手がけた案件は「個人事務所」の収入にする、というケースが少なくない。また、主な収入を政治や芸能活動に頼っている弁護士の方々も、よく見かける。おそらく、年間所得100万円以下は個人事務所としての年間収支で、弁護士個人の収支でみるならば「それをメインの収支にはしていない」と考えるのが常識的であろう。
その代表格として、「4大事務所(Big Four)」と呼ばれる大規模な法律事務所があることを、皆さんはご存じだろうか。大手門タワーに事務所を構える「西村あさひ法律事務所」(弁護士502名)、丸の内KITTEのあるJPタワー36Fを受付とする「長島・大野・常松法律事務所」(弁護士370名)、丸の内パークビルディングに東京オフィスを持つ「森・濱田松本法律事務所」(弁護士372名)、少し離れて赤坂Kタワーにある「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」(弁護士440名)。
彼らの平均年収は、新卒でも最低1000万円からスタートというのが司法改革以前の常識だったが、現在では800~900万円台が初任給と言われている。「それでも高給取り!」なのは間違いない。ただ、ロースクールの学費を奨学金でまかなっているケースも多く、他の資格と比べて「借金スタート」組も少なくない。
ブル弁との比較で、事務所を置かず、携帯電話で仕事を受ける弁護士を「ケータイ弁(ケー弁と呼ぶ)」といわれています。実際には弁護士の事務所登録には必ず固定電話が必要なので、これはアダ名にすぎない。
昔の呼び名では、事務所に居候して、自分の案件を増やしていく段階の若手弁護士が「イソ弁」だったが、現在では「アソシエイト」と呼ばれている。大手・準大手では、ほぼ3年が「ジュニア・アソシエイト」と呼ばれる期間。年俸は毎年約100万円ずつ上がるが、労働時間の厳しさ・ブラックさに耐えかねて半数が辞めていくような事務所もあるとのこと。その後、登録4年目に「シニア・アソシエイト」となってからはさらに実力がものをいう。「ブル弁」の世界でアソシエイトから「パートナー」に移行すれば、数億円以上の年俸を稼ぎ出す弁護士も少なくないのだ。
これまでは「独立してボス弁になる」のが「イソ弁」の夢だったが、大手事務所の統合によって「1人事務所所属」の弁護士数は10年前の45.28%から25.92%に下がっている。司法制度改革による需要と供給のアンバランスではなく、大手による「寡占状態」が続いていることがよくわかる。
また、超高齢社会における最大の朗報として、弁護士には「定年」がない。「弁護士白書」2015年版によると、日本の弁護士総数は36415人(うち女性6618人)。このうち80歳以上が1407人(うち女性57人)を数える。
日本人の平均寿命が男性80.5歳、女性86.8歳であるのと照合すると、「死ぬまで稼げる」資格であることは間違いない。
「食えない」弁護士もいるって、本当?
「弁護士食えない説」が浮上してきたのは、この2-3年。「弁護士 食えない」で検索してみると、「5人に1人が生活保護受給者並みの低所得にあえいでいる」などの情報が出回っていることが分かる。個人事務所を開設する弁護士の22%が年間所得100万円以下という国税庁の調査結果もある、というが、これは弁護士の「働き方」の事情を考えてみればよくわかる。
弁護士は、法律事務所に属しながら、個人で手がけた案件は「個人事務所」の収入にする、というケースが少なくない。また、主な収入を政治や芸能活動に頼っている弁護士の方々も、よく見かける。おそらく、年間所得100万円以下は個人事務所としての年間収支で、弁護士個人の収支でみるならば「それをメインの収支にはしていない」と考えるのが常識的であろう。
ブル弁からケータイ弁までいる弁護士の世界
「ブル弁」とは「ブルジョワ弁護士」の略。大企業相手にM&Aや国際商取引、特許訴訟などの業務を請け負い、高額の報酬を受け取る一部弁護士を指す呼び名である。その代表格として、「4大事務所(Big Four)」と呼ばれる大規模な法律事務所があることを、皆さんはご存じだろうか。大手門タワーに事務所を構える「西村あさひ法律事務所」(弁護士502名)、丸の内KITTEのあるJPタワー36Fを受付とする「長島・大野・常松法律事務所」(弁護士370名)、丸の内パークビルディングに東京オフィスを持つ「森・濱田松本法律事務所」(弁護士372名)、少し離れて赤坂Kタワーにある「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」(弁護士440名)。
彼らの平均年収は、新卒でも最低1000万円からスタートというのが司法改革以前の常識だったが、現在では800~900万円台が初任給と言われている。「それでも高給取り!」なのは間違いない。ただ、ロースクールの学費を奨学金でまかなっているケースも多く、他の資格と比べて「借金スタート」組も少なくない。
ブル弁との比較で、事務所を置かず、携帯電話で仕事を受ける弁護士を「ケータイ弁(ケー弁と呼ぶ)」といわれています。実際には弁護士の事務所登録には必ず固定電話が必要なので、これはアダ名にすぎない。
固定報酬ではない弁護士の世界
大手や中小の法律事務所に所属できたとしても、それは一般企業における「就職」と完全には合致しない。全て固定給という事務所は少なく、インセンティブが年俸の3分の1から半分に及ぶ事務所が多いのだ。昔の呼び名では、事務所に居候して、自分の案件を増やしていく段階の若手弁護士が「イソ弁」だったが、現在では「アソシエイト」と呼ばれている。大手・準大手では、ほぼ3年が「ジュニア・アソシエイト」と呼ばれる期間。年俸は毎年約100万円ずつ上がるが、労働時間の厳しさ・ブラックさに耐えかねて半数が辞めていくような事務所もあるとのこと。その後、登録4年目に「シニア・アソシエイト」となってからはさらに実力がものをいう。「ブル弁」の世界でアソシエイトから「パートナー」に移行すれば、数億円以上の年俸を稼ぎ出す弁護士も少なくないのだ。
これまでは「独立してボス弁になる」のが「イソ弁」の夢だったが、大手事務所の統合によって「1人事務所所属」の弁護士数は10年前の45.28%から25.92%に下がっている。司法制度改革による需要と供給のアンバランスではなく、大手による「寡占状態」が続いていることがよくわかる。
80歳を越えても生涯現役!
弁護士の働き方はプロスポーツ選手などと同じで、事務所に「所属」はしているが、生涯保証があるわけではない。しかし弁護士の働き方は、スポーツ選手や芸能人とは比較にならないほどフレキシブル。企業顧問や法律相談、出身大学や法律予備校で講義を持つなど、資格を活かした役割を数通り兼ねるのが、平均的な都市部の弁護士像となる。また、超高齢社会における最大の朗報として、弁護士には「定年」がない。「弁護士白書」2015年版によると、日本の弁護士総数は36415人(うち女性6618人)。このうち80歳以上が1407人(うち女性57人)を数える。
日本人の平均寿命が男性80.5歳、女性86.8歳であるのと照合すると、「死ぬまで稼げる」資格であることは間違いない。
人気の講義ランキングTOP20










