テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
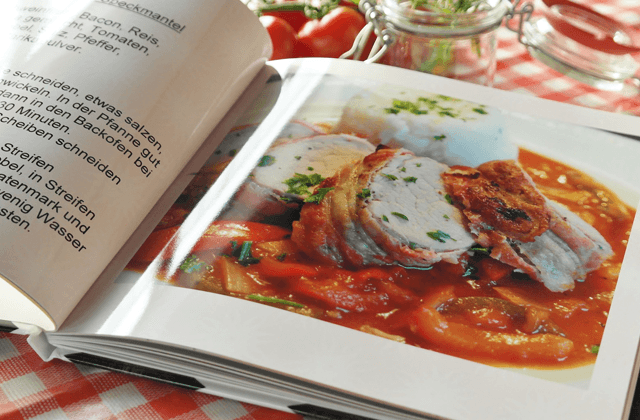
ハイカロリーから理系の料理まで!秋に読む料理本5選
書店の一角にずらりと並ぶ料理本。レパートリーを増やそうと新しい一冊を探しにいっても、たくさんありすぎてどれを選んでいいかわからない、そんな声をよく聞きます。料理が得意ではない、という人にとっては料理本選びも簡単なことではないはず。
今回は、あまり料理をしない方も、料理のレパートリーがマンネリ気味という方も、思わず「作ってみたい!」と思うような、美味しく楽しい料理本をご紹介。秋の味覚を求めてグルメなお店に足を運ぶのもいいですが、せっかくの「食欲の秋」、料理本片手に新しいメニューにチャレンジしてみるのもまた一興。「読書の秋」としても楽しめるような、読むだけでもおもしろい変わり種な料理本をセレクトしてみました。
「ダイエットって美味しいの?」とばかりに、健康指向の世の中に対し、食欲という本能を貫くのがこの一冊。カロリーも糖質も上限なし、「美味しい」だけを追求した享楽的なレシピの数々が、ページを繰る度に脳内にドーパミンを分泌させ、読む人をハッピーに。食いしん坊で豊満な魅力を放つ女性料理家ふたりがタッグを組み、肉に炭水化物にスイーツと「食べる喜び」を思い出させてくれる衝撃のハイカロリー料理本です。
料理は勘とセンス、と言う人もいますが、「料理は科学」ともいわれます。そんな理論派の料理男子に最近話題なのがこちら。多くのレシピ本には、調味料は適量、などと書かれていることも多く、「適量って何グラムなんだ!」と腹立たしく思っていた人に応えてくれる一冊。レシピだけでなく、用意するキッチンツールや鍋のサイズ、火加減や手順表まで、徹底的に解説。美味しい料理には理由がある、と納得させられます。
便利なキッチングッズは多々ありますが、実は料理を作り出す一番のツールは「手」。料理研究家で文筆家でもある平松さんが、割く・混ぜる・捏ねる・揉む・ちぎる、といった料理を生む「手」の動作をテーマに書いた珠玉の料理エッセイ。韓国の定番料理キムチやナムルも、箸で混ぜるのではなく、手で混ぜて揉んで押して、のひと手間でびっくりするほど味がよく馴染む。そんな手から生まれる美味しいヒントを教えてくれます。
秋に美味しくなるものといったら、フルーツ。こちらはフルーツを朝食やデザートとしてだけでなく、おかずや食事に昇華させた一冊。料理にフルーツというと、酢豚のパイナップルのように「ありえない!」と思う人も多いようですが、そんなことを言っていては食わず嫌いも甚だしいと叱られてしまうくらいに、完成度の高い果物料理が登場。食卓がマンネリ気味と嘆いている方は、ぜひこの本でチャレンジを。
料理の腕が如実にあらわれるといわれる料理が、野菜炒め。火加減や調味料にこだわる人は多いですが、切り方でも仕上がりが違ってくると意識したことはありますか。ピーマンは横より縦に切ったほうが苦味が少なく旨味を感じられ、ナスは切り方によって火の通りが変わってきます。そんな野菜のカットのコツを学べ、料理初心者でも作れるシンプルで美味しいレシピが紹介されています。子どもの野菜嫌いも切り方次第で克服できるかも。
ということで、気になる料理本はありましたか。忙しいとつい外食やお惣菜に頼りがちになりますが、料理の時間を「義務」ではなく「楽しい」時間に変えてくれる料理本を、あなたも探してみてはいかがでしょうか。
今回は、あまり料理をしない方も、料理のレパートリーがマンネリ気味という方も、思わず「作ってみたい!」と思うような、美味しく楽しい料理本をご紹介。秋の味覚を求めてグルメなお店に足を運ぶのもいいですが、せっかくの「食欲の秋」、料理本片手に新しいメニューにチャレンジしてみるのもまた一興。「読書の秋」としても楽しめるような、読むだけでもおもしろい変わり種な料理本をセレクトしてみました。
カロリー無制限。欲望を満たす満腹レシピ
『禁断のレシピ』(枝元なほみ・多賀正子著、NHK出版)「ダイエットって美味しいの?」とばかりに、健康指向の世の中に対し、食欲という本能を貫くのがこの一冊。カロリーも糖質も上限なし、「美味しい」だけを追求した享楽的なレシピの数々が、ページを繰る度に脳内にドーパミンを分泌させ、読む人をハッピーに。食いしん坊で豊満な魅力を放つ女性料理家ふたりがタッグを組み、肉に炭水化物にスイーツと「食べる喜び」を思い出させてくれる衝撃のハイカロリー料理本です。
料理男子もハマる、話題沸騰の左脳系レシピ
『チューブ生姜適量ではなくて1cmがいい人の理系の料理』(五藤隆介著、秀和システム)料理は勘とセンス、と言う人もいますが、「料理は科学」ともいわれます。そんな理論派の料理男子に最近話題なのがこちら。多くのレシピ本には、調味料は適量、などと書かれていることも多く、「適量って何グラムなんだ!」と腹立たしく思っていた人に応えてくれる一冊。レシピだけでなく、用意するキッチンツールや鍋のサイズ、火加減や手順表まで、徹底的に解説。美味しい料理には理由がある、と納得させられます。
「手」は最上の料理道具と知る、食のエッセイ本
『世の中で一番おいしいのはつまみ食いである』(平松洋子著、文春文庫)便利なキッチングッズは多々ありますが、実は料理を作り出す一番のツールは「手」。料理研究家で文筆家でもある平松さんが、割く・混ぜる・捏ねる・揉む・ちぎる、といった料理を生む「手」の動作をテーマに書いた珠玉の料理エッセイ。韓国の定番料理キムチやナムルも、箸で混ぜるのではなく、手で混ぜて揉んで押して、のひと手間でびっくりするほど味がよく馴染む。そんな手から生まれる美味しいヒントを教えてくれます。
フルーツ×料理の、美味しい進化が止まらない
『果物料理』(渡辺康啓著、平凡社)秋に美味しくなるものといったら、フルーツ。こちらはフルーツを朝食やデザートとしてだけでなく、おかずや食事に昇華させた一冊。料理にフルーツというと、酢豚のパイナップルのように「ありえない!」と思う人も多いようですが、そんなことを言っていては食わず嫌いも甚だしいと叱られてしまうくらいに、完成度の高い果物料理が登場。食卓がマンネリ気味と嘆いている方は、ぜひこの本でチャレンジを。
目からウロコ。野菜の味は切り方にあります
『ウー・ウェンの野菜料理は切り方で決まり!』(ウー・ウェン著、文化出版局)料理の腕が如実にあらわれるといわれる料理が、野菜炒め。火加減や調味料にこだわる人は多いですが、切り方でも仕上がりが違ってくると意識したことはありますか。ピーマンは横より縦に切ったほうが苦味が少なく旨味を感じられ、ナスは切り方によって火の通りが変わってきます。そんな野菜のカットのコツを学べ、料理初心者でも作れるシンプルで美味しいレシピが紹介されています。子どもの野菜嫌いも切り方次第で克服できるかも。
ということで、気になる料理本はありましたか。忙しいとつい外食やお惣菜に頼りがちになりますが、料理の時間を「義務」ではなく「楽しい」時間に変えてくれる料理本を、あなたも探してみてはいかがでしょうか。
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










