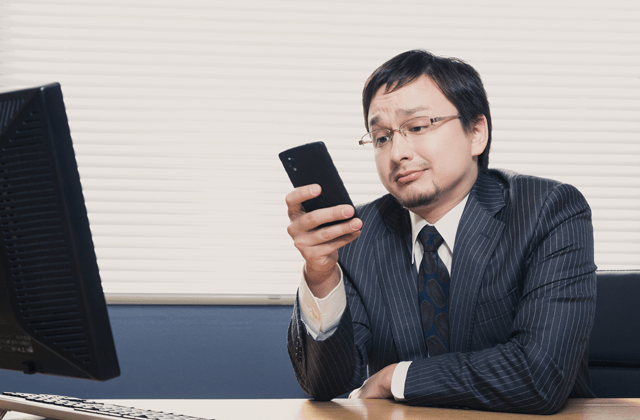
トラブル急増!職場で起こる「LINEいじめ」
スマートフォンとLINEが当たり前になった日本では、いつどこにいても連絡を取ることができます。職場でのやりとりにLINEを使っているという状況も多くなってきているようです。「いつでもつながっている時代」となったわけですが、便利な反面、いくつかの問題も起こっているのです。
また、パピマミというサイトでは入社したばかりの女性社員(22)の事例を取り上げています。その女性社員が仕事でミスをした際、上司はLINEグループの中で責めたそうです。その理由は、同僚に反省の態度を示すためということだったようですが、上司からのLINEによるメッセージは深夜や休日も続き、ついには「既読なっているのになぜ返信しないのか」といった内容のメッセージが届くようになります。その後、人事部に現状を訴えたその女性社員は後日、部署異動させてもらえたとのことです。
では「スルー」されるとなぜつらいのでしょうか。『99.996%はスルー 進化と脳の情報学』(竹内薫・丸山篤史著、講談社)によると、その要因に「承認要求」と「コントロール要求」があるようです。「既読スルー」は、この欲求が満たされないものとして感じ取られます。たしかにそういったメッセージアプリを使うことで、スピード感をもって仕事を推し進めたり、職場の一体感をつくり出したりする狙いが上司にあるのかもしれません。しかし、「既読」したからには必ず反応するべきだ、という発想はどうでしょう。ただ欲求の充足を求めているだけという状況になりかねません。
職場LINEによるハラスメントは現在、増加傾向にあるといいます。もし、あなたが上司の立場なら、LINEグループを利用する場合、「勤務時間外は使わない」「事務連絡以外は使用しない」などはっきりとしたルールを考えるべきかもしれません。
一方、あなたが部下の立場でもし問題が発生した場合には、会社にハラスメント相談窓口があれば、そこに相談するか、相談しづらいようなら、労働局や労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーなどを利用するということも頭に入れておくといいでしょう。大事なことは一人で我慢せず、必ず周りに相談することです。
LINEグループでのトラブル
例えば、東洋経済ONLINEでは会社員の女性(28)の事例が取り上げられています。その女性は、職場のLINEグループで積極的に発言しないことを上司にとがめられたそうです。ついには「既読してるなら返事しろよ」といったメッセージが個人的に送られるようになります。その後、彼女はメンタル不全に陥って休職することになるのですが、彼女が人事部や産業医と面談をした際にこのことが発覚し、その上司は転勤、降格処分となったそうです。また、パピマミというサイトでは入社したばかりの女性社員(22)の事例を取り上げています。その女性社員が仕事でミスをした際、上司はLINEグループの中で責めたそうです。その理由は、同僚に反省の態度を示すためということだったようですが、上司からのLINEによるメッセージは深夜や休日も続き、ついには「既読なっているのになぜ返信しないのか」といった内容のメッセージが届くようになります。その後、人事部に現状を訴えたその女性社員は後日、部署異動させてもらえたとのことです。
「既読スルーするな」と言うことの強迫性
これらの事例から注目したいのは、「既読スルー」というキーワードです。LINEは時と場所を選ばず、「既読」という状況だけが確実に伝わります。またLINEグループの活用にいたっては、同調圧力も働き、一人だけ異なる意見は言いづらく、うまく伝えるとしても文字だけでは慎重になるはずです。中には相手が望むような意欲的な言葉を「即レス」する人もいるでしょう。しかし、よく考えて発言しようとする人ほど、返すのに時間がかかることもあります。また、今は何も反応しないほうがいいかもしれないという判断もありえます。では「スルー」されるとなぜつらいのでしょうか。『99.996%はスルー 進化と脳の情報学』(竹内薫・丸山篤史著、講談社)によると、その要因に「承認要求」と「コントロール要求」があるようです。「既読スルー」は、この欲求が満たされないものとして感じ取られます。たしかにそういったメッセージアプリを使うことで、スピード感をもって仕事を推し進めたり、職場の一体感をつくり出したりする狙いが上司にあるのかもしれません。しかし、「既読」したからには必ず反応するべきだ、という発想はどうでしょう。ただ欲求の充足を求めているだけという状況になりかねません。
大事なことはルールを作ること、問題があれば一人で悩まないこと
LINEのようなメッセージアプリはメールと同様、いつでも読むことができる反面、「既読」機能によってリアルタイムに相手に状況が伝わるという点で、プライベートと仕事の時間を曖昧にしてしまうツールでもあります。職場LINEによるハラスメントは現在、増加傾向にあるといいます。もし、あなたが上司の立場なら、LINEグループを利用する場合、「勤務時間外は使わない」「事務連絡以外は使用しない」などはっきりとしたルールを考えるべきかもしれません。
一方、あなたが部下の立場でもし問題が発生した場合には、会社にハラスメント相談窓口があれば、そこに相談するか、相談しづらいようなら、労働局や労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーなどを利用するということも頭に入れておくといいでしょう。大事なことは一人で我慢せず、必ず周りに相談することです。
<参考サイト>
・東洋経済ONLINE
http://toyokeizai.net/articles/-/133000?page=2
・パピマミ
http://papimami.jp/53911
・東洋経済ONLINE
http://toyokeizai.net/articles/-/133000?page=2
・パピマミ
http://papimami.jp/53911
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







