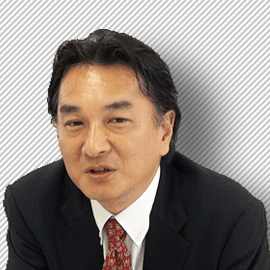●安全という言葉が、ちゃんと定義されていない
慶應義塾大学理工学部管理工学科教授の岡田有策です。近年、企業は「安全管理」や「安全・安心」といった言葉を掲げて、様々な活動を行っています。しかし、安全という言葉がどのように理解され、どのような考え方で安全に向けた取り組みが進んでいるのかというと、現実を見れば、実は怪しいところがあります。一見、分かったような気になっていながら、安全という言葉が、ちゃんと定義されていないことがあるのです。
もちろん、安全工学や安全学といった学問がありますし、安全という言葉の工学的定義は存在します。それは言い換えれば、事故の定義です。本来、事故とは、人間の生命・財産に損害を与えるものとして、定義されます。分かりやすく言えば、人が死ぬか死なないかということが、事故の根本にあるわけです。したがって、人が死ななければ安全だといっても差し支えありません。これが安全に対する本来の考え方の、ポイントです。
例えば、学問上は、人が死ぬ事故が起こったときには、当然その分析をして対策を打ちますし、「事故リスク」も、人が死ぬ可能性や確率を考えて分析をするということです。こうした考え方で研究をしている段階であれば、非常に分かりやすいでしょう。人が死ぬということは、生命学的にはっきりと定義ができるからです。
●過去の事例からは将来のことは分からない
ところが、日本が典型例ですが、次第に、「安全っぽい」ことが話題に上り、人が死ななかったとしても命に関わりそうなこと、あるいは生命・財産に影響しそうなことが問題になってきています。こうしたものを総称して、「安全に対する取り組み」が議論されるようになったのは、ここ20年ぐらいのことです。
確かに、人の死亡する事故をどれだけ減らしていくかということでいえば、方向性としては何も間違ってはいません。しかしその反面、現場の人間からみた場合に、安全とは何かが見えなくなってきているという状況が生じています。
例えば、ほとんどの企業で「安全とは何ですか」と聞くと、現場の係員レベルでは「事故がないことだ」という答えが返ってきます。さらに、「それでは事故とはなんですか」と聞くと、「例えば、これこれ」といったように、過去の事例で答えようとします。
しかし、当たり前ですが、過去の事例からは将来のことは分かり...