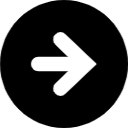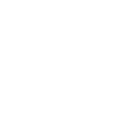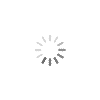この講義シリーズは第2話まで
登録不要で無料視聴できます!
逆境の克服とリーダーの胆力
松下幸之助が目指したのは政治の名人をつくること
逆境の克服とリーダーの胆力(8)2つのマインドの両立
神藏孝之(公益財団法人松下幸之助記念志財団 理事 /松下政経塾塾長代理/テンミニッツ・アカデミー論説主幹)
松下政経塾を立ち上げた松下幸之助の原点にあったのは、国家経営を誤れば全員が不幸になるという考えだった。公益財団法人松下政経塾副理事長・イマジニア株式会社代表取締役会長兼CEOの神藏孝之氏がシリーズレクチャーの最後に、リーダーにとって重要な2つのマインドについて語る。(全8話中第8話)
時間:8分07秒
収録日:2018年1月19日
追加日:2018年7月17日
収録日:2018年1月19日
追加日:2018年7月17日
≪全文≫
●菅官房長官が最も評価していた役人は香川氏だった
香川俊介氏の目『正義とユーモア』を制作した時、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏が、紙面上で追悼文を書いてくれました。香川氏の特徴を非常によく描いてくれています。中でも菅義偉官房長官と香川氏のやり取りは、興味をそそります。
菅氏が役人の中で最も評価していた人の一人は、香川氏でした。しかし、香川氏が消費増税に向けて動けば政局になってしまうから、そんなことはやめてくれと、菅氏は諭したそうです。追悼文集の中に書かれています。
私は菅氏の原稿を読んだ時、大変驚きました。「確かに追悼文集はプライベートで発刊しますが、内容は必ずマスコミに漏れます。こんな内容を載せても構わないのでしょうか」と菅氏の秘書官に確認しましたが、それで構わないとのことでした。
●日本にも改革者がいないわけではない
また、読売新聞の望月公一氏が記事にしてくれましたが、追悼文集では歴史学者の山内昌之先生が、香川氏のことを日露戦争の前に亡くなった川上操六と田村怡与造という、2人の代表的な参謀に例えて、彼の死を悼んでいます。川上と田村は日露戦争に心血を注いで亡くなっていったのですが、同様に香川氏も日本の大いなる改革者だったという内容です。日本にも改革者がいないわけではないと、おっしゃりたいのだと思います。
『正義とユーモア』を作って非常に良かったと思うことがあります。現在、霞が関の中には改革官僚としてのロールモデルがいません。この追悼文集が役人たちのバイブルになれば良いなと思います。役人の中にはこんな生き方をした人がいたのだということが、この本を読めば分かります。
人間は死ぬ前に何かに残して置かなければ、すぐに忘れ去られてしまうものです。人間の記憶は当てになりませんから。その人生を文章に残すことで、機会があればそれを読み返し、香川俊介という人間をその人の心の中でよみがえらせることができます。
●「経営マインド」と「パブリックマインド」の両立が課題
今回お話したことをまとめましょう。松下幸之助は老人の道楽で政経塾をつくったとしばしば言われますが、老人の道楽などでは全くありませんでした。松下は真剣でした。政経塾1期生の若者を85才の人間が叱るということは、真剣でなければできません。「猫に小...
●菅官房長官が最も評価していた役人は香川氏だった
香川俊介氏の目『正義とユーモア』を制作した時、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏が、紙面上で追悼文を書いてくれました。香川氏の特徴を非常によく描いてくれています。中でも菅義偉官房長官と香川氏のやり取りは、興味をそそります。
菅氏が役人の中で最も評価していた人の一人は、香川氏でした。しかし、香川氏が消費増税に向けて動けば政局になってしまうから、そんなことはやめてくれと、菅氏は諭したそうです。追悼文集の中に書かれています。
私は菅氏の原稿を読んだ時、大変驚きました。「確かに追悼文集はプライベートで発刊しますが、内容は必ずマスコミに漏れます。こんな内容を載せても構わないのでしょうか」と菅氏の秘書官に確認しましたが、それで構わないとのことでした。
●日本にも改革者がいないわけではない
また、読売新聞の望月公一氏が記事にしてくれましたが、追悼文集では歴史学者の山内昌之先生が、香川氏のことを日露戦争の前に亡くなった川上操六と田村怡与造という、2人の代表的な参謀に例えて、彼の死を悼んでいます。川上と田村は日露戦争に心血を注いで亡くなっていったのですが、同様に香川氏も日本の大いなる改革者だったという内容です。日本にも改革者がいないわけではないと、おっしゃりたいのだと思います。
『正義とユーモア』を作って非常に良かったと思うことがあります。現在、霞が関の中には改革官僚としてのロールモデルがいません。この追悼文集が役人たちのバイブルになれば良いなと思います。役人の中にはこんな生き方をした人がいたのだということが、この本を読めば分かります。
人間は死ぬ前に何かに残して置かなければ、すぐに忘れ去られてしまうものです。人間の記憶は当てになりませんから。その人生を文章に残すことで、機会があればそれを読み返し、香川俊介という人間をその人の心の中でよみがえらせることができます。
●「経営マインド」と「パブリックマインド」の両立が課題
今回お話したことをまとめましょう。松下幸之助は老人の道楽で政経塾をつくったとしばしば言われますが、老人の道楽などでは全くありませんでした。松下は真剣でした。政経塾1期生の若者を85才の人間が叱るということは、真剣でなければできません。「猫に小...
「経営ビジネス」でまず見るべき講義シリーズ
人気の講義ランキングTOP10
【10分解説】中島隆博先生《AI時代と人間の再定義》
テンミニッツ・アカデミー編集部
ヒトが罪を犯す理由…脳の働きから考える「善と悪」
長谷川眞理子