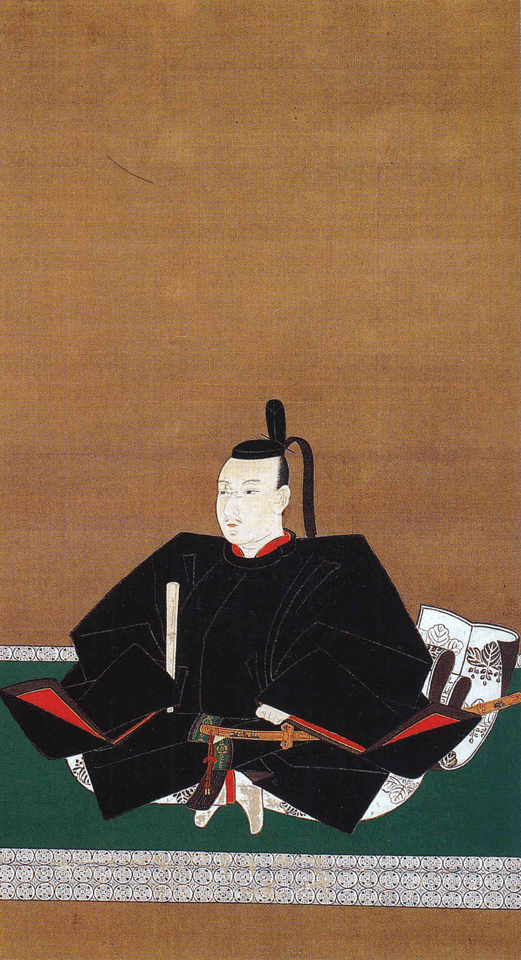●織田信長の官職辞職は新たな国家構想の証か
今回は、このようなかたちで諸勢力と共存して国内を統合していく上で、また家臣たちとともに政権、織田権力を運営していく状況のなかで、織田信長自身はどうあろうとしたのか、ということについて見ていきたいと思います。
一般的には信長というと、いつまでも国内にとどまっているのではなく、国の枠を越えていく新たな国家構想を描いていたといわれているかと思います。
その証とされるのが、天正六(1578)年四月に起きた信長の官職辞職で、その時についていた右大臣と右近衛大将を辞めてしまったところにあったかと思います。それが、信長が新たな国家構想を描いた証だと言われるのですが、果たしてそうなのか。今回はそのことについてお話ししていきたいと思います。
そもそも信長にとって官位というものがどうあったのかというところからです。信長が「権大納言兼右近衛大将」になったのは、天正三(1575)年十一月でした。これによって信長がどういう立場になったかというと、まず「権大納言」の立場によって足利義昭個人と同等になりました。また、「右近衛大将」というのは源頼朝が就任しており、足利義昭の父である足利義晴も早くに将軍を辞めた後に任ぜられた立場ですから、「武家の棟梁」にふさわしい立場であり、ステータスでした。
その職に就いたことで、信長は自分が足利家に代わって天下を統治していく存在であることを世間に示したということになっていると思います。さらに信長は、その後、最終的に「正二位右大臣兼右近衛大将」という当時の武家における最高位、任官士(武家のなかでの任官者)のなかでの最高の立場に就くことになっていきます。
●織田信長は辞官しても朝廷との関係を絶つことはなかった
信長にとって、官位というのは、自身が足利家に代わって天下人にあることを世間に示すステータスであったわけです。そのステータスとしてあった官職を、天正六年(1578)四月に信長は辞めてしまうことになります。今までは、信長がここから国家構想を描き出したといわれてきましたが、果たしてそうなのかという問題があります。
なぜならば、その時に辞める理由を書いた信長の書簡を見ると、次のように言っているからです。信長自...