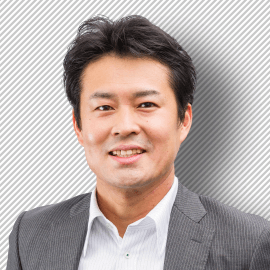●「働く」とは、キャリア資本を蓄積していくこと
―― 前回非常に重要な話をうかがいましたが、20年も30年も仕事をしてきて、しかも例えば「経理一筋30年」のような人の場合、それを手放すのが怖いというところも多分あるでしょう。また、変わっていくといっても、例えば「入社したときは製造のほうをやりたかったが、もう今さらね」ということになりがちだと思います。
人間の性格的な部分でのアイデンティからいっても、例えば「40年間生きてきたが、ここまできたものは、これしかない」というように、何かしら変わることへの怖さもあるかもしれないと思うわけです。これをどう変えるかというところで、プロティアン・キャリアの考え方は、全くガラッと変えるということでもないようですが、どういうイメージなのでしょうか。
田中 それには、こちらのスライドを見て、皆さんの中で起きていることをご理解いただくと分かりやすいかと思います。これからの「働く」というのは、キャリア資本を蓄積していくことだ、ということです。
同じメンバー、同じ仕事で長年働いていると、ビジネス資本の中の経験値が貯まっていきます。つまり、組織の中のプロフェッショナル化が起こり、「あの人に聞けば、なんでも分かるよね」というようになっていく。それは非常に大事なことで、ビジネス資本が貯まっていくと考えるわけです。
しかし、ビジネス資本というのはなくなりません。むしろ新しいチャレンジをしていったほうが、アドオン型でビジネス資本が貯まっていきます。
●ピボット型のキャリア形成とキャリアの日常化
田中 そのときの考え方をお伝えすると、例えば私などもミドルシニアのキャリア年齢に入ってきましたので、今までやってきたことを捨てようとは考えず、むしろ「ピボット」しようと思います。軸足として一つの支柱をつけ、これまでの専門性にもう一つ興味のあることをプラスする。それを社外で取り組んでもいいだろうし、学びというやり方でも副業のように働くやり方もある。さらにボランティア的な関わり方で、アドバイジングだけはしていくような方法もあるから、多様な形でキャリア資本を育てていけます。
つまり、プロティアン・キャリアはピボット型で、今までの蓄積を生かしつつ、しなやかに変幻していく。個人個人にとって、今までの...