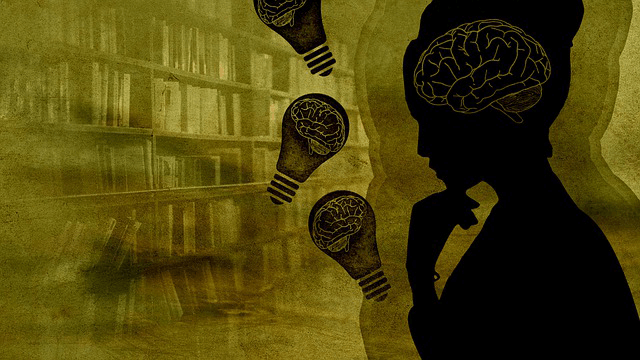●1990年代に話題になった「教養とは何だろうか」
―― 皆さま、こんばんは。本日は小宮山宏先生、長谷川眞理子先生に、「現代人に必要な『教養』とは?」というテーマでお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
小宮山 よろしくお願いします。
長谷川 よろしくお願いします。
―― 早速本編に入りたいと思います。実はこのテーマについて(事前に)ご参加の皆さんに質問を募集したところ、いくつかいただいています。一つはまさにタイトル通りで、「そもそも教養とは何か」ということです。
「現代において教養が重要だと各方面から口酸っぱく言われます。でも、そもそも教養とは何ですかと聞き返すと、答えられる人は案外少ない」ともいわれています。そういう中で、「では、本当の教養というものを、われわれはどう理解すればいいのですか」というご質問になります。
まず、ここを長谷川眞理子先生にお訊きしたいと思います。長谷川先生には、先日公開したばかりの「『今、ここ』からの飛躍のための教養」(2022年5月25日配信開始)という講義をいただきました。そこでかなり詳しくお話をいただいているので、ここでは手短にお話をいただけると有難いと思います。
長谷川 「教養とは何だろうか」というのは、次々に大学が教養部をやめてしまった1990年代初め頃、ずいぶん話題になりました。大学の先生たちの中でも、「それでは教養とは何か」と言い始めると、侃々諤々するばかりで駄目なので、もう定義の話はやめましょうということが多かったですね。
でも、やはり「リベラルアーツ」ということが元で、リベラルは「リベレートする(=解放する)」だから、今の自分の限界を超える、今の自分の考えの枠を超える、自分で考え、自分で決断するための基礎になるようなものということでいいのではないかと思います。
―― やはり、それらの基礎という部分なのですね。
長谷川 ものを考える基礎ということです。
●教養とは「よりよく生きるための知の力」
―― 考える基礎という今のお話を受けて、小宮山先生、その点はいかがですか。
小宮山 基本的にそうなのだろうと思いますが、私は東京大学(以下、東大)の頃にずっと3つのキーワードを言い続けてきました。それは「本質を捉える知」「他者を感じる力」、それから「先頭に立つ勇気」です。この3つをいろいろなところで言い...